現代ネット社会にも通じる心理──アンチの存在が信者の結束を強める
この研究は現代では主流の心理学研究の多くが発表前だった70年前のものです。
そのため、当時は認知的不協和理論の枠組みのみでこの現象が説明されましたが、現在ではフェスティンガーのこの興味深い観察報告について、より多層的な解釈が可能になっています。
まず注目されているのが社会的アイデンティティ理論(Social Identity Theory)です。これは1970年代にイギリスの社会心理学者ヘンリー・タジフェルらによって提唱されました。
この理論によれば、人は「自分がどの集団に属しているか」によって自己評価や行動を決める傾向があり、無意識のうちに周囲の人達を「内集団(ingroup、自分たちの仲間)」と「外集団(outgroup、その他の人間)」に分け、内集団に対して強い忠誠心や連帯感を持つようになります。
The Seekersでも、外部の嘲笑や否定的な報道によって「信者」対「大衆」という対立構造が強化され、信者たちの仲間意識と信仰心がむしろ強まっていたと考えられます。
また行動経済学におけるサンクコスト効果(Sunk Cost Effect)も関連すると考えられています。
これは「すでに費やした労力やお金、時間を無駄にしたくない」という心理から、状況が悪くなっても行動を変えられなくなる現象です。(この現象は、音速旅客機コンコルドの開発が典型例として紹介されるため、一般にはコンコルド効果という名で知られています)
The Seekersの信者たちも、すでに仕事や財産、家族や人間関係を犠牲にしてきたことから、「ここで信仰をやめるわけにはいかない」という心理に陥ったと考えられます。
さらに心理学の心理的リアクタンス(psychological reactance)から解釈することもできます。
これは1960年代にジャック・ブレームによって提唱されたもので、人は自分の自由や選択肢が奪われると反発するという心理的傾向を指します。
この現象は、ネット上では「カリギュラ効果」という呼び名で有名です。これは「カリギュラ」という映画が、過激な内容により公開禁止になった途端人々の関心を大きく集めてしまったという出来事からメディアが作った用語です。(カリギュラ効果は学術用語ではなく、主にコンテンツ規制に対して使われる俗称)
「心理的リアクタンス」はもっと広範な現象を扱っており、親への反抗期や、The Seekersの信者たちの行動に対しても適用されます。
この文脈では周囲から「やめろ」「間違っている」と否定されることで、信者たちはその反発から「自分たちは正しい」という確信を強めてしまったと考えられるのです。
このようにThe Seekersの事例は、当時は認知的不協和のみで説明されましたが、現在では社会的アイデンティティ理論、サンクコスト効果、リアクタンス理論など複数の理論を組み合わせることでより包括的に理解されています。
SNS社会ではカリスマ的インフルエンサーやアイドルをめぐるファンとアンチの対立にも同様の心理構造が見られます。

そう考えると、The Seekersの研究は、70年前にすでにネット社会における人間行動のパターンを先取りしていたと言えるかもしれません。
カルト教団への潜入調査という型破りな手法と、人間心理の根源に迫った先駆的研究。
フェスティンガーたちの『When Prophecy Fails(予言が外れるとき)』という研究は、人がなぜ「間違いを認めず信じ続けるのか」という普遍的な疑問への答えを提示しました。
間違いは誰にでも起きるものです。重要なことは早期にその間違いを認め改善点を見つけ出すことです。
しかし、間違いを認めない限り、その問題は永遠に解決されません。人が失敗を認めない心理を理解することは、問題解決を早める最も重要な知識となるでしょう。














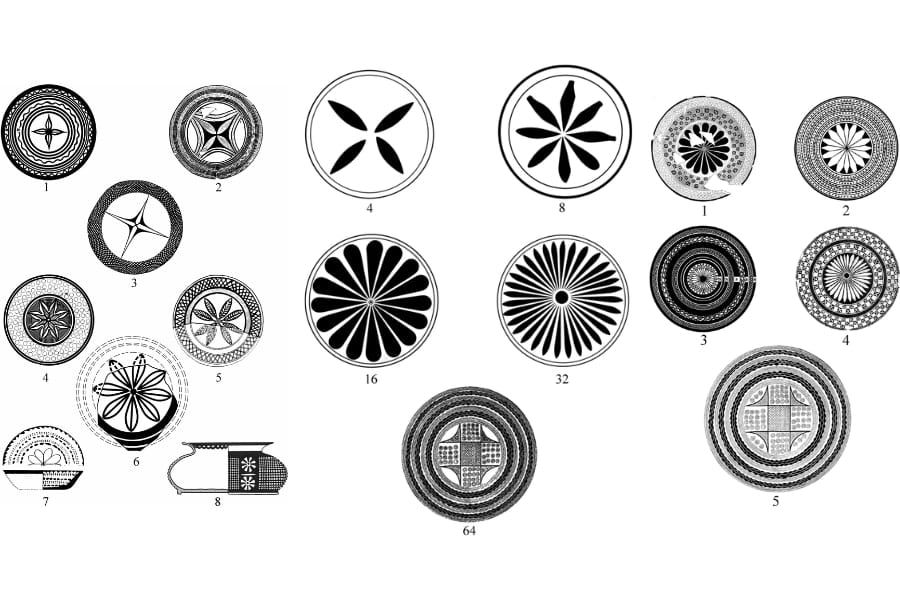

















![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)




























まるでコロナに罹っても重症化しなかったみたいな話ですね、さて真実はどっちだ
このような心理学の先駆的研究が奇蹟の年1953年に行われていたとは驚きです。「自分たちは正しい」「俺は悪くない」と頑なに正当性を信じる人々に対して,その考えは「間違っている」と否定すると逆に反発して,間違いを一層正当化する心理について,少しだけ理解できたように思います。また,権力者や専門家などの個人だけではなく,政治,司法,行政,会社,学問などの多くの制度や体系,そして生成AIですら頻繁に「間違い」を起こすのですから困ったものです。
ところで,この「間違い」を一体誰が,どのようにして確かめることができるのでしょうか?
ゲーデルの不完全性定理(ハイデンベルクの不確定性原理とよく間違えます)を持ち出すまでもなく,その体系の内部,つまり閉鎖系組織の中にいる限り,自分の間違いを認めるのは極めて困難です。なるべく,釈迦の手の平から抜け出さなければいけないと思いながら,いつも中途半端で投げ出してしまいます。本当に,その閉鎖系の中に立っていながら,そこで起きる間違いを認め,改善点を見つけ出すことは可能なのでしょうか?
なるほど。
新しい宗教に傾倒するしかないな。
普通は学識を広める事によって
色々な気付きを習得するんだろうね。
ww2の日本軍…
そして、いま、日本軍より激化先鋭してしまってるわ…
体張ってるなぁ、ポアされなくてよかった
女子大生のは当てつけっぽい気がするな
例えば気に入らない画家と下手くそな画家が居たら、下手くそな画家を褒めることで気に入らない画家を貶めてると言うか
本気でくだらない議論を褒めてるわけではなさそうに思うんだが
パターン分けの弊害と言うか、何か真面目な行動心理学者ほど、こうした心の機微を感知できてなさそうな
心を分析する上で、分類を先に作って人の行動を型にはめてしまうことで、盲点ができてないかな