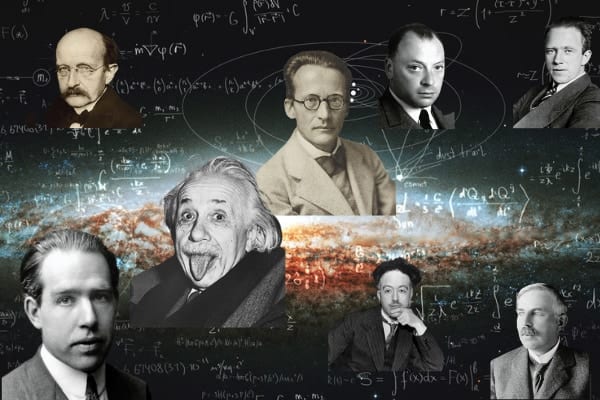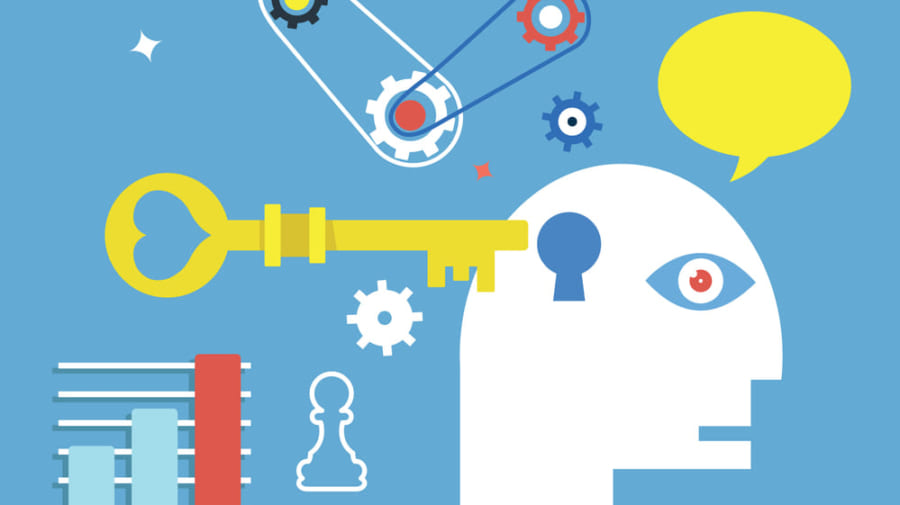時を刻む結晶がエネルギーを抱え込む

研究チームが描いたイメージは、「止まらない振り子」を二つ用意し、それらを結び付けるというものでした。
ここで言う「振り子」とは、実は量子の世界での“時間結晶”という特別な状態を持つ集団のことです。
通常、物理系はエネルギーを与えつづけてもいずれ落ち着いてしまう(安定状態に落ちる)のですが、時間結晶は外から“手拍子”のようにレーザーで常に駆動してやると、いつまでも振動(揺れ)を保ち続けるのです。
そこで研究者たちは“止まらない振り子”が二つをつなげて、振動自体を“エネルギーをしまうポケット”にできないかと考えました。
通常の電池は、「プラス極とマイナス極のあいだにある電位差」という“空間的な構造”を使ってエネルギー(電子の位置)を貯めています。
一方、時間結晶電池では、いわば「時間のなかで変化する量子的リズム」がエネルギーをためる役割を果たします。
ここは少し抽象的で難しいのですが、研究で「振動している」と表現されるものは実は量子そのものではなく量子の状態になります。
時間結晶と呼ばれる系では、見た目で“物体が物理的に揺れ動く”わけではなく量子を特徴付ける物理的性質(スピンの向きや超伝導状態などの量子状態)が周期的に変化するのです。
物理的に何かが動いていなくても、量子力学的な観測量(内部自由度)が周期的に変動し続けているわけです。
そのため時間結晶は空間的に何かをためることなく「時間的に変動する量子状態のリズムそのもの」にエネルギーが乗り続け、そこから必要に応じてエネルギーを取り出すイメージになります。
市販の化学電池のように電子が内部を動くのではなく、量子そのものにある時間的リズム変動の中にエネルギーを閉じ込めているとも言えます。
実際の調査にあたっては、理論シミュレーションを行い、二種類の充電パターンを試しました。
1つは両方の時間結晶に同時にレーザーを当てる(=両方の振り子に定期的に力を加える)場合、そしてもう1つは片方だけにレーザーを当てると、そこからもう一方へとエネルギーやリズムが“伝染”し、二つ目の振り子も後から振動を始める場合です。
するといずれのケースでも、結合された時間結晶が「止まらない振り子」として協調して動くと、静止した状態(振動なしの落ち着いた状態)よりも多くのエネルギーを蓄えられ、効率も高いことがわかったのです。
とくにおもしろいのは“感染充電”のケースで、あとから振動し始めた方が、より長く振幅(=蓄えられたエネルギー量)を保てるという結果になりました。つまり、一度振動リズムを獲得した結晶は、自分の揺れを維持しやすく、エネルギーを熱などに奪われにくくなるというのです。
「どうしてそんな都合のいいことが起きるのか?」――ここには時間結晶の不思議な特徴がかかわっています。
時間結晶の振動は、周囲のノイズにさらされてもリズムを崩しにくい(位相が乱されにくい)という性質があります。
ちょうど、トップ(コマ)が回り続けているときに重心が安定するように、振動自体が“バランスを保つ”働きをするのです。
このおかげで、エネルギーが外に逃げにくい状態をキープできます。
つまり、外から与えられるエネルギーが振動にうまく貯め込まれ、振動が止まらないかぎりそのエネルギーは「時間上の振幅」として保持される――これが“時間の中にエネルギーを蓄えている”ように見える理由です。
本研究を率いるフェデリコ・カロロ准教授は、この状態を「二つの結晶が共鳴すると、振動がエネルギーを抱え込む“量子ハンモック”になる」と表現しています。
ハンモックの揺れに身をあずけるように、二つの時間結晶が振動を続けながらエネルギーを保つ――それが量子電池の中核になり得るのです。
これは化学反応やイオン移動を利用している従来の電池とはまったく異なるメカニズムで、「時間の振動」を丸ごと蓄電に使う――この斬新な発想が「時間結晶電池」の最大の革新性です。
まだ理論段階ではありますが、「ただ二つの振り子(時間結晶)を結合してやるだけで、長くエネルギーを保てる」という結果は私たちのエネルギー利用の常識を覆す可能性があります。
実際、カロロ准教授らはこのモデルにおいて、時間結晶状態でエネルギーを供給すると量子電池としての性能が飛躍的に高まることを示しました。
カロロ准教授は「量子電池は、例えばナノスケールのデバイスにエネルギーを送り込む用途などが考えられます。古典的な電池よりも高性能を発揮する可能性を秘めています」と述べています。
今回の成果は、時間結晶という全く新しい物質相がその高性能電池の鍵となり得ることを示した点で、非常に興味深いと言えるでしょう。






























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)