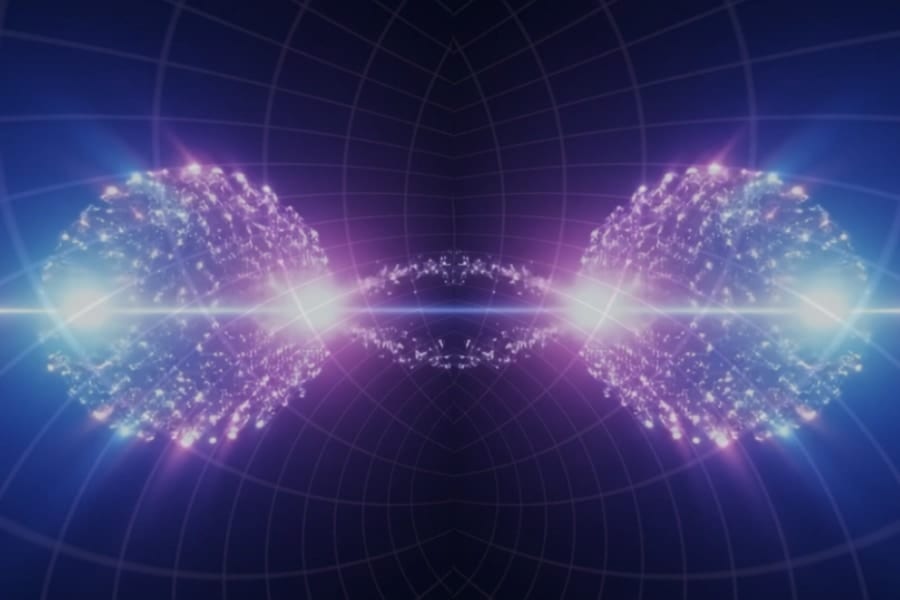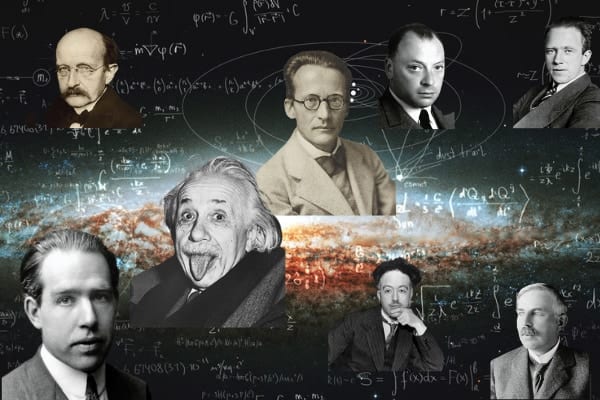量子電池の悩み“即時放電”に挑む

私たちが普段使っているスマホやリモコンなどの電池は、基本的に化学反応によって電気エネルギーを生み出しています。
電池の内部では化学物質が反応し、その結果として電子(電気の粒)が移動することで電流が流れ、エネルギーが取り出される仕組みです。
これは古くから知られている仕組みで、現代の多くの電子機器に利用されています。
一方、近年研究されている「量子電池」は、従来の電池とはまったく異なる原理で動きます。
量子電池とは、目に見えないほど小さな世界――つまり「量子」の世界に特有な不思議なルール、「量子力学」を使ってエネルギーを蓄える新しいタイプの電池です。
具体的には、原子や電子といった極小の粒子が持つ量子的な性質(たとえば、粒子が複数の場所に同時に存在するような奇妙な状態)を利用して、エネルギーを蓄えたり取り出したりします。
そのため、量子電池は従来の化学電池では達成できないほど高速でエネルギーを充電したり、大量のエネルギーを素早く引き出したりすることが可能になると考えられています。
こうした期待から、世界中で量子電池の研究が盛んになっています。
実際に理論研究では、複数の粒子を協力させることで充電速度が大幅に上がったり、従来とは比べものにならないほどの大量のエネルギーを一瞬で放出できる可能性が指摘されています。
また最近では、超伝導回路や分子を使った量子電池の小規模な実験が行われ、その基本的なアイデアが徐々に実証され始めています。
しかし、量子電池の開発には乗り越えるべき大きな課題があります。
最大の問題は「エネルギーが勝手に抜けてしまう」ことです。
量子の世界では、電池を充電してエネルギーを蓄えた後でも、そのエネルギーが充電器と電池の間を行ったり来たり振動してしまうのです。
これを専門的には「即時放電」と呼び、せっかく充電したエネルギーが安定して保てないことを意味しています。
わかりやすく例えるなら、コップに水を満タンにしても、小さな穴が開いていて水が少しずつ漏れ出てしまうようなものです。
この現象を解決しないと、量子電池は実用化が難しくなります。
そこで、研究者たちは「エネルギーが漏れない安定な充電方法」を見つけるために、さまざまな工夫をしています。
例えば、電池の内部にある原子を「ダーク状態」と呼ばれる特別な状態にすると、エネルギーが外に漏れにくくなることが知られています。
他にも、「断熱的(アディアバティック)」な操作という方法があります。
これは、ゆっくり丁寧にエネルギーを注ぎ込むことで、エネルギーが他の場所へ逃げてしまうのを防ぐ方法です。
こうした方法は理論的に提案され、一部は超伝導回路を使った量子電池の実験でもすでに実証されています。
また、超低温の原子を使った実験装置でも同様の方法が実現可能だと考えられています。
このような背景のもとで、本研究は「どうすればエネルギーを完全に充電し、それを安定して長時間保てるか」という課題に正面から挑みました。
そのために研究グループが注目したのが「極低温原子」です。
極低温原子とは、原子をほぼ絶対零度(マイナス273.15℃)という極限まで冷やした特殊な原子のことです。
原子をここまで冷やすと、普段は見えない量子の性質が強く現れ、レーザー光で原子を自由自在に動かしたり、原子同士が互いに押し合ったり引き合ったりする力(相互作用)を精密に調整することが可能になります。
このような極低温の原子を利用すれば、従来の方法よりさらに安定で高性能な量子電池が作れるかもしれない――。
研究者たちは、この可能性を実現するための新しい充電法を探究しました。




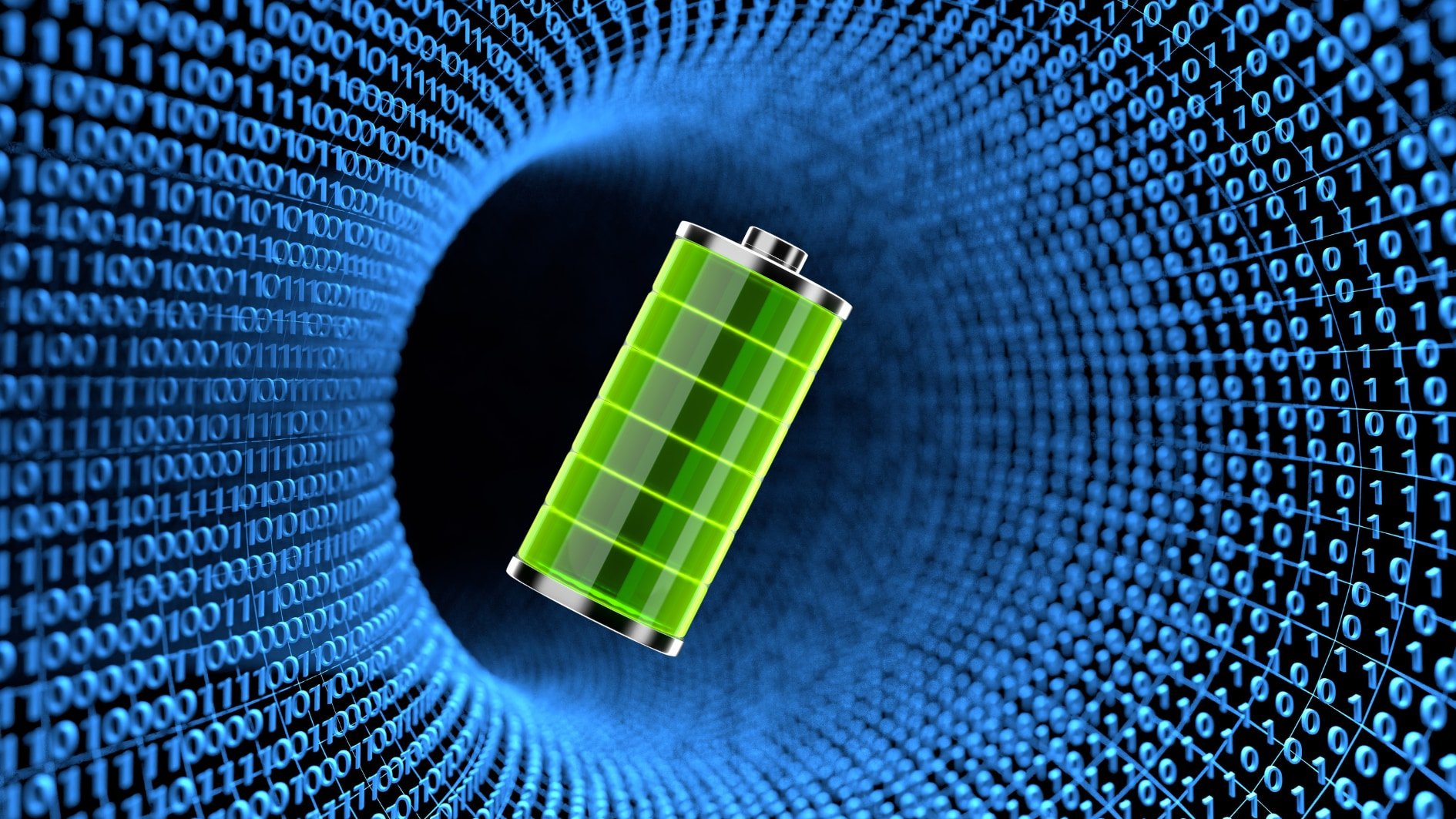











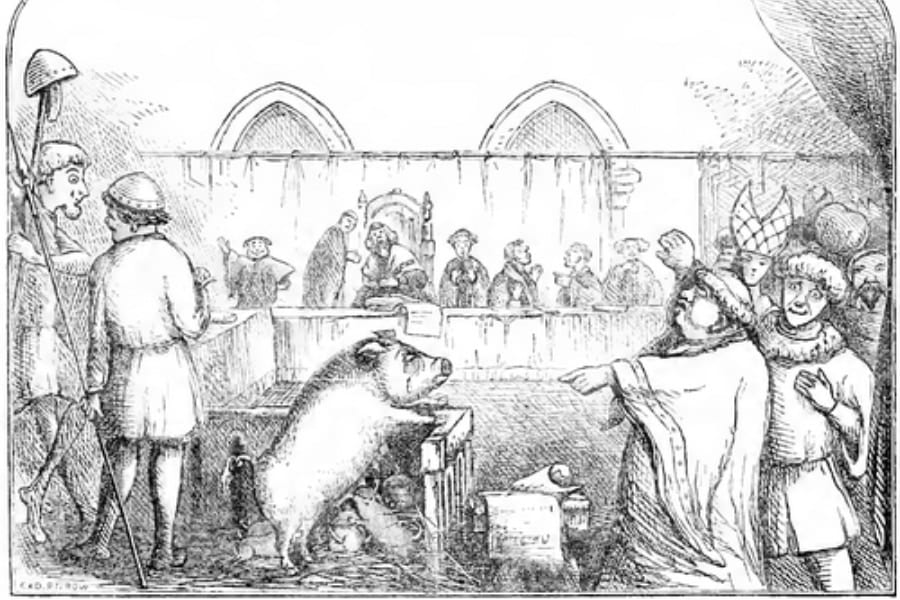













![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)
![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)