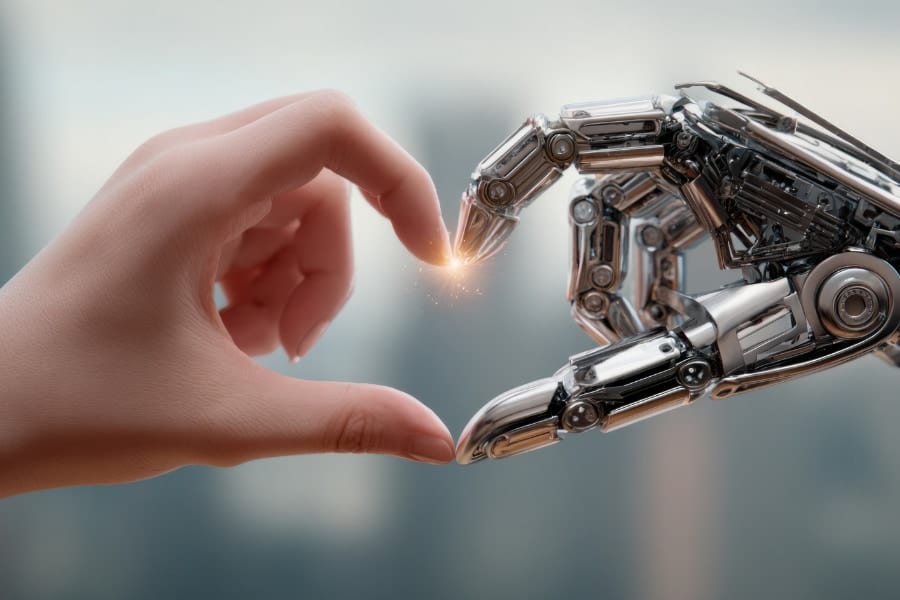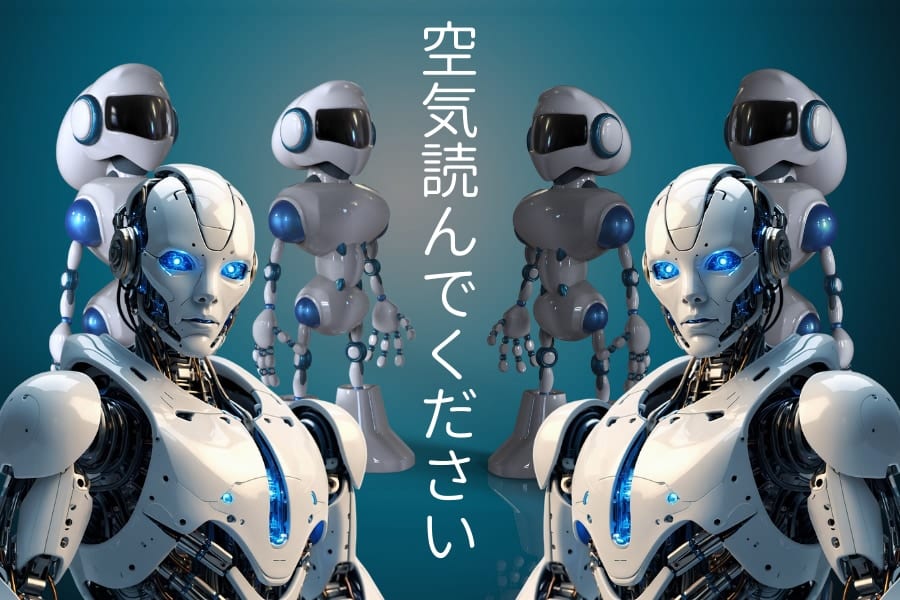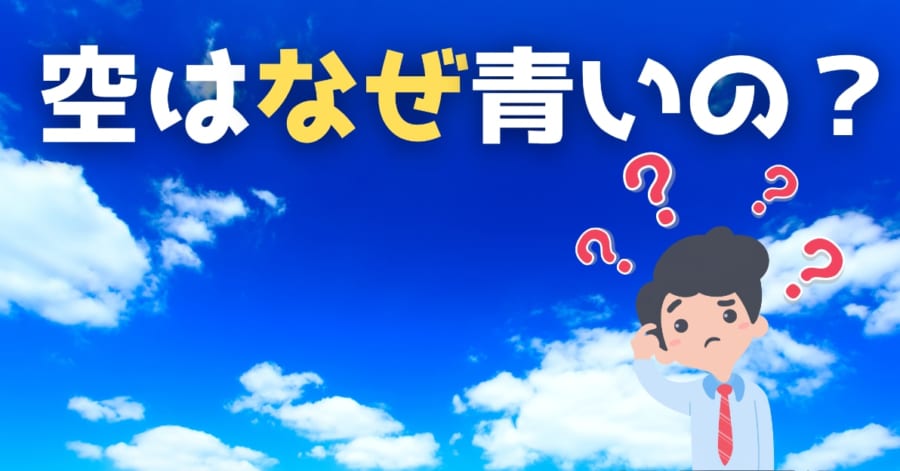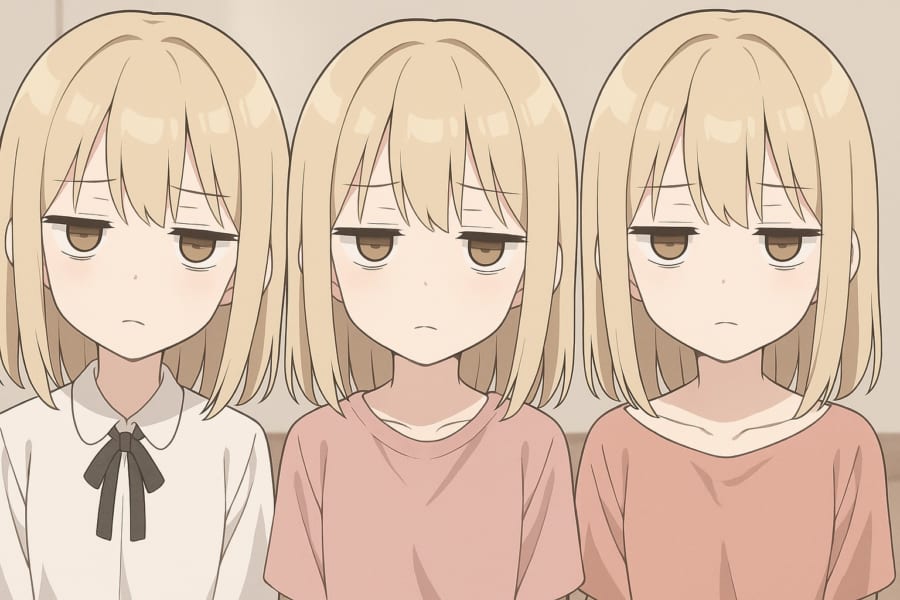あなたも知らずにAIを真似ているかもしれない

AIが人間を真似るのではなく、人間がAIを真似し始めている時代はすでに到来しているのでしょうか?
この謎を解明するため、研究チームはまず、ChatGPTが好んで使う単語を特定する実験を行いました。
ChatGPTに対して数百万ページに及ぶEメールやエッセイ、学術論文、ニュース記事などのテキストを「文章をより洗練させてください」「明瞭にしてください」といったプロンプトで編集させ、AIが頻繁に文章中に追加・使用した単語を抽出しました。
その結果、「delve(掘り下げる)」「realm(領域)」「meticulous(綿密な)」といった語彙がAIによって繰り返し挿入される傾向があることがわかりました。
研究チームは、このようなAIが特に多用する単語群を「GPTワード」と名付けました。
次に、そうしたGPTワードが人間の話す言葉にどれほど登場しているかを、大規模なデータで調べました。
具体的には、ChatGPT公開前(2022年11月以前)と公開後の期間に配信された膨大な英語音声コンテンツを分析しました。
その対象は、360,445本以上の学術系YouTube講演動画(大学などの講義・講演)と771,591本のポッドキャストエピソードに上り、合計約74万時間もの人間の談話が含まれています。
このデータを月ごとに区切り、AI登場前後でGPTワードの使用頻度の推移を比較・分析し、ChatGPT公開時点を境に単語使用傾向がどのように変化したかを詳細にモデル化しています。
また、対照実験として、ChatGPTがあまり使わない同義語(例えば“delve”の対照として“examine”や“explore”など)についても同様に頻度を追跡し、話題の変化や他の要因の影響を排除する工夫も行われました。
結果、非常にはっきりした変化が明らかになりました。
ChatGPTのリリース直後を起点に、英語の話し言葉におけるGPTワードの使用率が統計的に有意に上昇したのです。
例えば、学術講演や討論の場で「delve(掘り下げる)」「meticulous(綿密な)」「swift(迅速な)」「comprehend(理解する)」「boast(誇示する)」などの言葉が、それ以前の3年間と比べて約25〜50%も頻繁に使われるようになったと報告されています。
特に「深掘りする」や「掘り下げて考察する」という意味の“delve”という単語は、ChatGPTが文章を整える際によく付け加えるお気に入りの単語でした。
日本でも最近は「深掘りして解説する」という言葉を妙に聞くようになったという人もいるかもしれません。
研究者たちはこの“delve”などの会話での急増がAIから人への言語パターンの伝播を示す明確な証拠だと述べています。
重要なのは、こうした変化が台本のあるスピーチや番組内の決まり文句だけでなく、インタビューや対話といった即興の会話にも見られたことです。
「台本や決まり文句ならばAIが作成したものを読み上げてしまっただけなのでは?」と思う人もいるかもしれませんが、生の人間の対話にまでAIっぽさの侵食が進んでいるという結果は、着目すべきでしょう。
一方、対照として調べた同義語ではこれほどの急増は確認されず、またChatGPT公開の1年前や2年前を「変化点」に置いた分析でも同様の増加は起こらなかったため、2022年末のChatGPT登場こそが語彙トレンドを変化させた決定的要因であると研究チームは結論づけています。
以上の結果は、ChatGPTのリリース後、人間の話し言葉における単語の頻度がAI生成文章の影響を受けて変化し始めていることを示しており、同時にAIシステムが人間文化そのものを変革しつつある可能性を示しています。









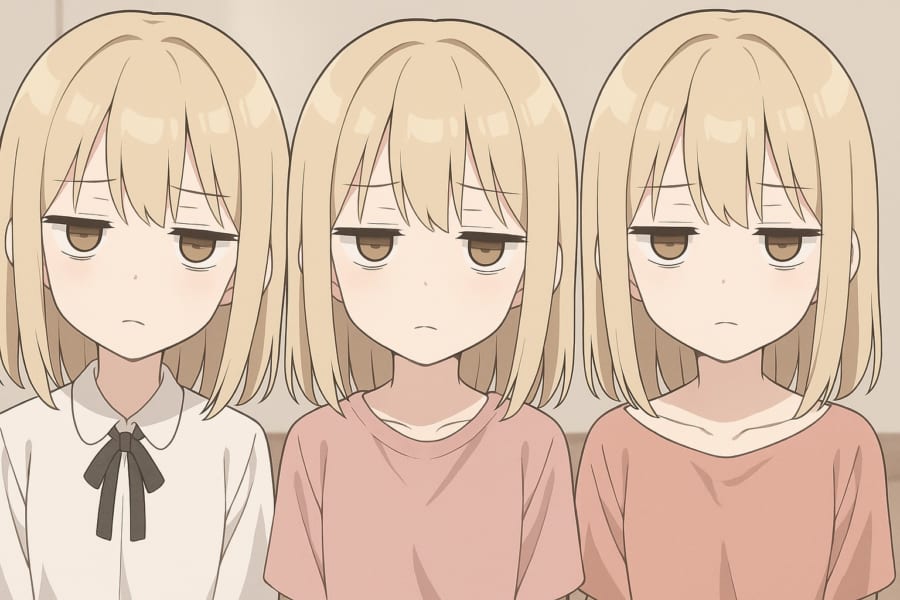





















![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)