プラスチックを“美味しい”と感じる動物――人間社会への警鐘

マイクロプラスチックに対する“味覚の学習”──この現象が生態系にもたらす影響は計り知れません。
まず、汚染餌を好むようになった動物本人(個体)にとって大きなリスクです。
本来なら栄養豊富な餌を食べるところを、プラスチックだらけのいわば「ジャンクフード」に頼る食生活に陥れば、栄養不良や発育不全を招く可能性があります。
事実、サンゴの実験では、プラスチック摂食による栄養不足や組織損傷が確認され、長期的には生存率の低下につながる恐れが示されています。
魚の場合も、プラスチック片で胃が埋まれば満腹感で餌をとらず餓死のリスクがあります。
また一部の研究では、プラスチック由来化学物質に引き寄せられる甲殻類の行動変化が観察されており、生理的または神経行動への影響が示唆されています。
こうした変化は生態系全体にも波及しかねません。
ある種が大量のプラスチックを食べて弱れば、その種を餌とする捕食者の個体数や健康にも影響が及びます。
食物連鎖のバランスが崩れれば、漁業資源などを通じた人間への影響も避けられません。
さらに、私たち人間への影響も無視できません。
マイクロプラスチックはすでに海産魚介類や食塩、飲料水などから広く検出されており、知らず知らずのうちに体内に取り込まれています。
先行研究でヒト血液中に複数のプラスチックポリマーが発見された例もあり、家畜用飼料や畜産物への拡大は現時点では明確ではないものの、将来的に無視できない懸念が残ります。
そのうえ培養細胞を使った実験ではマイクロプラスチックが細胞に損傷を与える結果もあるため、長期的には健康影響の可能性を慎重に見極めることが求められます。
幸い、本研究から明らかになった最大のポイントは、汚染エサに対する嗜好が「学習」によって形成されるということです。
これは理論上、環境からプラスチックを排除すれば嗜好をリセットできる可能性があるという、希望のある事実でもあります。
研究チームは、「プラスチック汚染の抑制を通じて元の生態系バランスを回復することが重要である」と強調しています。















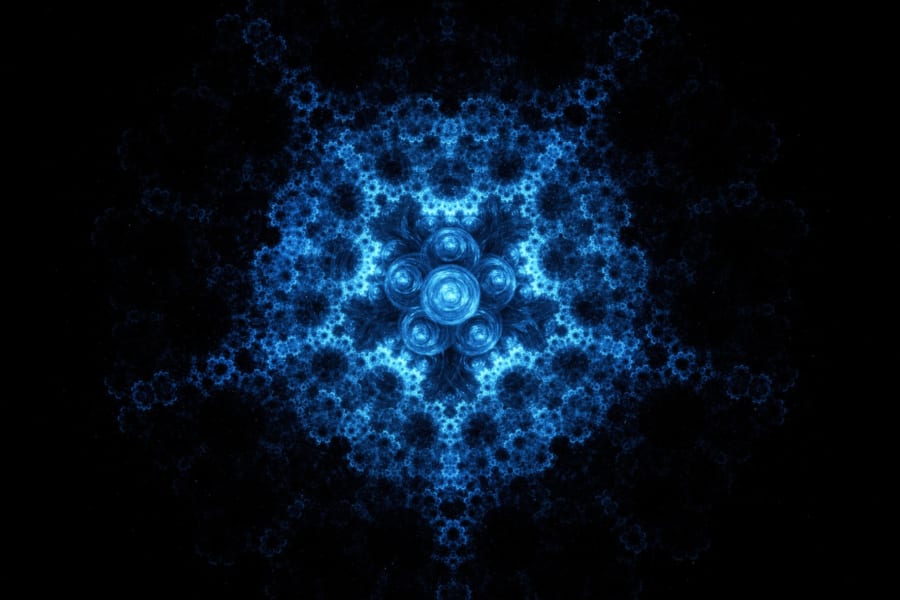














![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)




























蓼食う虫も好き好き。
すでにヒトの脳から平均7gものプラスチックが検出されるという研究もあるのに、人血液から発見された例もある、などというのは随分悠長な…
ひょっとしてマイクロプラスチックっておいしいの?
これ防虫とか殺虫にも応用できないかな。
元々美味しいと感じていたわけではなくて、美味しいと感じるようになって、やみつきになったって事なのでは
ビールを美味いと感じるようになるみたいな、くさやに慣れてやみつきになるとかなんじゃないかしら
防虫と殺虫に使うとしたら、分解されて残らない様にしないとならないし、誘引として使うとしたら、先ず嗜好を学習させないとならないでしょうね
麻酔性があるわけ?
へーマイクロプラスチックって美味いんだ
今度食べてみるわ
マイクロプラスチック?ペットボトルから摂取してますよ。
動物は人間も線虫も同じく体に悪いものを好むようになるところがこわいです。食品汚染がひどいです。プラスチック製品を使すぎです。
生体として具合が悪くなってるんだからやっぱり良くないよね…
マイクロプラスチックと一概に言うけど、何由来の何が健康問題が有って、それ以外は大丈夫とか研究せずに全てダメに持っていきたいのかな?
人造豚耳が好んで食べられる未来があるかもしれない……
シンナーやラテックスなど臭くて身体に悪いんだけどクセになるみたいな感じなのかな?生き物の不良化は深刻だなー
マイバック使いなさい
マイバッグも樹脂繊維だぜボンボン
妙な中毒性とかがあったりするかも…
ジャンクフード好きな人間と似たようなもんかもな
これで消化できるように進化すれば万事解決だな
最終的に人間がため込んでから燃やされるのでマイクロプラスチックは人間がいる限り少しずつ地球からなくなっていくはずです
では、マイクロプラスチックが人体にどのような悪影響があるのか?という情報は知られていないように思います。内分泌、免疫系への影響、発がん性など、、そのような研究結果も興味深いものがあれば、是非お願いします。
これって長い目で見ると、マイクロプラスチックを消化出来るような酵素なりを身に着ける事になるのでは‥?
線虫とかは世代交代が早い分進化も早い訳で。