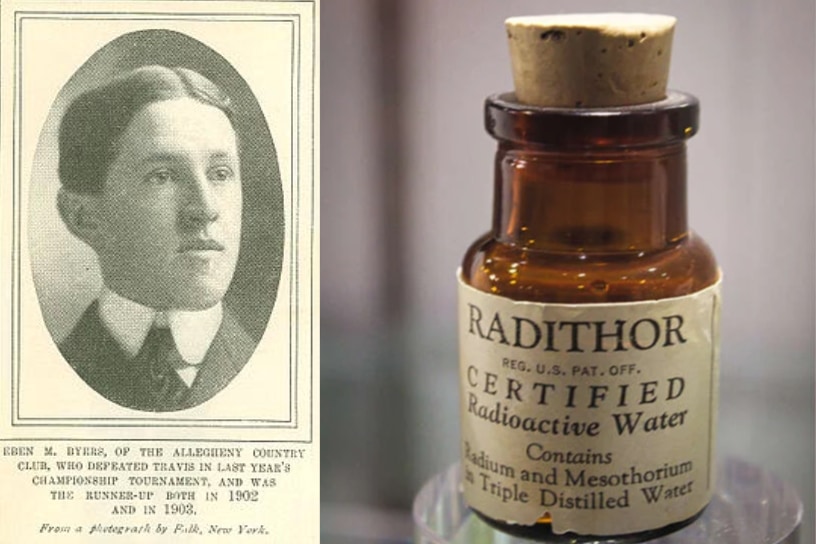「反すう」と「心配」の連鎖が「不安・抑うつ」を深める
さらにチームは、マインドワンダリングが直接的に心の病を引き起こすわけではなく、ある“思考の癖”を通じて悪影響を及ぼすことを突き止めました。
その思考の癖とは、「反すう(Rumination)」と「心配(Worry)」です。
反すうとは過去の後悔を何度も思い返してしまう傾向で、心配とはまだ起きていない未来の出来事に対して過剰に備えようとする考え方です。
どちらも自己否定的な思考に陥りやすく、不安や抑うつと深く関係しています。

チームは「マインドワンダリング → 反すうや心配 → 不安や抑うつ」という因果の連鎖モデルを構築し、解析を行いました。
その結果、非意図的なマインドワンダリングが「反すう」や「心配」の頻度を高め、最終的に不安や抑うつの強まりにつながるという構造が見えてきたのです。
とりわけ、未来に対するネガティブな考えが「心配」を増やし、そこから不安症状へと発展するルートが強く確認されました。
一方で、過去の後悔を繰り返す「反すう」は、直接的に不安や抑うつを引き起こす力が弱いこともわかりました。
興味深いのは、意図的なマインドワンダリングについては、これらの悪影響が見られなかったどころか、むしろ「心配」を減らす方向に働く可能性が示された点です。
つまり、自分の意志で未来を具体的に想像したり、ポジティブな思考に意識的に向けたりすることは、むしろ心の健康にプラスに働く可能性があるということです。
意図せぬ「ぼんやり思考」があなた自身を責めていた
今回の研究は、日常のなにげない「ぼんやりとした思考」が、気づかぬうちに私たち自身を追い詰めるメカニズムを明らかにしました。
それは単に集中力が途切れていたのではなく、自己否定のきっかけとなる心の自動運転だったのです。
もしあなたが最近、理由もなく不安や落ち込みを感じているなら、その背後には「ネガティブで未来的で曖昧な考えごと」が潜んでいるかもしれません。
そんなときは、自分がどんな思考にとらわれていたのかに気づき、「これは反すうかも」「これは心配しすぎかも」とラベルを貼って手放すことが大切です。
そして、意図的にポジティブな未来を思い描く時間を持つことも、自己否定のループを断ち切る第一歩になるのです。




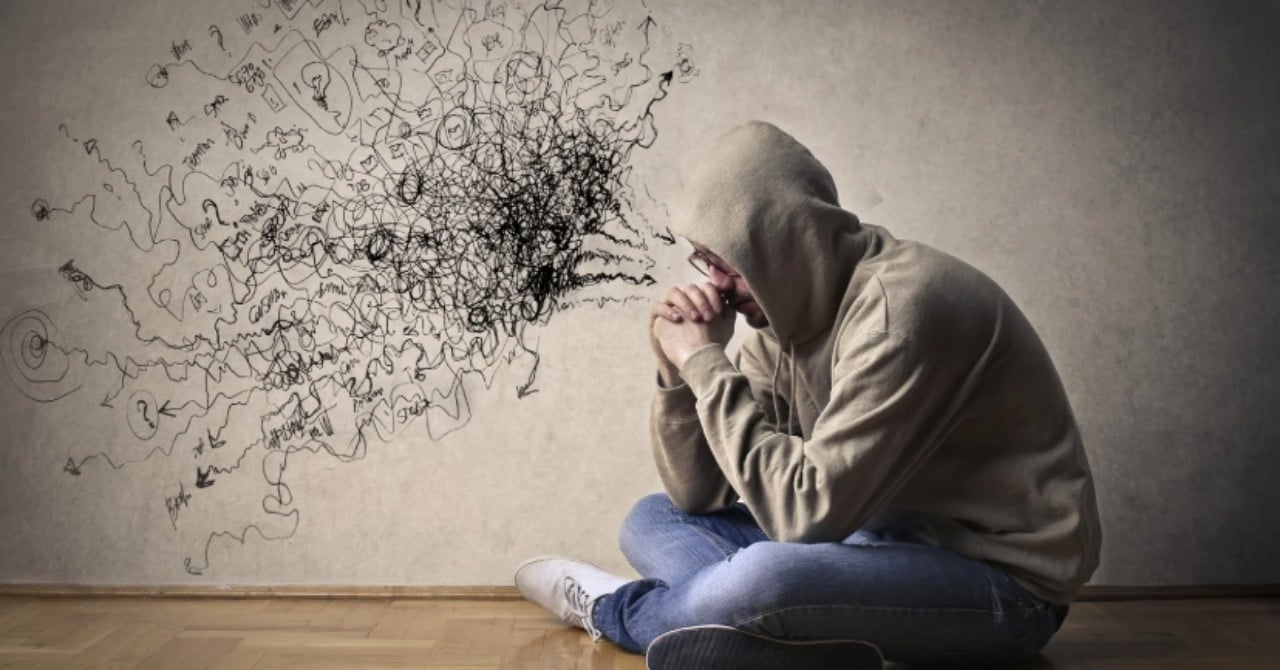























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)