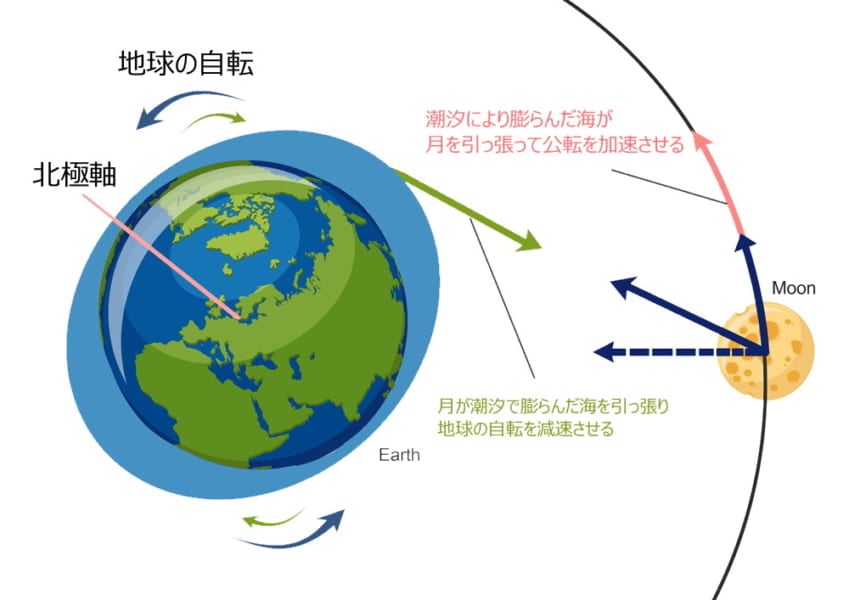老化は本当に「ゆっくり進む」ものなのか?

これまで老化といえば、少しずつ、年を重ねるにつれてじわじわ進んでいくものと考えられてきました。肌のしわが増えたり、白髪が目立ったり、回復力が落ちたりと、変化はあるけれど、いつどこから老いが本格的に始まるのかを、医学的に明確に捉えるのは難しいとされてきました。
一方、近年の研究では、老化の進み方が実は一様ではなく、ある年齢を境に“加速する”可能性があるという見方が注目されています。つまり、老化は「緩やかな坂道」ではなく、「あるところで傾斜が急になる坂」のような性質を持っている、ということです。
この「転換点(inflection point)」の存在を裏付ける研究は、実はこれまでもいくつか報告されてきました。
たとえば、アメリカのスタンフォード大学が行った大規模な調査では、約4000人の血液を解析したところ、34歳、60歳、78歳のタイミングで体内のタンパク質が大きく変化することがわかりました。また、別の研究では、44歳ごろと60歳ごろに代謝や免疫に関わる物質が大きく変わるとされており、老化にはいくつかの“加速ポイント”があると考えられています。
ただし、こうした研究で使われたのは、血液や腸内環境など、体の外側から取り出せるサンプルでした。つまり、どの臓器がどう変化しているのかを直接見ているわけではなく、全身の状態を間接的に推測する方法だったのです。
それに対して、今回の研究では、実際に亡くなった人の献体から13種類の臓器と血漿を採取し、それぞれの中に含まれるタンパク質の変化を直接測定しています。筋肉や肝臓、大動脈、腎臓、肺など、体の内部にある主要な臓器を個別に解析することで、どの臓器が、どのタイミングで、どのように老化していくのかを詳細に比較することが可能になったのです。
タンパク質は、筋肉や臓器を構成する材料であり、酵素やホルモンとしての働きも持つ、生命活動の主役のひとつです。体内の状態が変わると、作られるタンパク質の種類や量にも変化が生じます。
そのため、ある臓器の中でどのタンパク質がどのように変わっていくのかを詳しく調べれば、老化の進み具合を客観的に知る手がかりになります。
研究チームが献体それぞれの組織から抽出したタンパク質は、合計で約17,000種類にも及びました。
この情報をもとに、年齢ごとのタンパク質の変化を解析することで、臓器ごとの「老化の地図」を描き出すことを試みたのです。
さらに研究では、臓器ごとに年齢とともに増減する特定のタンパク質を抽出し、それを「老化関連タンパク質(senescence-associated proteins)」として定義しました。
そしてこれをもとにして、各臓器が“どれくらい年を取っているか”を推定する「プロテオミック年齢時計(proteomic aging clock)」を構築しました。これは、私たちの臓器が年齢とともにどのようなペースで変化していくのかを、可視化する新しいアプローチです。
つまり今回の研究は、体の表面では見えにくい老化のサインを、タンパク質という“内なる声”から探り出そうとしたのです。
その結果、ある驚くべきパターンが見えてきました。




























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)


![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)