デジタル販売化と消費者心理のズレがもたらす「価格への違和感」
ゲーム価格が上昇していく中、消費者側の心理も大きく変化してきました。
近年、ゲーム販売はデジタル中心へと移行しつつあります。
プレイヤーはダウンロード購入を前提とし、パッケージを手に取ることは少なくなりました。
このデジタル化により、ユーザーの間で「ゲームはもっと安く買えるものだ」という意識が広がりつつあります。
Epic GamesやBlizzard EntertAInmentに勤務経験のあるゲームプロデューサー、Ryan Maloney氏は、「オンラインでのセール文化が浸透した結果、消費者はフルプライス(定価)に対して敏感になっている」と指摘します。
かつては60ドルでも納得されていた価格が、今では「高すぎる」と感じられてしまうのです。
しかも、デジタル販売ではパッケージ・流通・小売などのコストが削減されているため、「だったら安くなるべきでは?」という疑問や不満が噴出するのも無理はありません。
しかし、現実にはその浮いたコスト分は、増大する開発費や広告費の補填、あるいは株主利益に還元される形で吸収されています。
つまり、プレイヤーの期待と企業の論理に深いギャップがあるのです。
そしてそのギャップを埋める術を見つけられないまま、業界は高価格化と不信感の連鎖へと突入しています。
この構造は、ゲーム業界に限らず、映画、音楽、書籍といった他のメディア業界でも共通しています。
しかし特にゲームの場合は開発サイクルが長く、投資額が大きいため、価格改定の影響が極めて直接的に表れるのです。
では、解決策はあるのでしょうか?
専門家の一部は、インディーゲームや中小規模の制作スタジオによる「ミドルタイトル」への回帰が鍵になると語っています。
小規模でもクオリティの高い作品が成功する例(『Stardew Valley』『Balatro』など)は増えており、多様性と柔軟性のあるゲーム市場の構築が、今後の価格安定につながる可能性もあるのです。
De Schutter教授は、次のように述べています。
「ゲーム業界は“すべてが超リアルなグラフィックである必要はない”という姿勢に立ち返り、『このグラフィックで十分』と納得することが必要になってくるでしょう」
これからのゲーム業界には、グラフィックの精密さだけではなく、「体験としての満足度」や「制作の持続可能性」に対する新たな価値基準が求められているのかもしれません。




























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)
![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)




















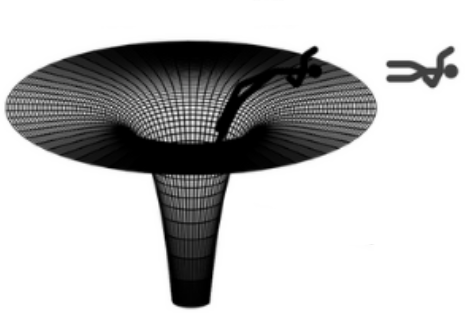
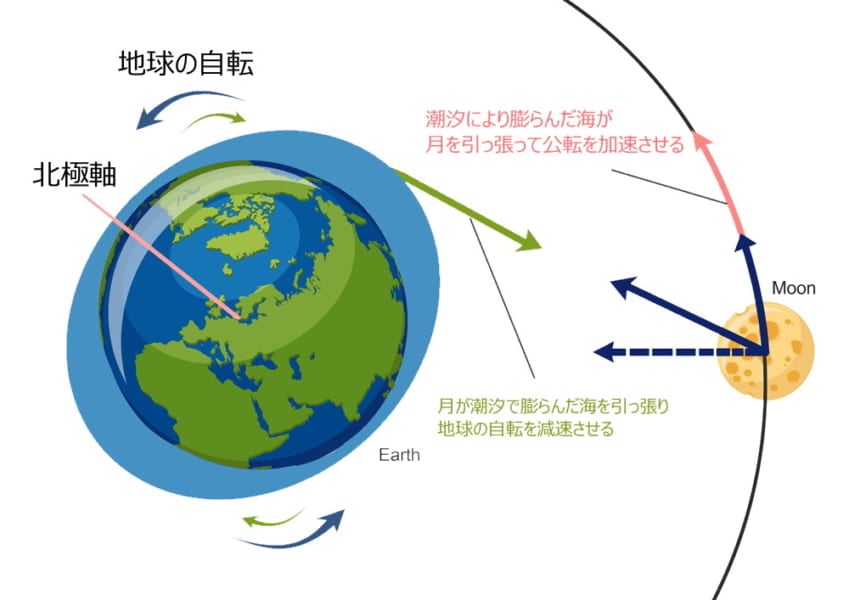






高いゲームの最大の問題点は値段にふさわしいクオリティを持ってないことですね。
あのお値段って9割以上がグラフィックなわけですが、ユーザーのほぼ全員がその違いには気がついてませんし、そこに金払う気もないはずです。
ユーザーはグラフィックではなくてゲーム内容に金を払いたいので、そっちにお金を使わないと高い高い言われ続けることになります。
肌の質感がすごいとか、服の表現が本物みたいとか、そういうのはあまり求められてないのです。
NPCとの会話に生成AIを組み込んでリアルな会話ができるようになるMODとかありますけど、ユーザーが求めてる進化ってそっちなんですよね。
求められてないところにお金使って、「コストかかったので値段上げます」言われてもそりゃ納得はしないのですよ。
同感です。40年前のグラフィックと音楽でも声優がいなくても夢中になって遊べました。五感を満たしたいのではなく刺激や創造力や主体性を満たしたいのです。幼児は石ころ一つで遊べるし、小学生ならボール一つで遊べます。それが年を取るにつれビリヤードやゴルフになるとルールが複雑化したり待ち時間が増えて主体性が奪われて行くと共に楽しさは減っていきます。ゲームが大人向けになってしまっているのです。
SFC時代からゲームは1万円超えてた気がするよ
ボリュームも増えてるし、今のゲームが高いとは思わないなあ。
普通に数千時間遊んたりするし、時間単価で1円切ることすらざらよ。