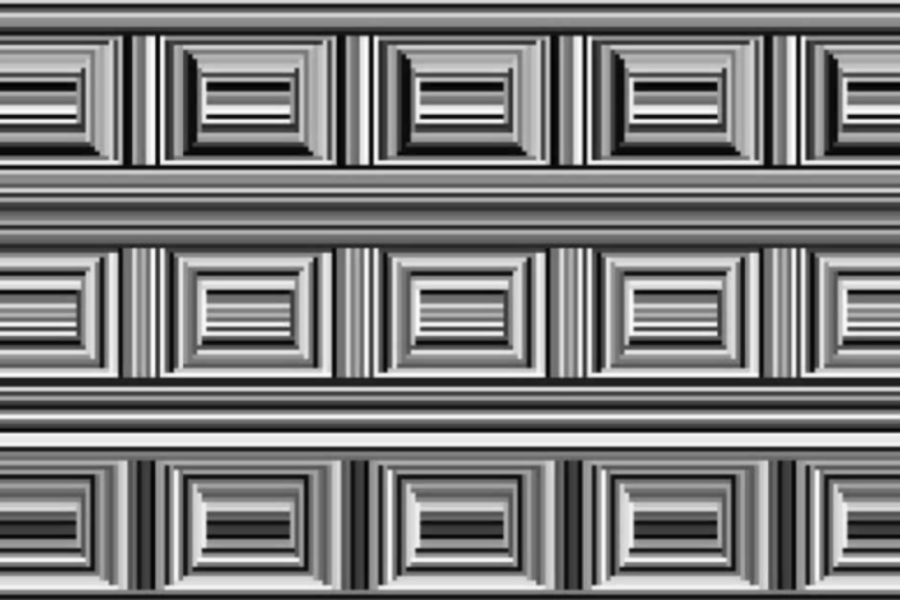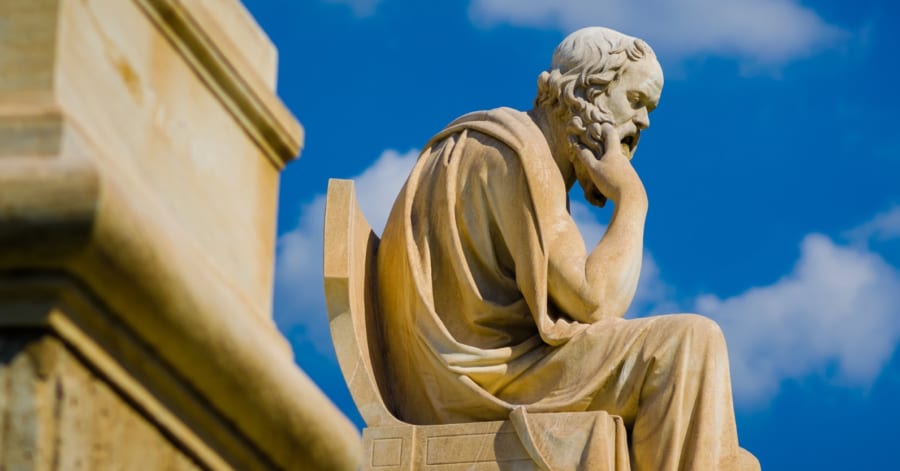哲学は人を賢くする?大規模データで検証
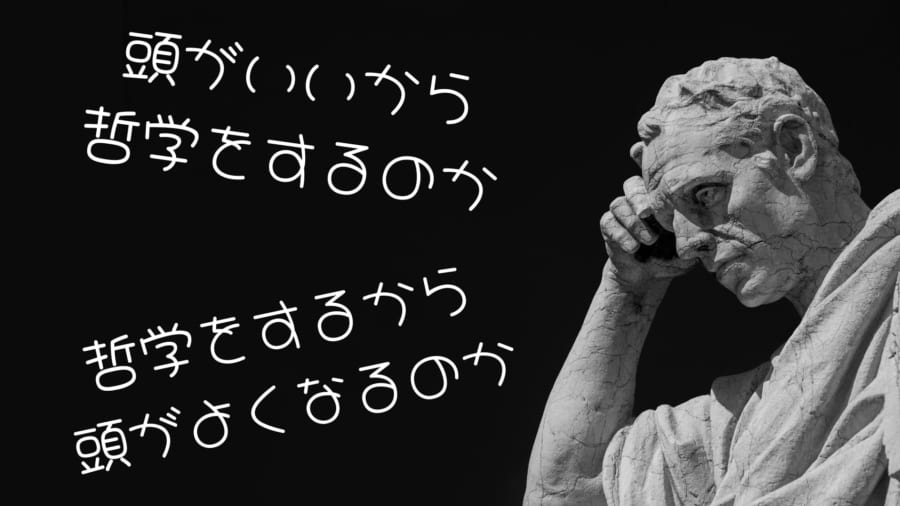
今回の研究チームは、「哲学を学ぶと本当に頭が良くなるのか?」という問いを、できるだけ公平に調べようとしました。
しかし「哲学を学ぶことで頭が良くなるのか」を確かめるのは、簡単ではありません。
なぜかというと、哲学を選ぶ学生はそもそも優秀な人が多いからです。
最初から頭の良い人が哲学を選び、そのため哲学科の成績が高くなっている可能性もあるのです。
これを「自己選抜」と呼びますが、この影響を取り除かなければ、本当に哲学の学習が力を伸ばしたかどうかは判断できません。
そこで研究者たちは、アメリカ全土にある800を超える大学から集まった約60万人もの学生のデータを使って、この問題に挑むことにしました。
まず、大学入学時に学生たちが受けるSATという試験の結果を見て、それを元に学生たちがもともと持っていた能力の差を推測します。
SATとは、高校生が大学に進学する際に受ける標準的な学力試験で、主に「言葉の能力」と「数学の能力」を測るものです。
このSATの点数を参考にすれば、「最初の時点でどれくらい優秀だったか」を大まかに把握できます。
その上で、大学卒業前に受ける2種類の別の試験の結果と比較することで、「入学後にどれだけ能力が伸びたのか」を調べることにしました。
1つ目はGREという大学院入試のテスト、2つ目はLSATという法科大学院の入試テストです。
GREは大学院に入るための試験で、「言葉を使う力」と「数学を解く力」を試すものです。
LSATは法科大学院への入学試験で、特に「論理的な思考力」と「文章を正しく理解する能力」を測る試験です。
つまり、この調査で研究者がやったことは、「入学時の能力が同じだったとして、卒業するとき哲学科の学生のほうがテストで高い点数を取っていたかどうか」を統計的な方法で調べる、ということです。
最初のスタート地点をそろえることで、哲学を学ぶという行為自体が学生の能力を伸ばしたのかどうかを、より正確に判断できるわけです。
ただし、SATでは完全には論理的な思考力を測れないという限界があるため、結果を見る際には注意が必要になります。
さらに研究チームは、テストだけでなく学生の「考える習慣や姿勢」にも注目しました。
大学1年生の時と4年生の卒業間近の時に、学生自身にアンケートを行い、「どれくらい自分から進んで新しい知識を求めるようになったか」「意見が違う人の考え方を理解しようとするか」といった姿勢を自己評価してもらったのです。
これらは専門的に「Habits of Mind(探究心や批判的に考える習慣など)」と「Pluralistic Orientation(異なる考え方を柔軟に受け入れる姿勢)」と呼ばれています。
そして、こうして丁寧に集められ分析されたデータから、興味深い結果が浮かび上がりました。
まず最初に、哲学を専攻した学生は、言葉の力(GREの言語部門)と論理的な思考力(LSAT)に関して、卒業時の成績が他の専攻よりもはっきりと高くなっていたのです。
具体的には、GREというテストの「言語推論」の部門では、哲学科の学生の平均点が他専攻より33点も高く、LSATでも2点ほど高くなっていました。
こうした差は統計的にも明らかで、偶然とは考えにくい、信頼できる差であることが確認されています。
ただし、同じGREでも数学部門の結果には、哲学専攻と他の専攻の間にほとんど差がありませんでした。
つまり哲学は、数学の力を伸ばすことにはあまり貢献しなかったということになります。
またアンケートの結果では、哲学を専攻した学生は卒業までの間に、他専攻の学生と比べて「探究心」や「批判的な考え方」、「異なる意見を受け入れる柔軟性」などがはっきりと高まっていました。
この向上は入学時の能力差を調整した後でもはっきり確認され、伸びの幅は小さめでしたが確かな効果が見られました。
特に「Habits of Mind(良い思考習慣)」では哲学科が全ての専攻の中でトップ、「Pluralistic Orientation(多様な視点を受け入れる態度)」でも6位と上位を占めました。
さらに研究者たちは、「哲学科は特に優秀な学生だけが卒業前のテストを受けるから高いのでは?」という別の疑問も調べました。
結果として、そうした偏りが哲学科にだけ特別にあるという証拠は見つかりませんでした。
つまり、この研究は、「もともと頭がいい人が哲学を選んだため」だけでは説明できない、哲学そのものの効果をしっかりと示したと言えるのです。
以上の調査結果から、哲学を大学でしっかり学ぶことは、特に「言葉を扱う力」や「論理的に考える力」、そして「探究心や柔軟な考え方」といった知的な能力や習慣を着実に伸ばすのに役立つ、ということがわかったのです。




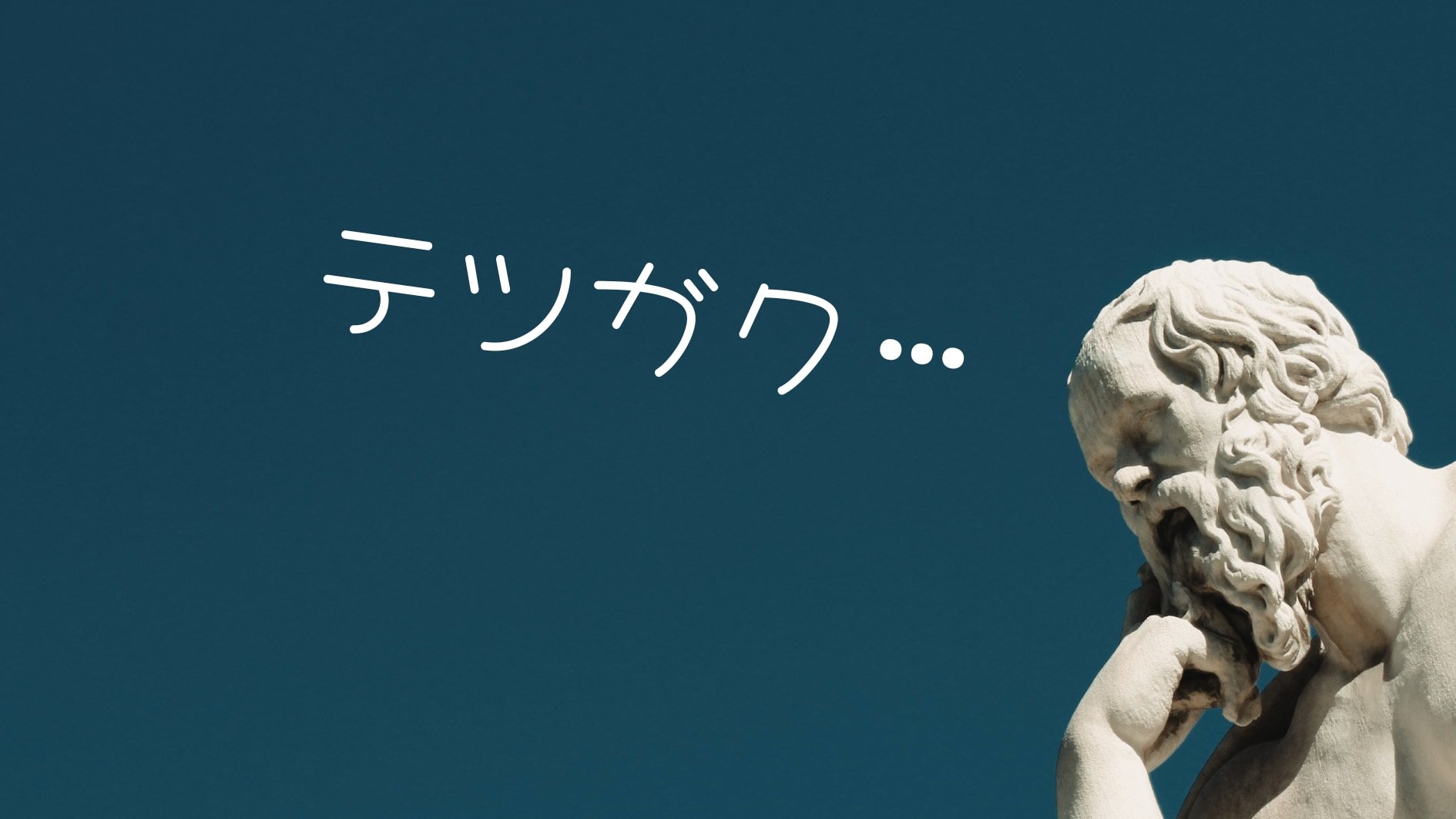























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)
![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)