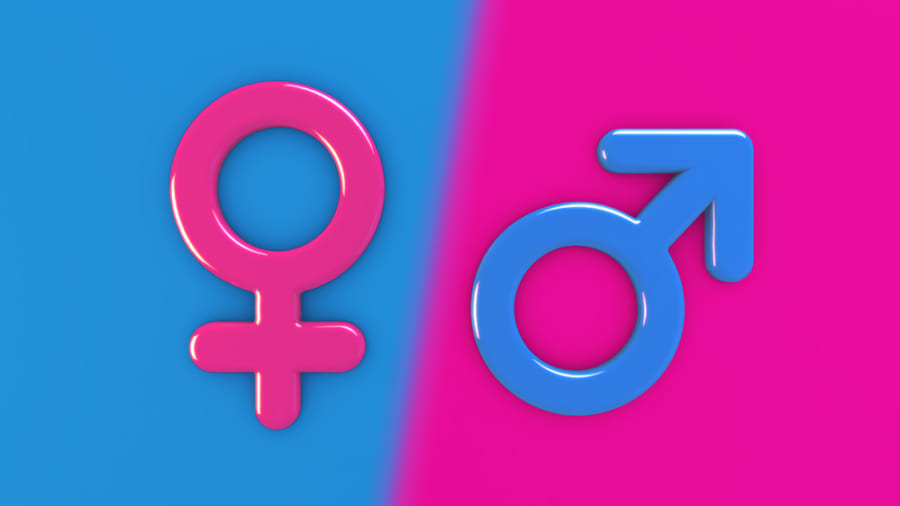二足歩行を可能にした骨盤を変える遺伝子を特定

なぜ私たちヒトは、まっすぐ立って歩いたり走ったりできる特別な骨盤を手に入れられたのでしょうか?
実は、この謎を解く鍵は、私たちがまだ生まれる前、母親のお腹の中にいる「胎児」の時期の骨盤の作られ方にありました。
胎児が成長する段階では、骨は最初から硬いわけではなく、軟骨という柔らかくて弾力のある組織からできています。
成長とともに、その軟骨が少しずつ硬い骨へと変わっていくのです。
この軟骨が骨へと変わる場所は「成長プレート」と呼ばれますが、これはちょうど植物が伸びるときの「成長点」に似ています。
この成長プレートが骨の成長方向を決め、骨の長さや幅をコントロールしているのです。
他の類人猿や多くの哺乳類の骨盤では、この成長プレートが縦方向(上下方向)に伸びることで、縦に細長い腸骨が作られていきます。
ところが、研究チームの観察によってヒトの胎児では全く違うことが起きていることがわかりました。
ヒトの胎児では、およそ妊娠53日目ごろまでは類人猿と同じように縦方向へ成長が進みますが、この時期を境に成長の向きが徐々に変化し始めるのです。
そして72日目ごろになると、成長プレートの向きがはっきりと「横方向」になり、横向きに骨が広がっていきます。
この変化はとても劇的で、研究を率いたカペリーニ教授自身も驚きました。
教授は「まさかこんな劇的に変わるとは思っていなかった。最初は徐々に短くなると思っていたが、実際にはまるで『90度ひっくり返った』ように短く幅広の腸骨が形成されていた」と語っています。
こうしてヒトの腸骨は「縦に細長い板」ではなく、横方向に広くて短い「ショート&ワイド型」に生まれ変わります。
これは、まさに二足歩行に適した安定した土台を作るための進化的な工夫だったのです。
しかし、この進化の工夫はこれだけにとどまりません。
実はもう一つ、他の動物とは大きく異なる特別な工夫がヒトの骨盤に施されていました。
それが、骨が実際に硬くなり始めるタイミングと場所の劇的な変化です。
一般的に、哺乳類の骨はまず骨の中央付近(骨幹部)から骨化(硬く変化すること)が始まります。
しかし、ヒトの骨盤では骨化が始まる場所が大きくずれ、後ろ側の縁(仙骨付近)から硬くなり始め、そこから外側へ放射状に骨化が進んでいくという、非常に特殊なパターンが発見されたのです。
しかも、さらに驚くべきことは、骨の内側部分がすぐには硬くならず、外側だけが先に硬くなるという不思議な現象でした。
内側の骨化が外側よりも約16週間も遅れて始まることで、骨盤の内部には長期間、軟骨が残る仕組みになっていたのです。
これはまるで、固まる前の粘土の周りだけを先に乾かして中を柔らかく保つことで、形を崩さずに大きく成長させる技術のようです。
この巧みな戦略のおかげで、骨盤は周囲にある筋肉や靭帯を安定してつなぎ止めながら、柔軟性を維持しつつ、内部をゆっくりと確実に固めていくことが可能になりました。
あえて例えるなら、自転車のギアを切り替えて坂道を登るように、骨盤が成長するスピードとタイミングを細かくコントロールする「二段変速ギア」を進化の途中で組み込んだようなものなのです。
このヒト特有の骨盤の作り方の秘密を明らかにするために、研究チームはとても綿密で粘り強い方法で調査を行いました。
まずヒトだけでなく、チンパンジーやテナガザルなど約20種類もの霊長類の胎児標本を、世界中の博物館から合計128点も集めました(標本の数はプレスリリースに基づく情報です)。
その中には、なんと100年以上も前にホルマリンに浸けられて保存されていた珍しい標本まで含まれていました。
こうして集められた貴重な標本を使い、「マイクロCTスキャン」という最新の立体撮影技術を使って、胎児の骨盤がどのように形作られていくのかを詳細に観察しました。
さらに、顕微鏡を使って胎児の骨盤を薄くスライスした標本を丹念に調べ、骨の成長がどのように進んでいるかを細かく比較したのです。
このようにして、通常は見ることが難しい胎児の成長過程を、生物学の「タイムマシン」を使ったかのようにじっくりと観察することができました。
しかし研究チームの探求心はこれで終わりません。
次に彼らは、最新の遺伝子解析技術を駆使して、「骨盤の作り方を決めている遺伝子スイッチ」の働きを詳しく調べました。
遺伝子スイッチとは、私たちの体の中で遺伝子の働きをオン・オフするスイッチのような仕組みで、これによって体の部品が作られるタイミングや場所がコントロールされています。
研究の結果、この遺伝子スイッチに相当する「調節DNA領域」が、ヒトでは他の霊長類よりも非常に多く変化していることがわかったのです。
この調節DNA領域の中には、特にヒトで急激に進化した「ヒト加速進化領域(HAR)」と呼ばれる特別な領域も含まれていました。
これらの領域は、他の動物ではほとんど変化していないのに、ヒトだけが特別に速く変化してきた不思議なDNA領域なのです。
さらに、成長プレートの向きを縦方向から横方向に切り替えるときには、「SOX9」「PTH1R」「ZNF521」という名前の3つの遺伝子が重要な役割を果たしていることが明らかになりました。
特に「PTH1R」という遺伝子については、人間の胎児と比較してその機能を詳しく調べるために、マウスを使った遺伝子操作実験が実施されています。
研究チームは、「PTH1R」の遺伝子にヒトの病気に関連する特定の変異を加えた遺伝子改変マウスを作成し、そのマウスの骨盤がどのように成長するかを調べました。
その結果、「PTH1R」遺伝子を変異させると、マウスでも腸骨の成長がうまくいかず、正常な骨盤より短くなったり、早すぎる骨の成熟が起きることが確認されています。
この結果から、「PTH1R」という遺伝子は、骨盤を正常な形や大きさに育てるため重要な役割を担っていることが分かります。
また、骨化のタイミングを遅らせて、骨盤を外側からじっくりと広げる働きを制御しているのは「RUNX2」「FOXP1」「FOXP2」という遺伝子であることもわかりました。
これらの遺伝子群は「遺伝子スイッチ」のように働いていて、特定のタイミングで発動し、骨の成長方向を変えたり、骨が硬くなるタイミングを調整したりしていました。
自然は、この遺伝子スイッチを細かく調整することで、私たちヒトに他の霊長類にはない全く新しい形の骨盤を作り出すことに成功したのです。
このようにして今回の研究は、「ヒトが二足歩行という特殊な能力を獲得するために、自然がどのように遺伝子のスイッチを操作してきたのか」を非常に鮮明に示してくれました。
単に骨の形だけが変わったのではなく、骨の「作り方」そのものが変わっていたという驚きの事実が、私たちの目の前にはっきりと提示されたのです。
人類の進化の歴史において、このように発生のプロセス自体が劇的に変化することは極めて珍しい出来事であり、それだけ重要で意義深い発見と言えるでしょう。
私たちがなぜ二本足で立ち、自由に歩き回れるのかという根本的な謎が、この研究によってついに解明への扉を開けたのです。




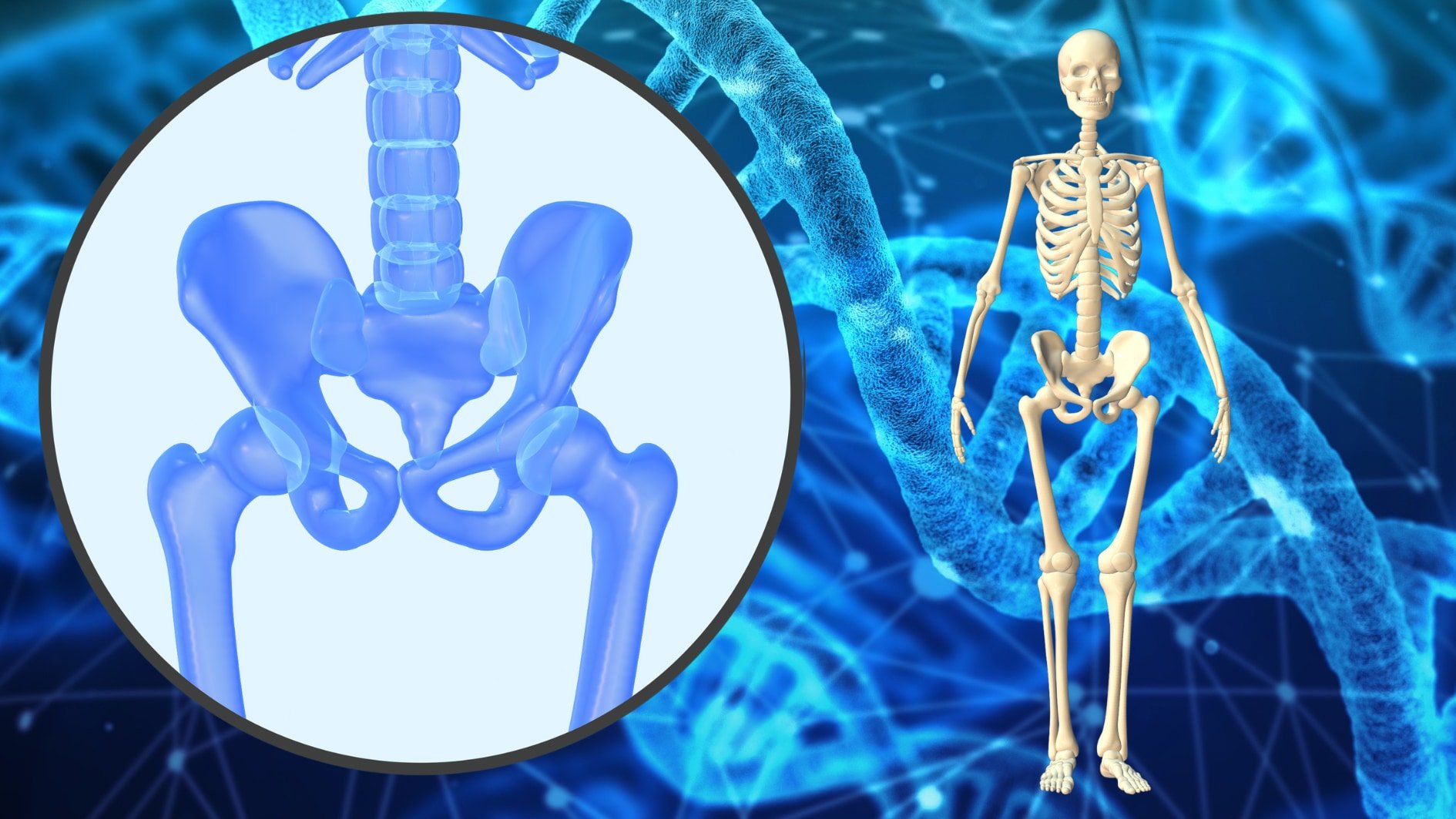























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)