種の運命を左右する遺伝子の『抜け道』

どんな条件が揃ったら新しい『種』として枝分かれするのか?
新たな研究ではその決め手になるのが「遺伝の仕組みがどのくらい素早く整うか」が重要であることを示しています。
では、「遺伝の仕組みが整う」とは一体どういうことでしょうか?
少しずつ順を追って説明しましょう。
生き物は、それぞれの環境で生き残るために色々な特徴を持っています。
たとえば、ある場所では大きなクチバシが有利で、別の場所では小さなクチバシが有利、ということがありえます。
このように異なる特徴を持つ個体が同じ種の中にいる場合、通常はその中間的な特徴をもつ雑種も生まれます。
しかし、環境がはっきり二分されていて、中間の特徴が不利な場合、その雑種はうまく生きられません。
こうした状況で重要になるのが、雑種が生まれにくくなるような「遺伝子の工夫」なのです。
一つのわかりやすい例が、シロオビアゲハというチョウの仲間です。
シロオビアゲハのメスには、毒を持つ別種に似せた模様(擬態型)の個体と、目立たない普通の模様(通常型)の個体がいます。
中途半端に似た模様だと天敵に見破られてしまうため、はっきりどちらかのタイプになることが生き残りに重要です。
そこでこのチョウは、模様や形を決める複数の遺伝子を染色体上にぎゅっとまとめて一緒に働かせる仕組みを持っています。
この仕組みを「スーパー遺伝子」(超遺伝子)といいます。
スーパー遺伝子とは、複数の遺伝子がまるで一つの大きなスイッチのように働き、複数の特徴を一気に切り替えることができる仕組みです。
例えるなら「お弁当箱の中に仕切りを入れて、それぞれの料理が混ざらないようにしている」のと同じようなものです。
この仕組みがあるおかげで、中間の模様を持つ雑種が生まれる確率が低くなります。
こうした仕組みのほかに、もう一つの工夫があります。
それは、「優性」という遺伝子の性質です。
ここで先ほどのシードクラッカーという小鳥の例を思い出してみましょう。
シードクラッカーはクチバシの大きさが極端な二タイプに分かれていますが、大型クチバシを決める遺伝子が「優性」だということが知られています。
遺伝子には「優性」と「劣性」という性質があり、優性の遺伝子は、たとえ異なるタイプの遺伝子とペアになった場合(雑種)でも、自分の特徴を強く表現できるのです。
道路に例えるなら、道の両側にガードレールを置いて、真ん中に中途半端な形が生まれるのを防ぐ仕組みだと言えるでしょう。
実際にシードクラッカーでは、この優性遺伝子のおかげで中間型の個体が生まれにくくなっています。
さらにもう一つ重要なのが、「エピスタシス」(遺伝子の相互作用)という仕組みです。
遺伝子は単独で働くこともありますが、中には「他の遺伝子と協力して初めて効果を発揮する」タイプのものがあります。
たとえば、ペアのダンスを想像してみてください。
長い間ペアで練習をしてきた二人なら息の合ったダンスを踊れますが、突然パートナーを取り違えると、うまく踊れません。
これと同じように、特定の遺伝子ペアが長期間セットで働いてきた場合、途中で違うタイプの遺伝子とペアになってしまうと、うまく機能しなくなってしまいます。
こうした「遺伝子の相性問題」が起きると、中間型の雑種は生き残る確率がさらに下がります。
つまり、エピスタシスは、中間型をさらに不利にし、極端なタイプだけを残しやすくする働きをしているのです。
こうした遺伝子の巧みな工夫は、いわば「遺伝的チート」(遺伝的な抜け道)だと言えます。
なぜ「チート」と呼ぶのでしょうか?
普通、極端に異なる2タイプがはっきり安定すると、それぞれが異なる種に分かれてしまうのではないかと思われますよね。
しかし、この遺伝的チートが進化すると、違うタイプ同士が交配しても不利な中間タイプが生まれる確率が大きく下がるのです。
そのため、「交配可能な状態」が保たれ、かえって種が分かれにくくなるという不思議な状況が生まれます。
これは、遺伝子のレベルで「異なるタイプ同士が交配可能なまま共存する」という絶妙なバランスが作られることを意味しています。
逆に言うと、もしこの「遺伝的チート」が進化しなかった場合、違うタイプ同士が交配すると不利な雑種がどんどん生まれてしまいます。
そうなると生き物たちは自然と「自分と同じタイプ」と交配するようになり、やがて遺伝子の違いが蓄積し、種が分かれていくのです。
最近のゲノム(遺伝子情報)研究では、このような巧妙な仕組みが、遺伝子のクラスター(集団)としてまとめて進化しやすいことが明らかになっています。
たとえば、「染色体の逆位」(遺伝子の順序が逆さになる変異)によって有利な遺伝子がまとまるケースや、偶然近くに並んだ遺伝子が一緒に受け継がれるケースがあります。
こうした遺伝子の連携が、中間型の個体を減らすことに役立つことがわかっています。
シロオビアゲハやイトヨのような例以外にも、自然界ではこうした遺伝子のクラスターが数多く見つかっています。
この研究チームが出した重要な結論は、まさに「この遺伝子の巧妙な仕組みがどれくらい速く進化するのか」を解明することが、種分化を促進する条件と抑制する条件を理解するための重要なカギになるということでした。




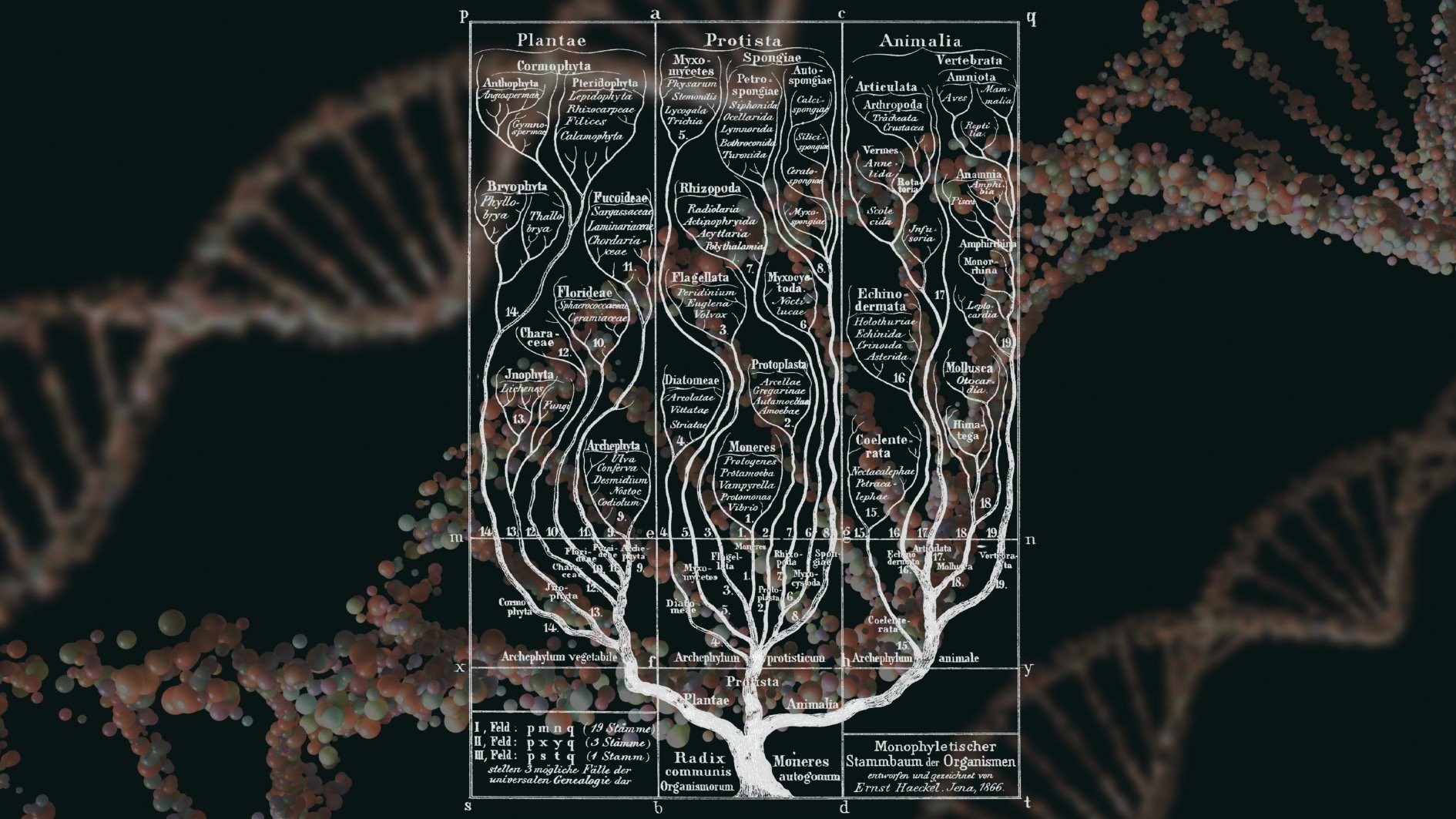























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)



























