10代への「寝る前の禁止」ルールは守られておらず、影響も小さい
研究の結果、まず明らかになったのは、寝る前のルールがほとんど守られていないという現実です。
寝る前1時間にスクリーンを使った子どもは99%に達しており、ほぼ全員が該当しました。
しかも83%の夜で平均32分もスクリーンを利用していました。
内容はスマホやタブレット、テレビ、ゲーム機など多種多様です。
寝る前の運動(中強度以上)は、22%の子が全体の7%の夜だけ行っており、しかも平均2.3分と非常に短時間でした。
また、寝る前の飲食(夜食や飲み物)については、約3分の2の子どもが研究期間中に一度は寝る前に食事やスナックをとっており、実際には30%の夜で何かしら食べていました。
夜食の多くはスナックや甘い飲み物、時にはカフェイン入り飲料も含まれました。
「寝る前に○○禁止」とよく言われますが、そもそも、そのルールを気にしている若者はほとんどいないのかもしれません。
では、こうした若者たちの睡眠は実際どうだったのでしょうか。
寝る前にスクリーンを使った夜でも、「総睡眠時間」や「睡眠の質(途中で起きる回数など)」には大きな変化が見られませんでした。
ただし、スクリーンを使わない夜と比べて、スクリーンを使った夜は23分ほど寝つきが遅くなっていました。
つまり寝る前にスマホを使うと、「寝つきが少し遅くなるが、依然としてぐっすり眠れている」という結果でした。
運動した夜は、「総睡眠時間」が平均34分も長くなっていました。
これは現代の10代の睡眠不足を考えると、むしろメリットにもなりうる変化です。
なお、中強度以上の運動自体は平均2.3分とごく短時間だったため、もっと長く・頻繁な運動だと違った結果になるかもしれません。
夜食や飲み物(カフェイン・糖分・脂質を含む)については、「その夜の睡眠」への目立った悪影響は見つかりませんでした。
つまり、寝る前に食べたからといって睡眠が悪化するとは一概に言えなかったのです。
この研究が示す新しい見方は明快です。
「寝る前にスマホやおやつを禁止しなければならない」というルールは、現実の子どもたちの行動や科学的なデータと必ずしも一致していないと言えます。
寝つきの遅れなど、一部にある程度の影響は見られるものの、本研究の観察期間内では、睡眠不足や質の大きな低下は見られなかったからです。
また、そもそもルールが守られていないので、「現実的なルール」とは言えないのかもしれません。
ただし、ルールが不要なわけではありません。
この研究で観察された変化に「まったく実害がない」とは言い切れないからです。
特に寝つきが20分以上遅れることは、敏感な子や翌朝が早い子にとっては十分な不利益となる場合もあります。
また、夜の運動についても、より頻繁で長い運動や他の生活習慣と組み合わさった場合の影響は今後の研究が必要です。
さらに、本研究は観察研究であり、因果関係を完全に証明したわけではありません。
この研究は、「寝る前ルール」に対する現実的な見直しの必要性を、客観的なデータで初めて明確に示した点は重要です。
今後は、完全な禁止よりも個々の生活リズムやバランス、適度さを重視した新しいガイドラインの必要性が示唆されています。
オタゴ大学の研究チームは、今後も10歳から15歳を対象にさらなる調査を進める予定です。
































![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)




















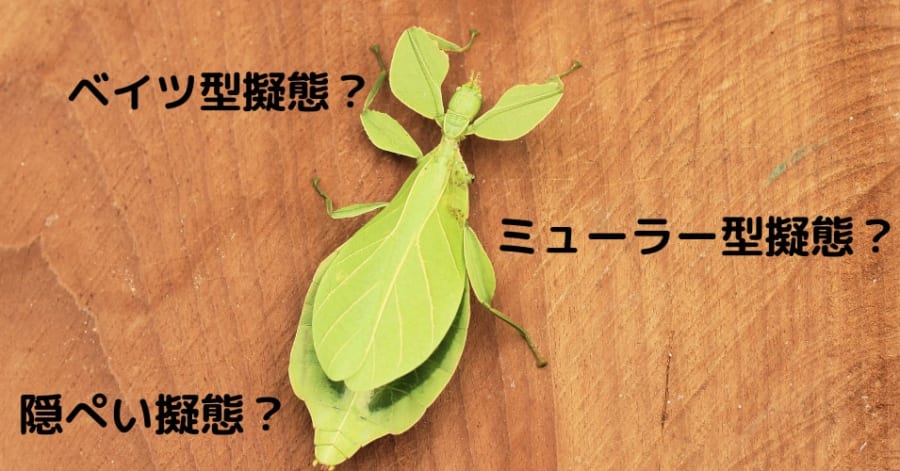







それを言ってる大半の親だって言われる側だった十代の頃は無視してただろうしね
自分ができもしなかったことを言ったって子供は敏感にそれを感じ取って鼻で笑ってるよ
まあ大人は自分に酔ってるか無害さアピールに夢中してるしね