本文2:生命活動と光のつながりが明らかに
撮影の結果は驚くべきものでした。
まず、マウスでは生きているときには明確な光が検出されました。
しかし、安楽死した直後には、その光が全身で顕著に低下しました。
まだ体温は残っているのに、光が大きく弱まったという結果は、この発光が単なる熱や外的な影響ではなく、生きている細胞の化学反応に関係していることを示しています。
なお、この比較では死の前後でそれぞれ約1時間の露光を行い、条件の違いを丁寧に見分けています。
植物でも同じように、興味深い変化が見られました。
気温を上げたり、葉を少し切ったりすると、光の強さが増しました。
さらに、試した複数の処理の中では、傷ついた部分に局所麻酔薬(ベンゾカイン)を塗った条件が最も強い発光を示しました。
これは、植物の体の中でストレスやダメージに反応する化学反応が活発になった結果だと考えられます。
こうした結果から、研究チームは「超微弱光子放出」は生命活動の指標になりうると考えています。
つまり、この光を観察すれば、体の中でどんな反応が起きているのかを、外からそっとのぞくことができるかもしれないのです。
この技術には、医療や農業への応用も期待されています。
たとえば、人や動物の健康状態を体に触れずに評価したり、植物が病気になる前にストレスを検出したりできる可能性があります。
もちろん、今のところこの光は非常に弱く、撮影には長い時間と慎重な環境制御が必要です。
リアルタイムで観察するには、さらに技術の改良が求められます。
それでも、見えないはずの“生命の光”をとらえたという成果は、生体活動を非侵襲的に可視化する新しい手法の可能性を示した重要な一歩といえます。
研究者たちは、この光を「生命が発する小さなメッセージ」と呼んでいます。
もしかすると未来には、私たちの体や植物が、健康状態を“光”で知らせてくれる時代が来るかもしれません。
目には見えないけれど、確かに存在するその輝きが、生命の新たな理解への道しるべとなりつつあるのです。




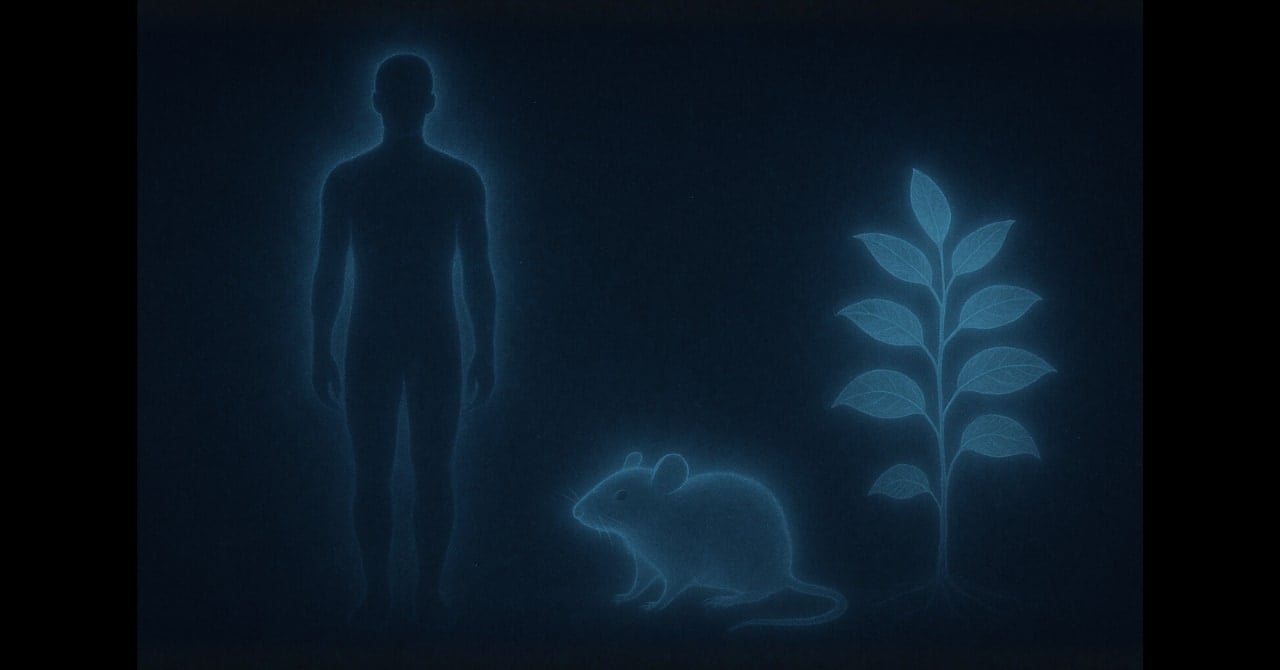



























![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)




























生き物ちゃんの命の輝きを見よってやつですね。
生命探査とかにも使える日が来るといいですね。
モンローの言っていたルーシュのことかな。
昔、オカルト分野で言われていた「オーラ」と同じものかな?
科学者「そうだ!命の輝きを見よう!(命を殺しながら)」
やっぱ科学者ってクズだわ…w
映画の話です。
老人が死を迎え、看取られる際に家族に対して神々しく光を感じた述べるシーンがあります。
どうでもいい。勝手に光ってろ
これは重要だぞ・・・
災害救助でも生きている人間を探すべきだ・・・
埋もれた生者を感知するとき
生者を誤って火葬しそうなとき
それぞれ役に立つかも・・・
どうでもいいなら見なきゃいいのに。どうでもいいことにわざわざ自分から首突っ込んで文句つけないと気が済まないタイプなんだね(笑)
これは熱光源による発光ですよね
細胞に負荷がかかるなど、細胞が多く働くときに発光する理屈です。
頭をぶつけて火花がでた、辛くて口から火が出たなど、昔から目には見えない感覚は人に伝わっています。
可視化することはもっとシンプルな方法でありますが、分野違いで化学博識者こそ気付きづらいでしょう。
では時代を待ってみましょうか
全く読解力が無いんだね、化学発光だ。
これらの研究は、かなり前から研究対象となっている。一番古いもので、ギロチンの後何回瞬きしたか。(15回程度、神経細胞は内蔵酸素で3分程度生きる。つまり意識はある。)生前と死後では体重に差がある。(2から3g程度の低下。魂の重さ?)
生き物である限り、化学反応が停止すればゆっくりと体温低下となる。赤外線としての光子量の低下。ただ、環境が絶対零度でない限り光子は発せられる。(背景放射と同じ考え)
死後硬直のエネルギー位置から緩むまでのエネルギーの低下。その後酵素による自己分解のエネルギー量の増大。体に多数存在する細菌などによる分解エネルギーの放出。
これは劇的で、骨髄の分解まではかなりの時間を要する。そしてリン酸カルシュウムから、炭酸カルシュウムへの移行。全て発熱反応であり、活性酸素は重要な役割を担っている。強力な酸化反応による発熱。つまり光子の放出。
全て化学反応と生物物理で説明可能。感光であるから光子が関係。
さて、この光子はどれくらいの周波数の波であったかの記述がない。記述があれば、どの周波数帯なのか色分けができる。
全ての生き物は、イオンをうまく利用している。この時微細な磁場が発生する。
また、生き物は食べ物として大変微量の放射性物質を摂取し自己も微量の放射線を発する。
このようなたくさんのパラメーターを排除しているかどうか記述がなく生体発光の実験結果としては不十分である。
代謝が高い小型動物は発光性が高い予想ができ、皮下脂肪の多い大型動物では少ない予想となる。
また、完全に石化した化石や琥珀内の昆虫などは腐敗という工程がない限り発光しないと予想できる。
すぐに消えるのではなく、徐々に消える。この時間経過の記述もない。
生体発光は、40年以上前にアメリカサイエンス誌に発表されている。まだ素粒子の標準理論のない時期である。
”さて、この光子はどれくらいの周波数の波であったかの記述がない。記述があれば、どの周波数帯なのか色分けができる。”
本記事冒頭に記載された論文アブストラクトの記述によれば200-1000nmとあり全可視光領域を含んでいる。そもそも動物は赤外線カメラで検知できるので、少なくとも赤外領域は論外。
別にギロチンしなくても脳への血流を止めるだけで人間は意識を失うんで、
ギロチンされても意識があるのは無理があると思われます
これってキルリアン写真とは違うのん?
命の輝き…ってコト!?
ストレスを受けると光り方が強くなるのなら、どれくらい強いストレスがかかっているのかの客観的指標として応用出来るのかも。
貴方の魂は、何色ですか?
真っ暗な部屋に閉じ込められた時、自分の身体は見えますか?
つまりそういう事。
下らない実験で動物を安楽死させるなボケ
昔、自宅で棒を回して遊んでいた時に、その棒が自分の頭に当たりまして、その瞬間に目から黄緑の蛍光色の星型の光が飛び出してびっくりしました。星は輪郭だけで、中は空洞でした。五芒星の典型的な星マークでした。漫画の中だけの誇張だと思っていましたが、本当だったのでびっくりしました。本編の記事とは関係ありませんが、他の方のコメントを拝見して思い出しました。人間は微量の電気で動いているらしいですが、光はその電気と関係しているのでしょうか?テレパシーがあるとしたら、やはり電気が関係しているのでしょうか?超能力者が実在したら、強力な電気を放っているのか?それとも他者の電気に働きかけて利用するのでしょうか?植物や生物に電気だとか光だとかって不思議ですね。
そら、励起して基底状態に戻るとき(電子が内側に落ちる)光子は出るやろ。何を当たり前のことを。
体内発光(ガンマ線)を計るPET(陽電子断層撮像)は放射性核種を飲んで、体内で核反応や陽電子の対消滅をおこさせる侵襲があります。自発光の光を受動的に測る分には、被曝は生じません。
この記事の生物発光が過酸化物やラジカルの化学反応の副産物として出るなら、応用が想像できます。記事にあるリアルタイム性は不要です。
暗室に入って、(睡眠導入剤か筋弛緩剤で)数時間寝てもらう間に計測します。サーモグラフィと併用して経口を絞った光電子倍増管を並べます。発熱と発光が重なる部位は急性炎症、発光が多い部位は(腹部大動脈の硬化や腎動脈炎など)慢性炎症をを疑えそうです。腺筋症、橋本病など自己免疫疾患にも応用できそうな夢があります。
前立腺炎、拍動性の頭痛、歯根部の炎症など皮膚表面に近ければ、拾える光量も増えるでしょうから、狭い経口のセンサーを並べたプローブを直接充てることで解像度をあげられそうです。
単細胞生物で調べてみよう。
生きてるときは体温で励起されやすいだけかもしれない。
植物でも調べているのだから、体温は関係ないのでしょう。