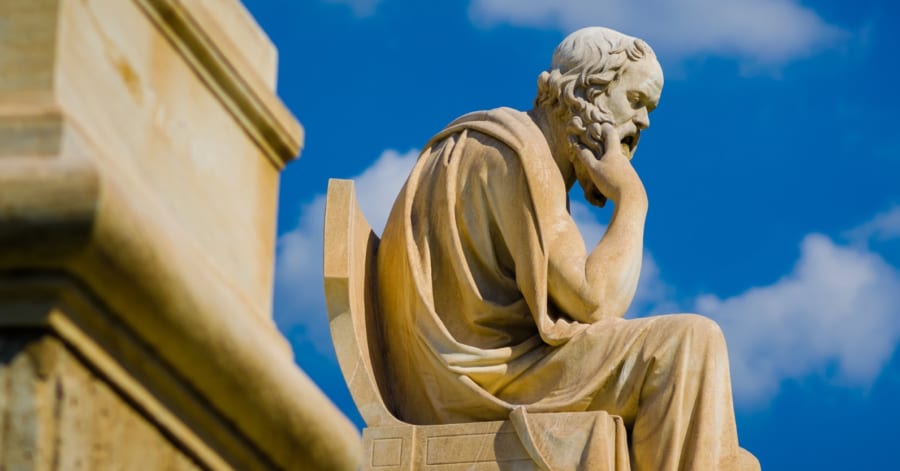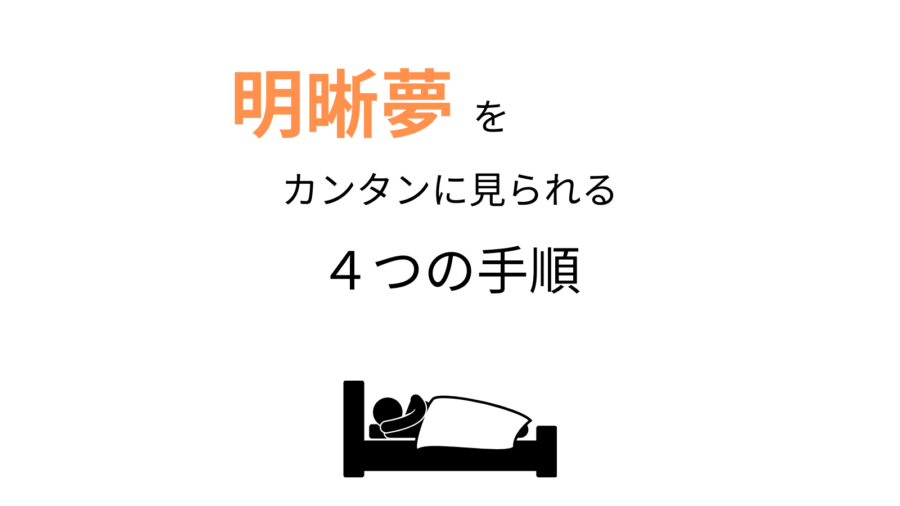『繊維神話』を科学が覆す。本当に便秘に効く食べ物は?

「便秘になったら、とりあえず食物繊維を摂りなさい」。
このフレーズ、誰でも一度くらいは聞いたことがありますよね。
学校の保健室でも病院でも、便秘の相談をすると、まず言われるのはだいたいこれです。
食物繊維というのは簡単に言えば、食べても人間の体で消化されない成分のことです。
この消化できない繊維は便に混ざってその量を増やすので、「便のかさ」が増えることで腸の動きが活発になり、便秘が改善されると言われています。
だから、便秘の人は野菜サラダを山ほど食べたり、野菜ジュースをガブガブ飲んだり、食パンは「全粒粉入り」や「ブラン(ふすま)入り」を選んだりと、とにかく食物繊維を積極的に摂るようにアドバイスされてきました。
ところが現実はそう甘くありません。
実際にやってみると「繊維だけ頑張って摂っても全然効かない!」という話はよくあります。
お腹の調子は一向に良くならず、「ほんとに繊維って便秘に効いてる?」と疑問に感じている人は多いでしょう。
事実、慢性的な便秘(長く続いている便秘)に悩む患者さんの中には、食物繊維をいくら摂ってもなかなか改善せず、満足できない人が過半数を超えるという調査報告まであるくらいです。
ちょっと意外かもしれませんが、便秘というのは実はとてもやっかいな症状です。
ただお腹が張るとか痛いだけでなく、体が重くだるくなり、集中力まで落ちてしまいます。
その結果、仕事や学校生活のパフォーマンスも下がり、実際に経済的な損失につながることすらあります。
さらには、慢性的な便秘のために病院に通い続けると、そのぶん医療費もかさんでしまいます。
だから、誰もが「なるべく薬に頼らず、食生活の工夫だけでなんとか便秘を治したい!」と考えるわけですね。
ところが、これまでの医療ガイドライン(医療現場での治療の基準)では、便秘への食事療法はなぜか非常にざっくりしたものでした。
「とりあえず繊維と水分を増やしましょう」という、ちょっと漠然としたアドバイスが中心だったんですね。
具体的な食品や飲み物の指示がなかったため、繊維をとっても便秘が治らないと困っている人は実際にとても多かったのです。
そもそも、なぜこの「とりあえず繊維と水分」が常識になったのかというと、生理学的には一応ちゃんとした理由があるのです。
食物繊維が便のかさを増やし、水分をとることで便が柔らかくなる、というのは確かに間違いではありません。
直感的にも、便の量が増えて柔らかくなれば出やすくなるだろう、と誰でもイメージしやすいですよね。
でも、科学の世界では「理屈として正しそう」と、「実際に効果があること」はまったくの別物です。
これまで便秘と繊維の関係を調べる研究はいくつもありましたが、それぞれ小規模で、しかも研究のやり方がバラバラでした。
実際の効果をちゃんと調べるには、患者さんを無作為にグループ分けして比べる「RCT(ランダム化比較試験)」という厳密な方法が必要なのですが、これが十分には行われていなかったのです。
つまり、「とりあえず繊維が便秘に効く」という常識は、ちゃんとした科学的な裏付けがないまま広まってしまったわけですね。
これはいわば、「効きそう」というイメージだけが独り歩きした『繊維神話』みたいなものです。
長年、この常識が中途半端なままで止まっていた背景には、こうした研究の不統一とRCT(ランダム化比較試験)試験の不足がありました。
そこで、今回の研究チームは、この曖昧な便秘ケアの常識に真正面から挑みました。
研究チームを率いたのは、イギリス屈指の名門、キングス・カレッジ・ロンドン(KCL)の科学者たちです。
彼らは世界中の便秘研究をくまなく集め、膨大なデータをもう一度ゼロから見直すことにしたのです。
食物繊維や水分は、本当に便秘改善に役立つのか?
もし繊維や水分以外にもっと効果的な食品や方法があるならば、それはいったい何なのか?
こうした「常識の壁」を超えるために、科学者たちは本気のチャレンジを開始したのです。












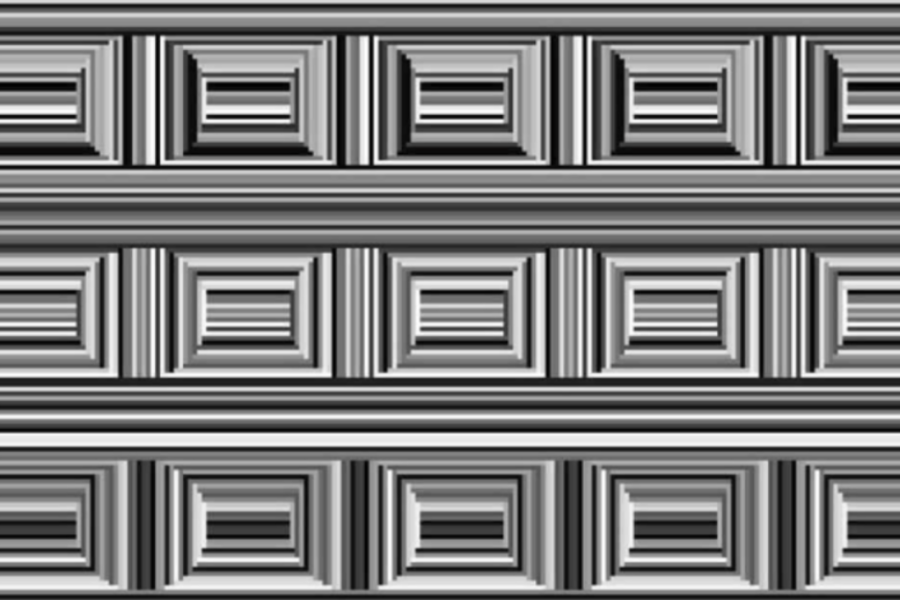
















![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)
![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)