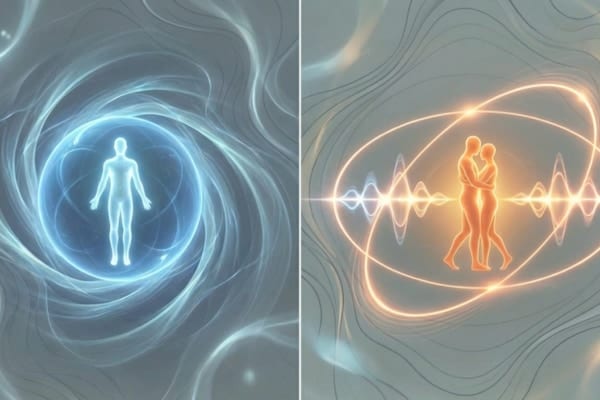「時間と脳の関係」を、どうやって確かめたのか
西南大学の研究チームはまず、中国の大学生240人に協力してもらい、ADHDの傾向と、未来をどれだけ意識しているか、という二つの特徴をアンケートで測定しました。
ADHD特性には、成人用の自己記入式質問票である「Adult ADHD Self-Report Scale(ASRS)」を使いました。
これは「集中が続かない」「順番どおりに物事を進めるのが苦手」といった項目にどの程度あてはまるかを答えていくテストです。
一方で未来志向には、「Zimbardo Time Perspective Inventory(ジンバルドー時間的展望尺度(ZTPI))」という心理測定法を用いました。
これは「将来のために今の楽しみを我慢するほうだ」「長期的な目標をはっきり持っている」といった問いに答えることで、どれだけ日ごろ未来を意識して行動しているかを数値化するテストです。
この結果、未来志向が高い人ほど、注意力の欠如や多動・衝動性といったADHD特性のスコアが低いという、これまでの研究と同じ傾向が改めて確認されました。
次に研究チームは、全員にMRI装置に入ってもらい、脳の画像を撮影しました。
ここで行われたのは、大きく二種類の解析です。
一つ目は「ボクセルベース形態解析(Voxel-Based Morphometry)」という方法で、脳の各部位の灰白質の量を比べる解析です。
灰白質とは、神経細胞の本体が集まっている部分で、「その場所の計算資源の多さ」をざっくり見るイメージに近いものです。
この解析の結果、未来志向が高い人ほど、自己を振り返ったり行動を計画したりするときに関わる上内側前頭回や左前中心回で灰白質が多いことが分かりました。
一方で、左下頭頂小葉や左上側頭回といった情報処理や認知制御に関わる領域では、未来志向が高い人ほど灰白質が少ないという、逆向きの関係も見つかりました。
これは「機能が弱い」という意味ではなく、脳のネットワークが成熟し、処理が効率化されている状態だと考えられます。そのため未来を強く意識できる人ほど、目の前の刺激や情報に必要以上のリソースを割かずにすむ“効率的な処理”が行われている可能性があります。
これが予定に合わせて行動をコントロールする能力につながっている可能性があるのです。
二つ目は、「安静時機能的結合解析(resting-state functional connectivity)」です。
これは、何も課題をしていないときに、脳の領域同士がどれくらい同時に活動しているかを調べる方法で、「どことどこがよく情報をやり取りしているか」というネットワークの地図をつくることができます。
研究チームは、先ほど灰白質の変化が見つかった領域を「種(シード)」として設定し、そこから他のどの領域に向かって強い結合が伸びているかを調べました。
その結果、とくに重要だったのが左下頭頂小葉です。
この左下頭頂小葉は、未来志向が高い人ほど、内側前頭前野の中でも背内側前頭前野と腹内側前頭前野という二つの部分と強く結びついていることが分かりました。
これらの前頭前野の領域は、「デフォルトモードネットワーク」という自己や将来のことを考えるときに働くネットワークの中核であり、将来の目標やその価値を評価する役割を持つと考えられています。
これが優先順位をつけて予定を考えるための土台になっている可能性があります。

































![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)