雲が空に浮かんでいられる理由

雲は、水蒸気(空気より軽い)が上昇気流によって持ち上げられ、冷やされたときに発生します。
水蒸気(透明)が冷えて凝結し、小さな水滴(光を乱反射するため白く見える)となるのです。
この雲の水滴は空気より重いため、当然ながら落下します。
ただしレモン氏は「非常に小さい水滴は、それほど速く落下しない」と指摘します。
雲の中に存在する水滴の平均的なサイズは、雨粒の約100万分の1であり、これは地球と太陽の体積比率とほぼ同じです。
つまり引力によって生じる「微小な水滴の落ちる力」はそこまで大きくなく、もっと強い上昇気流によって、長時間持ち上げられ続けます。
雲全体の重量は500トンもありますが、水滴一粒一粒はとても小さくて軽いため浮いていられるのです。

しかし当然水滴同士はぶつかればくっついてより大きな水滴へと成長していきます。
拡散した水滴がまとまって成長する速度は大体一致するので、あるタイミングで上昇気流が水滴を支えきれなくなり、まるで崩壊するように地上へ雨となって降り注いでくるのです。
夏に積雲が突然大雨を降らせるのもこれが原因です。
水滴の密度が高まり暗くなった雨雲を見上げて、雨が降りそうと感じるのはこのメカニズムを私達も自然と理解しているからでしょう。
1km3の積雲が学校のプール一杯の水を抱えていて、ゾウ500頭分の重さの水を地上に落とすと考えると、ゲリラ豪雨がヤバいのも当然でしょう。
雲が抱えている重さを舐めてはいけないようです。






























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)


















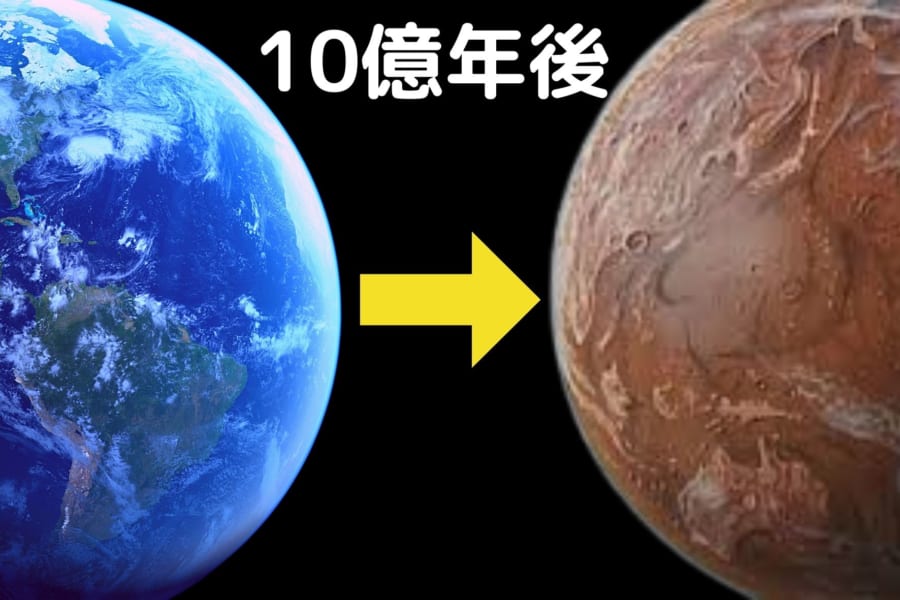
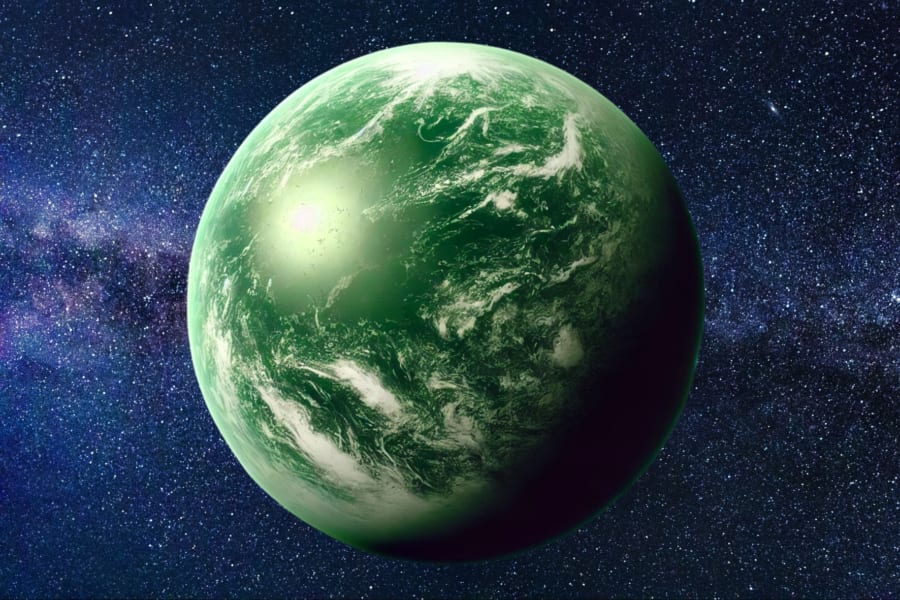


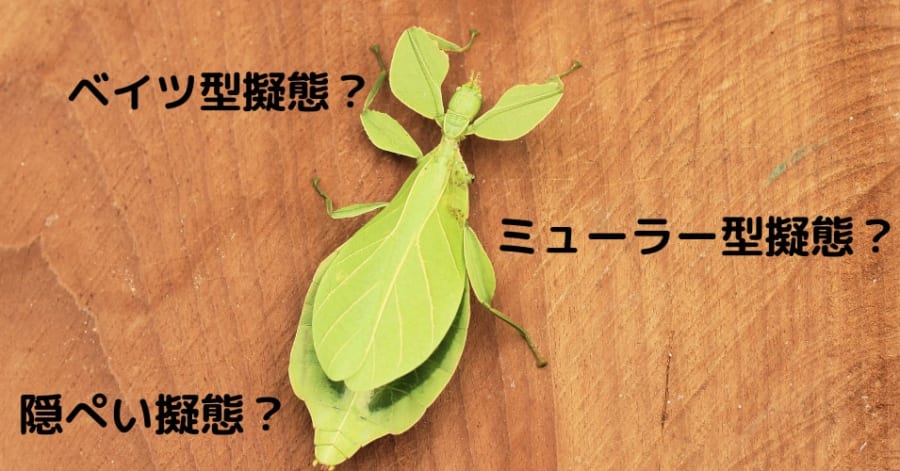






雲の動きを撮影した動画を見てください。1分間で猛烈に変化します。同じ形状で浮いているとは思わないように。
山村慕鳥の詩「おおいくもよ~ずつと磐城平いはきたひらの方までゆくんか」
雲の答え「いいえ、私はすぐに消えます。」
誰が何を観察して、何を測っているかを理解して雲の重さを考えましょう。
面白かった。
> 山村慕鳥の詩「おおいくもよ~ずつと磐城平いはきたひらの方までゆくんか」
> 雲の答え「いいえ、私はすぐに消えます。」
秀逸です