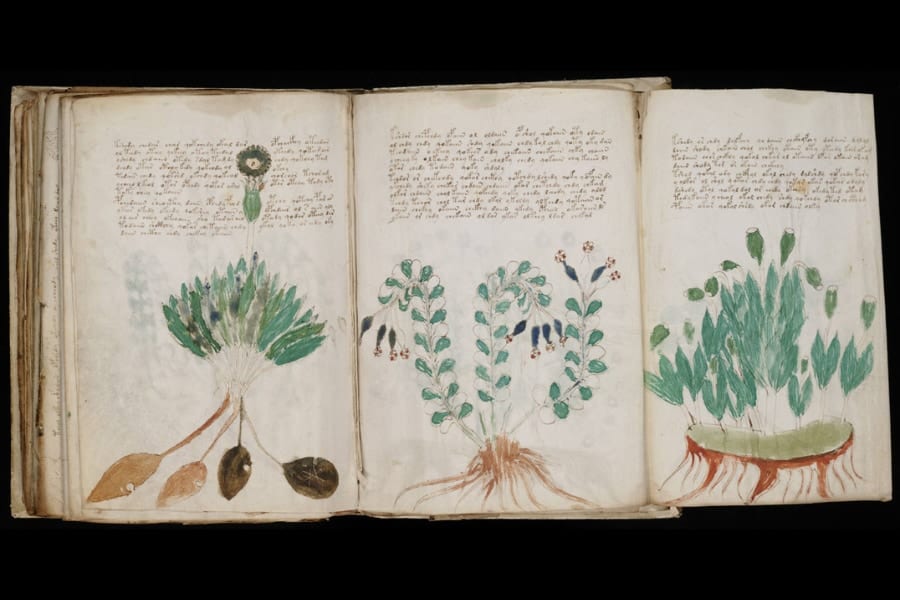憧れと嫌悪が入り混じった、女性たちの纏足観

このように纏足は物凄い痛みを伴うものであり、女性に対する負担は重かったのです。
それでは当の女性自身は纏足についてどう捉えていたのでしょうか?
先述したようにかつての中国の村々においては、小さな足が美しさの基準とされていました。
足の小さいことは、ただ美しいというだけではありません。
嫁ぎ先にて姑の目に適い、家庭の和を保つ要ともなりました。
ことわざにすら「纏足のない嫁は家を揺るがす」とあったというのだから、あながち冗談ではなかったのでしょう。
思い出されるのは、現代におけるハイヒールです。
曰く「纏足はハイヒールと同じだ」との声もあります。
確かに、無理に足を縛り、痛みを耐えてまで美を追求する姿勢には通じるものがあるでしょう。
だが、現代のハイヒールは自らの選択で履くものです。
それに対し、纏足は時に親の命じるまま、あるいは周囲の同調圧力の中で強いられたものでした。
さて、纏足が結婚にいかに関係したかを考えてみます。
当時の結婚は本人の意思など尊重される余地がなく、家族が主導するものでした。
仲人はまず相手の足の大きさを見て、その良し悪しを評価したといいます。
纏足をした女性の足の小ささは、謙譲や道徳性の象徴であり、家庭に順応する証とされたのです。
こうして聞いていると悪しき文化のように感じてしまいますが、現代の価値観で纏足を単なる苦行として否定するのも片手落ちです。
小さな足に憧れを抱き、自ら進んで纏足に臨んだ少女もいたといいます。
例えば、ある少女の物語では、父親が反対し、母親も痛みを見かねて断念させようとしたにもかかわらず、本人は「私は頑固だから」と言い張って纏足を続けました。
周囲の女性たちが纏足をしているのを見て「私もあんな足になりたい」と憧れを募らせた結果です。
その一方で、纏足を忌み嫌う女性たちもいました。
ある女性は「夜な夜な足を縛られた布を緩めた」と語っています。
纏足の痛みは激烈であり、たとえ美への憧れがあったとしても、それを越える苦痛が彼女たちを襲ったのでしょう。
このように、纏足には憧れと嫌悪という二面性が絡み合っていました。
纏足に憧れる者にとっては、それは達成感や自己肯定感をもたらすものだったのです。
一方で、纏足に耐えかねた者にとっては、抑圧と苦痛の象徴でした。
だが、いずれの場合にも、彼女たちの小さな足は社会的な価値を具現化する存在であり、家族の中でも、地域社会でも、その役割を果たしていたのです。
結局のところ、纏足は個人の美意識だけでなく、家族や社会の問題でもありました。
親は纏足を通じて娘に家族の名誉を背負わせようとし、女性たちはその枠組みの中で、苦しみながらも己の価値を見出そうとしたのです。
この複雑怪奇な文化を、ただの過去の奇習として片付けてしまうのは惜しいです。
それは、現代の私たちの美や価値観にも、何かしらの問いを投げかけているように思えます。


























![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)