古よりあった小さな足への憧れ

纏足の起源については諸説あるものの、小さい足は古の頃から中国で好まれていました。
時を遡ること3世紀、詩人たちは妖精や娘たちの軽やかな足取りに魅せられ、5世紀頃には「小さな足」が詩の中でロマンチックに歌われていました。
9世紀、『酉陽雑俎』に収録された葉限の物語は、小足が美の象徴として描かれた一例です。
そして10世紀の宮廷では、踊り手たちの足が布で縛られ、そのしなやかな姿が称賛されました。
やがてこの風習は宮廷の女性たちの間で広まり、13世紀には官僚階級の妻や娘にも定着したことが発掘品から判明しています。
しかし、纏足が社会全体に浸透するのは明代以降です。
この時代の家父長制の中で、纏足は女性の謙虚さと忍耐を象徴し、良家の息子にふさわしい花嫁像を形作る手段となりました。
小さな足は美しさだけでなく、道徳的な資質までも表現するとされたのです。
また足に巻く布の材料となっている木綿の生産が広がると農村部にも浸透し、清代末期まで広範囲で続きました。
廃止への道は19世紀末から始まりました。
変法運動(清末期に行われた、西洋の制度を学んで中国の制度も改革しようとする運動)を機に士大夫(中国の知識階級)たちが纏足を批判し、康有為(こうゆうい)や梁啓超(りょうけいちょう)が設立した不纏足会が声を上げたのです。
中華民国時代には孫文や蔣介石が禁止令を出し、西欧的価値観が「時代遅れの伝統」に終止符を打つ助けとなりました。
さらに戦乱や文化大革命を経て纏足は完全に姿を消したのです。
こうして、中国の「小さな足」は歴史の彼方へと歩み去ったのです。














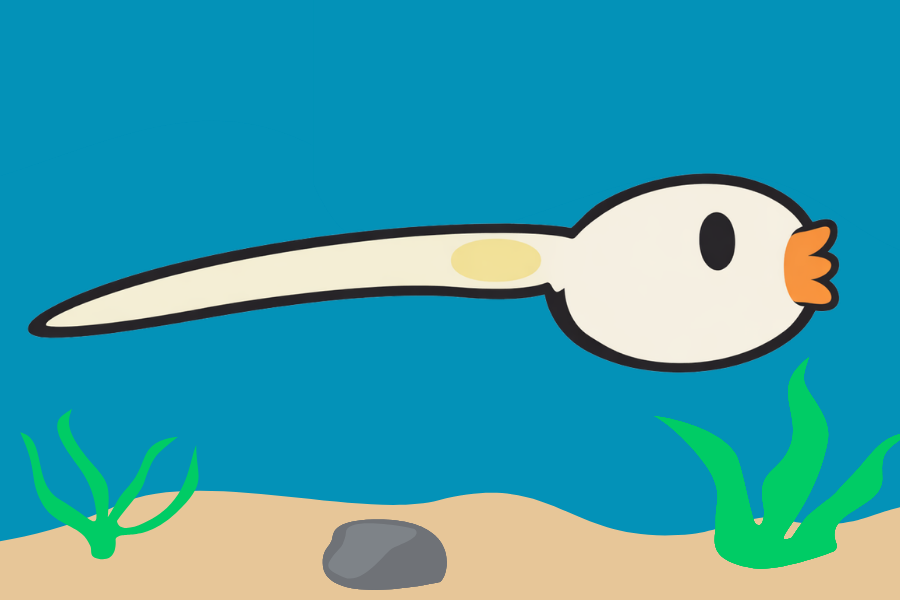
















![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)



























