名実ともに痛みを伴うものであった、纏足からの解放
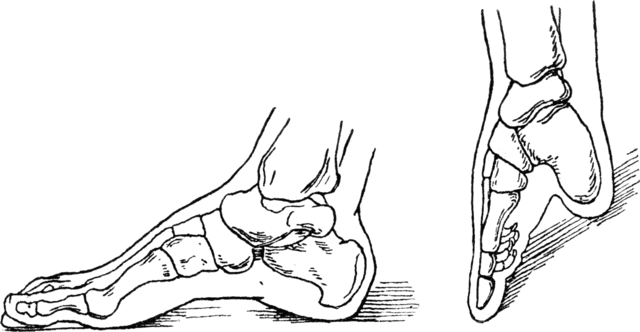
しかし1920年代に入ると、状況は一変します。
纏足の伝統が中華民国が主導した「放足運動」という波にさらわれ、一転して解放を強いられる時代が訪れたのです。
この放足運動は単なる通達では済まされず、人を派遣して徹底的に纏足をやめさせるという強制的なものでした。
これまで「纏足しなければならない」という社会規範に縛られていた女性たちは、今度は「纏足を解かなければならない」という別の圧力に苦しむことになったのです。
纏足を解くという行為は、女性たちに新たな痛みを強いました。
何十年も縛られて変形した足が完全に元に戻ることはなく、逆に歩行が困難になる場合もあったのです。
さらに、これまで足を隠すことが「正しい」とされていた社会において、人前に足を晒さなければならないという状況は、女性たちにとって大きな精神的苦痛となりました。
「解くこと」は解放ではなく、また別の形の束縛だったのです。
一方で、この運動の中で地域や世代間の違いも浮き彫りになりました。
都市部では放足が比較的速やかに進行したのに対し、農村部では纏足が美徳とされる風習が根強く残り、結婚に必要とされる場合もあったのです。
また、母親たちが娘に纏足をさせる背景には、伝統だけでなく社会的な圧力があり、その結果、家族間に軋轢が生じることもあったといいます。
しかし、放足運動がもたらしたのは苦しみだけではありませんでした。
教育の普及という恩恵も同時に生まれたのです。
これまで学校に通えなかった多くの女性が教育を受けられるようになり、家の外の世界に触れることで、新たな価値観を得る機会を得ました。
この変化により、家族や小さな共同体の価値観に縛られていた人々が、より広い視野を持つことが可能となったのです。
纏足の廃止は、一つの伝統が終焉を迎えた象徴的な出来事です。
しかし、その過程における苦痛や葛藤を見つめ直すとき、私たちはこの変革が単なる解放ではなく、社会の価値観そのものを揺さぶる試みであったことに気付きます。
それは、山間の風がもたらした痛みと希望の物語です。













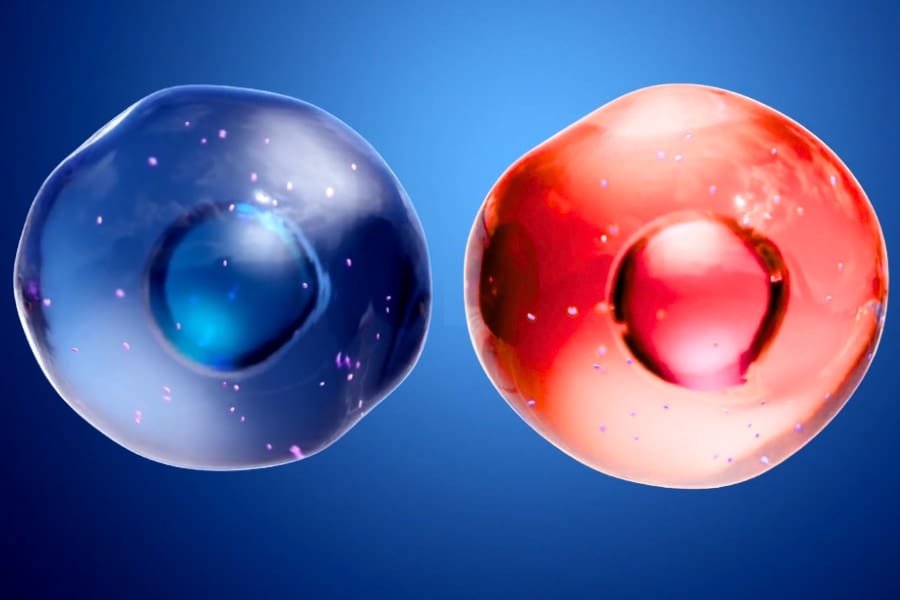








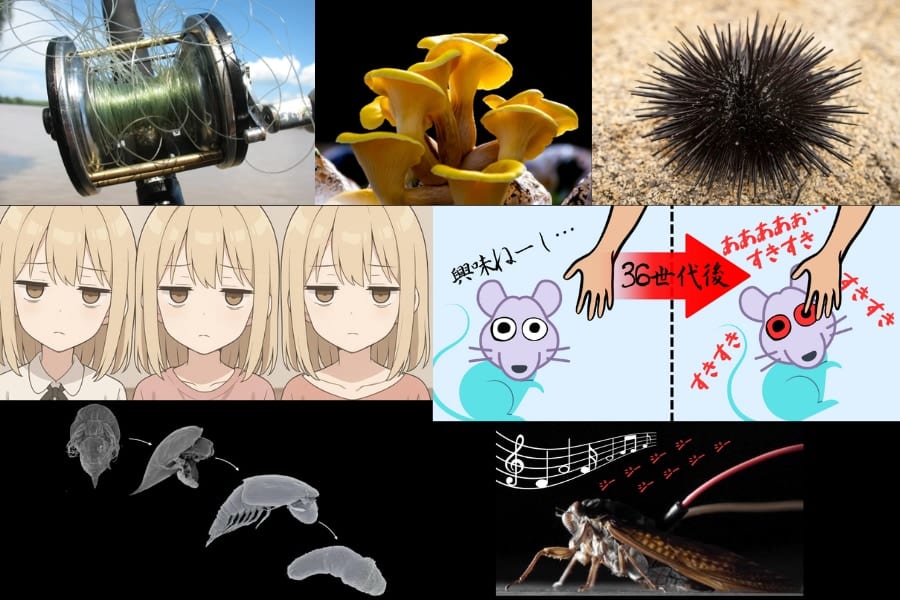








![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)
![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)















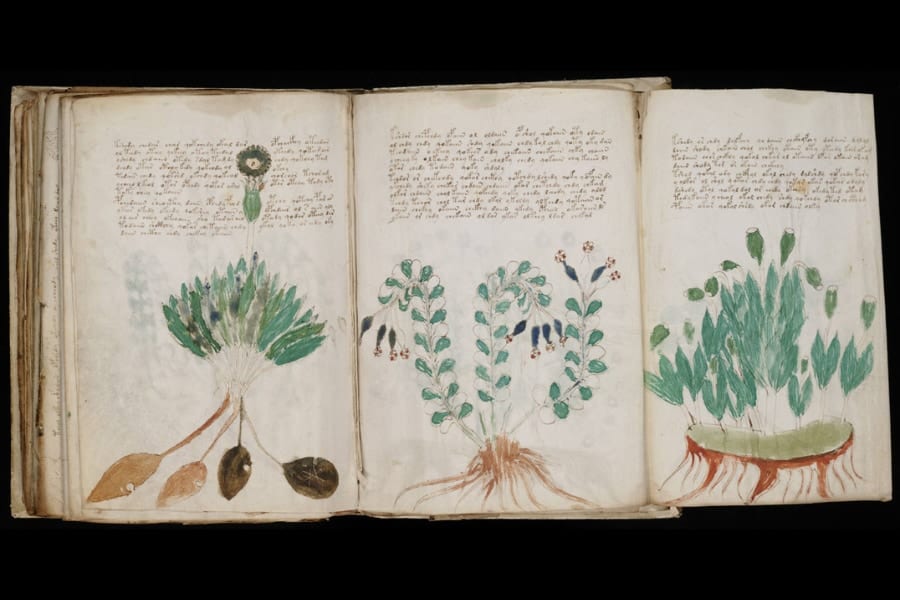












纏足へのあこがれは女性のスタイルの流行りもあったかもしれませんが足が不自由でも生きられ、また逃げられないと言った籠の鳥に似た背景が謙虚さを表すとともに女性の価値に繋がっていたのかもしれません