人を食べるべきでない科学的な理由
そもそも生物はヒトも含めて、自分たちの種に有利になるように生存競争を進めていかなければなりません。
その上で人が人を食べることは進化上の観点からするとデメリットだらけなのです。
食人行為のデメリットは大きく分けて3つあります。
1つ目は「狩りのコストが高すぎること」です。
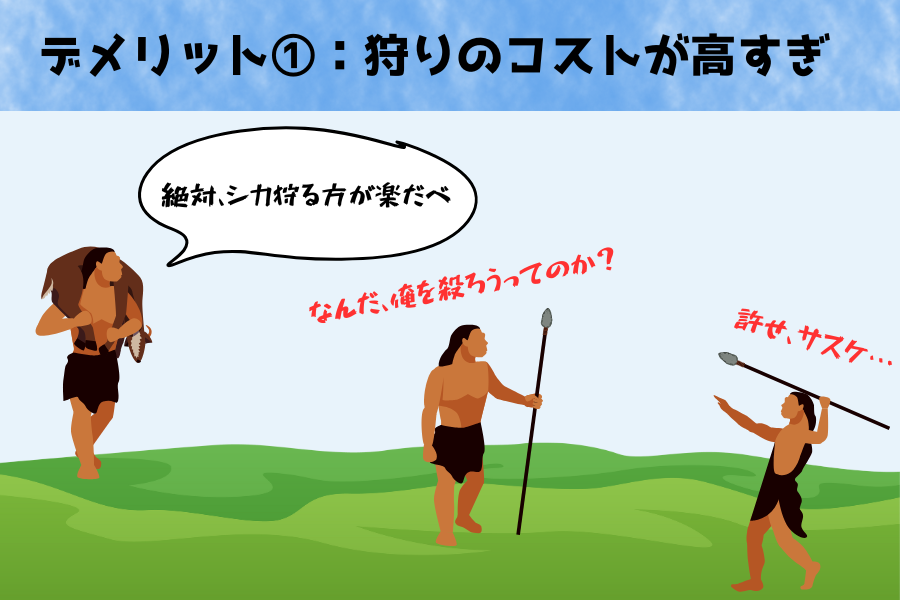
狩猟をする生物はいかに体力を削らず楽に獲物を得られるかをモットーにします。
もし人を好物とする食人族がいたとすると、彼らは自分たちと肉体的および知的に同レベルの相手を狩らなければなりません。
これはウサギやシカ、イノシシを狩るより遥かに労力がかかる上に、間違ったら自分がやられる確率が非常に高いのです。
まず、この狩りのコストという点で食人行為は割に合っていません。
2つ目は「人肉の栄養価が低いこと」です。
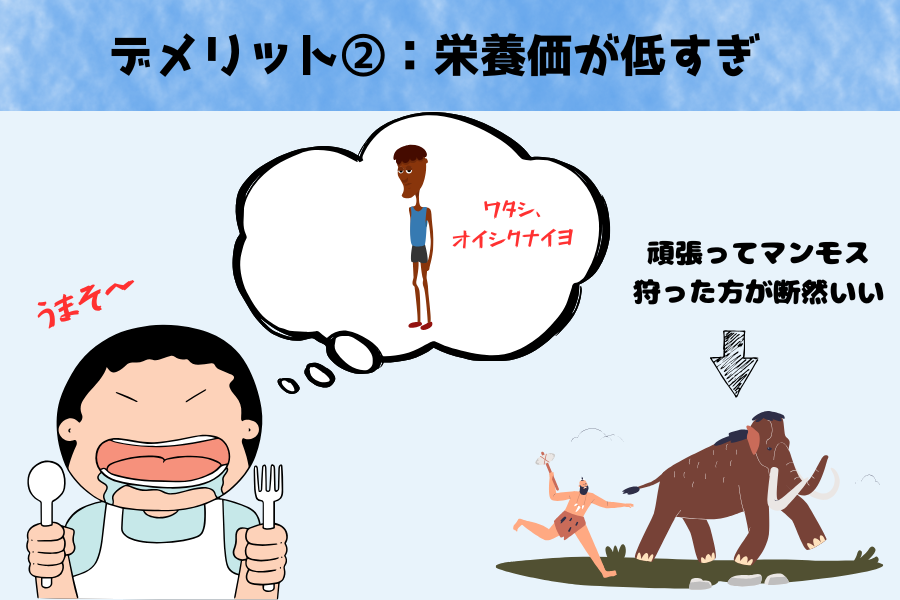
これについては英国ブライトン大学が2017年に興味深い研究を報告しました(Nature, 2017)。
ここで研究チームは「食人族が体重55キロの男性を食料にした場合に得られるカロリー量」を試算したのです。
具体的には、心臓は650キロカロリー、肝臓は2570キロカロリー、太ももは1万3350キロカロリー、上腕は7450キロカロリー、脳と脊髄は2700キロカロリーというように各部位のカロリーを計算し、これらを合わせて人体一つの総カロリー量は約12万〜14万キロカロリーになると算出しました。
一見するとすごい高カロリーにも聞こえますが、実はこれは25人の成人男性が半日もつかどうかの栄養しか得られない数字なのです。
それならば、集団で協力した1頭のマンモスを仕留めれば、同じ数の男性が2カ月間暮らせるだけの食料が得られるとチームは述べています。
なので、毎日の栄養を効率的に摂る上で食人行為はまったく向いていません。
しかし最大のデメリットは3つ目にあります。
それが「病気への感染リスクが極めて高いこと」です。
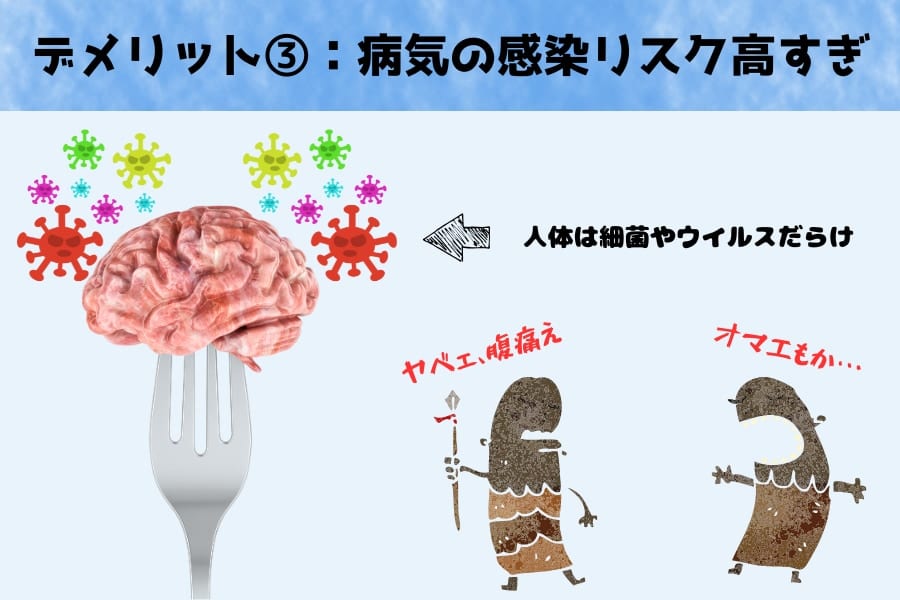
私たちの体は表向き健康そうに見えても、さまざまな細菌やウイルス、寄生虫などが棲みついている可能性があります。
そして重大なポイントは、ある人に感染した細菌やウイルス、寄生虫が同種の人間であれば容易に伝染しうる点です。
例えば、他の動物からヒトにウイルスが伝染するには、そのウイルスに何らかの遺伝子変異が起きる必要があります。
イメージとしては、コンセントのプラグの形がちょっと違う様を想像してもらうといいでしょう。
ある動物には挿せるコンセントでも、プラグの形が違うヒトには挿さらず、感染が起きません。
しかしヒト同士であれば、プラグの形を変えなくともそのまま感染できるわけです。
では日常的に人肉食を続けているとどうなるのか?
この疑問に答えてくれる実例が過去にあります。
南太平洋のパプアニューギニアに先住する少数民族「フォレ族」の事例です。
フォレ族は1950年代まで、日常的に死者の肉を食べて弔う風習を持っていました。
具体的には、死者の筋肉部位を男性が食べて、脳と臓器を女性が食べていたのです。
その中で奇妙な病気がフォレ族の間に広がり始めます。
全身の筋肉が緩んで上手く立てなくなったり、体中が激しく震えて止まらなくなったり、何も口にすることができず、最終的には肺炎で死亡してしまうケースが急増したのです。
この謎の病気は現地で「体が震える」という意味から「クールー病」と呼ばれています。

研究者が詳しく調べたところ、その原因は死者の脳内に潜む「プリオン」という病原性物質にあることが判明しました。
プリオンは周囲の正常なタンパク質を病原性物質に変質させながら、脳を徐々に蝕んでいく恐ろしい物質です。
これが原因でクールー病が発生しており、実際に脳を食べていた女性により多くのクールー病が見られていました。
このように食人行為を日常化させる集団は、いつか必ず何らかの伝染病を引き起こし、破滅の道を歩んでいく運命にあるでしょう。
こうした科学的な理由から「人は人を食べるべきではない」とはっきり断言できるのです。
































![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)




















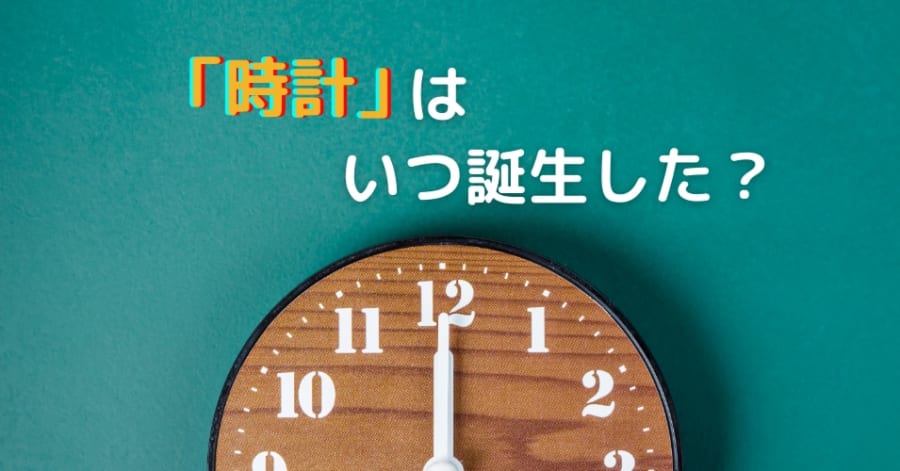
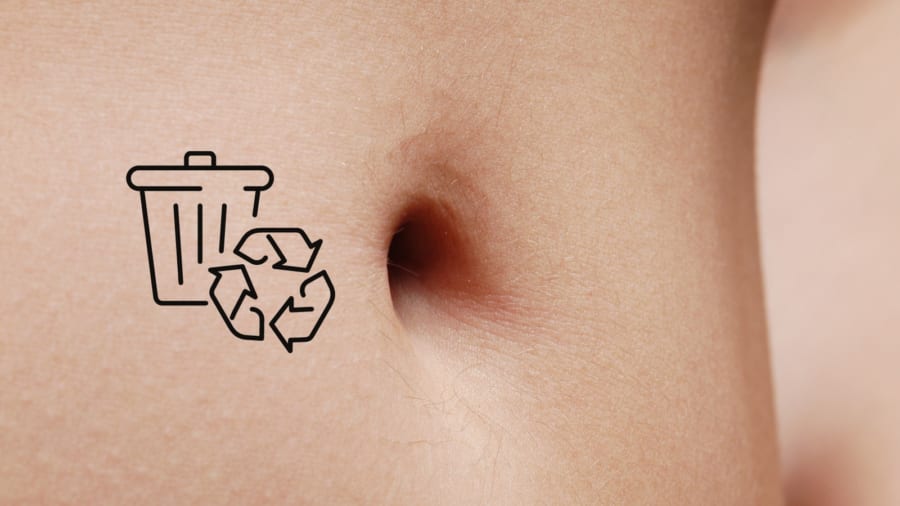






めっちゃ面白い
カマキリはカリバニズム遺伝子を進化の過程で獲得したのかな? ある面で効率的で自種完結型なのに対し、人間はカマキリと違う方向で進化してくれてよかった、のだろう?
倫理観とも関連しておもしろかったです。
人間はカマキリとは違う進化をしちゃったんですね。残念。あなたにバックから犯されながら貴方の頭をもぎ取って食べたかったな
メスカマキリさん怖い
カマキリは1年で死んじゃうからね。雄を食べても卵生んで直ぐ死ぬから、雌の体内に病原菌が蓄積しようがない。だから栄養取るのが優先されるんでしょうね。
👍🏻
オスを食べたメスと、オスを食べなかったメスの、産卵を比較した実験があり、それによると、
「オスを食べて栄養補給したメスのほうが、産卵数が多い」
とのことです。
カマキリ オス 食べられる 比較
等で検索してみてください。
カマキリは「自分より小さい動くモノ」は何でも捕食しようとするように出来ている、同種のオスも冷害ではない。
ゆえ、交尾直後のオスだけではなく交尾の為に近づくオスも捕食対象で、交尾できずに喰われてしまうオスも多い(逆に運よく逃げ延びて二匹目のメスと交尾に成功するオスも稀にいる)
自己犠牲精神の発露ではないのです。
人肉食は コスパ悪いから流行らないという説明が興味深かった
あと 多分 人肉は無理してでも食うほど美味くないのでは?
子供とか乳児とか、狩るためのコストが低い存在が居る以上、この説明は成り立たない。多産でなく再生産コストが高いとかなら分かるが。
子供や乳児など、狩猟コストが低いのは幾らでも有るので、論旨が間違い。多産でないので再生産コストが高いのならわかる。
「畜産」しようとするとコスパが悪いって話では?
人を育てるための「餌」は結局のところ人が食べるものでなければ健康に育たないんで、十数年分の時間と食料を糞に変えて(記事によれば)半日分のカロリーを作ってるのと同じってことになる。
失礼、半日じゃなくて12.5日/人か。
喰う為の品種改良してない種は美味くない
豚みたいな味らしい
子供や乳児を狩るコストは低くない。親やその部族は守るために戦うだろうし、守れなくても報復するし。
豚はイノシシを家畜化したものだから、イノシシは品種改良される前の原種という事になるが、イノシシ肉は豚肉よりも旨味が濃くて美味しいと言われています。
つまり豚とイノシシに関しては、喰う為の品種改良をしていない種の方が美味しいという事になります。
美味しい野生動物の肉には更に上があり、アナグマの肉は「幻のジビエ」とか「地球上で一番美味しい肉」などと賞賛されているほど美味しいらしい。
鳥の肉に関しても、「狩猟界」という雑誌が行った狩猟鳥の美味さの順位付けをする企画で、トップに入ったのはカモ、キジ、ウズラ、コジュケイだったという話があります。それら狩猟鳥と比べると、鶏の肉は12位相当だったそうです。
また別の話として、ヒヨドリやツグミも特に美味しい野鳥として知られています。(尚、現行法ではツグミを獲るのは禁止)
つまり、品種改良されたものよりも美味しい野生動物は珍しくないわけです。
美味しい魚介類に至っては、品種改良されていないものばかりです。
ミオグロビンは酸素と結びついて赤くなる奴だろ。あれって牛にも豚にもあるし。
DNAしらべたってことなのか?
それはヘモグロビンだ
ミオグロビンは酸素と結びつくと赤ではなく茶色になる奴で、血液中ではなく、筋肉を構成している筋繊維の内、遅筋繊維の方の中に存在していて、筋肉が必要とする酸素を一時的に貯蔵する働きをしています。
酸素と結びついてもすぐにまた酸素を手放してしまうため、茶色になっているものは割合が少なく、そのため筋肉は(血抜きをしても)茶色が殆ど目立たず、酸素と結びついていないミオグロビンの色である赤色が支配的なのです。
2026/01/11 19:50:55に書き込んだ際には書き忘れてたけど、ヘモグロビンと同様にミオグロビンもまた牛にも豚にもあります。
しかしながらミオグロビンに限らず生物が持つタンパク質を合成するための遺伝子の配列は進化の過程で少しずつ変異し続けており、そのため進化論的に同じ起源を持ち、尚且つ同じ働きも持っているタンパク質であっても、生物種が異なればアミノ酸配列が多少異なる場合が多いわけです。
また、タンパク質以外の有機物に関しても、それもまた触媒作用を持つタンパク質である酵素を使った化学反応によって合成されていますから、複雑な分子構造を持つ物質の場合は、生物種の違いによって分子構造が多少違ってくる事も無いわけではありません。
ミオグロビンはヘムと呼ばれる有機物とタンパク質、それと鉄が結びついている有機物なので、人間のミオグロビンと人間以外の動物のミオグロビンとでは、アミノ酸配列を始めとした分子構造に若干の差異があると思われますから、排泄物の化石に含まれていたミオグロビンのアミノ酸配列を調べればそのミオグロビンがヒトのものなのかどうかが判るわけです。
尚、排泄物の中に食べた生物のDNAが含まれているという可能性はありますが、ミオグロビン自体にはDNAは含まれていません。
>人間の筋肉に存在するタンパク質「ミオグロビン」が検出された
とある以上、調べたのはミオグロビン自体であって、DNAを調べたわけではないと考えられます。
あと余談ですが、排泄物の化石の中に見つかったのが、もしミオグロビンではなく人間のDNAやヘモグロビンだった場合には、腸の新陳代謝のために腸内壁表面の細胞が垢のように流れ落ちたものや、胃潰瘍のような病変により消化管内で起きた出血による血液、等の“排泄した当人由来”のDNAやヘモグロビンが混入した可能性も考えられますので、必ずしも人肉食の証拠とはなりません。
人間も一種の哺乳類と考えたらね…
でも、決して食べたいとは思いませんが…
脳を食べずに火を通せば問題ないってこと?
プリオン病は中枢神経の疾病だから、脳はヤバいです
ハムスターの実験で感染した脳組織を600℃で灰にしてもまだ感染力があったようです
狂牛病は牛に肉骨粉を与え強制共喰いさせた事により広まった
病気や寄生虫、異常プリオンへの感染リスクを考えれば共喰いはデメリットが多い
霊長類ではチンパンジーは群れ同士の争いで相手の子猿を捕らえて群れ全員で共喰いする
この共喰いは単にタンパク源としてではなく、相手の群れに対するプレッシャーと自分たちの群れの結束を高める儀式的意味合いが強い
共食いを日常的に行うようになると種として絶滅するしかないので日常的に共食いをするようにはなりません。コメントにあるカマキリは交尾後にオスが食われる事がありますが、これはオスの体が子孫を残すための栄養となるのでオスにもメリットがあります。交尾後にオスが食われる例はクモなどでもありますが日常的に同種を狩って食べる生物はいないと思います。
ちょっと違う話だが
イスラム教で豚は不浄なので食べないのも似た理由と言えるかも
臓器移植できるくらい免疫的に人間に近いから
共通のウィルスとか寄生虫が多くてリスクが高い
君子は庖廚へ近づかず、厨房で屠殺された動物見たら食いたくなくなるから
動物だって食欲が失せかねないのに意思疎通が容易に出来る同族を好んで食うやつは居ないだろうなぁ・・・
論理無視しても、人間だったら食料より労働力の方が価値が高そうって考えると宗教的な理由以外は日常的に食べる目的にならなそうだ
コンセントとプラグが逆
ほんまそれな
一番の理由は、共感性などからくる抵抗感でしょ。当たり前だけど。
そういえない人は知性を持った社会性のある動物として欠落してるよ。
これもまたか、本当うんざり。クールーは免疫ある人なら感染者の脳を食っても死なない事をどの情報サイトも動画も番組も言わないの何なん。ケチュア族は砒素に免疫を持っていたり、雑食や肉食の動物は半分くらいが共食いする、それは共食い如きでは簡単に絶滅しない事を証明している。同種を主食として養殖してまで食ってたら不効率だけど必要に迫られたら食った方が良い。共食いしたら100%死ぬみたいなアホな二極的論法へ誘導しないで欲しい。この記事ではそこまでは言ってないし生地の共食いにはリスクがあるよという主張には同意するけどメリットがある事を言ってないのがダメ。
2018年の研究においてプリオンタンパクに対する自然免疫の獲得に関する論文が出ています(2018,石橋大輔)が、
プリオン病に対する抵抗があるのは、免疫がたまたま学習し抵抗する(自然免疫)からではなく、もとからプリオンタンパクの接触によって、畳み込み構造を変化させるためのスイッチとなる受容体が変異しているから、という理由でプリオンタンパクに対する抵抗がある人のほうが多いように思われます(クールー病の話題として挙がるフォレ族自身からも、別の個体からは非感染効果のある遺伝子変異が見つかっており、フォレ族の中には感染する人もしない人も混じっている、そしてこれは、一般的には免疫とは、みなされない。免疫には2種類あり、先天的な免疫とは、マクロファージやNK細胞などの、学習を必要としない免疫細胞らによる活動によって行われる免疫機能を指すが、ここに、遺伝子の変異に由来する機能を当てはめて考える例は少ない。ちなみに、この変異をもつ人は、ヤコブ病など他のよく知られるプリオン病に対しても抵抗力をしめすという興味深いことが知られている。特異性の高い免疫が、全く構造の異なる原体に対しても効力を示すことは、免疫として当てはめることを困難にする理由となる,2015,Emmanuel.A.Asanteら)。
ところで、先天か学習かに因らず、免疫が獲得されたのであればプリオンタンパクに対する抗体価が上がるはずですが、もとから感染しないのであれば抗体価は上がらないか、限定的である可能性があると考えます。ただし、どちらの経路が理由で、そのプリオン病への感染を防止しているかの割合を調査した研究や論文は、例がないように思われますが、だれかご存じの方いますか。
話は反れましたが、自身が既知のプリオン病に対して抵抗があり、また、他の、捕食対象となる人物が保有している病原体に対する免疫によって未然にカバーされているのであれば、食人を行うべきではない3番目のリスクは取り除かれます(加熱調理などによって安全性を高めることももちろん可能である、ただしプリオンタンパクは加熱に強いため、完全にタンパク質の構造が破壊されるような、ウェルダンを超える程度の加熱が必要である)。タンパク源は食品としての生産コストが高いため、環境負荷を減らすためにも、人肉を食料として有効活用する方法の模索が望まれるため、このメリットの得るために、プリオン病とそれへの感染抵抗について正しい理解が広まる必要があることでしょう。
ヤフ知恵袋より役に立った。1000000コインみたい。知らなんだ
前の文長過ぎ
でも病気てクール―病だけじゃなくない。何か他にもやべえのが出てきそう。
共食いしている生き物ってどういう気持ちで食べてるのかな?気になる〜
関係無いけど「ソイレントグリーン」をまたみたくなった。
脳と脊髄からも感染するから知らなければ避けるのは不可能
タイトルが「食べてはいけない理由」なのに、理由①②が、人間が慣習的に人を「食べない理由」なので趣旨が違う。
また、感染症リスクを回避できれば人肉食は可能という意味では、倫理や宗教同様、絶対に食べてはいけない理由にはならない。
なので、冒頭の「倫理的に駄目だ」という説明と、同レベルの説明しかできていない。
人間の歴史ってわりと殺し合いなの考えると、殺してもいいとされる理由はたくさんあるのに、食べるのはダメなのも意味不明ではある…。
ただし、そもそも集団レベルの殺し合いのメリットって土地や物や権力や地位の獲得ももちろんあるけど、基本的には奴隷の獲得だと思うと、栽培を社会の基礎と考えた時、捕えた敵方の人間を肉にするより、栽培のための奴隷として利用したほうが儲かるんだよね。これ、奪った土地で鉱山掘らせるのでも同じ。少ない飯で死ぬまで働かせたほうが富になる。
どんなリスクがあってもそれを上回るベネフィットがあれば余裕でやるのが人間なので、単純においしくないのだと思います。
少なくとも万人受けする味ではないのでしょう。
結局これ
フグでもこんにゃくでも、おそらく何人も死にながら何人も腹痛にあいながら何度もトライ&エラーで必死に食ってきただろうに、人間食べないのは、きっとうまくないんだわ
必死になる理由がないんだわ
人体一つの総カロリーが12万〜14万kcalで、これが25人の成人男性が半日もつかどうかの栄養しか得られない数字だとすると、12万kcal÷25人=4800kcalが半日分。1日当たり9600kcalは取り過ぎじゃない?
成人のヒトの1日のエネルギー消費は2500キロカロリー程度。12万キロカロリーあれば約50人の1日の消費エネルギーに相当する。
「25人の成人男性が半日もつかどうかの栄養しか得られない数字」というのは明らかに間違っている。
2500キロカロリー程度というのは現代人の話。
獲物を探して1日中のやまを歩き回り、獲物を見つけたら自分たちよりも脚の速い相手が疲れ切って走れなくなるまで追いかけ続けて仕留めていた狩猟採集時代の人間なら到底その程度では済まない。
脳食べるとヤコブ病になるからね
なんか食べたらダメな理由が全てクリアされたら食べるのか?という質問に対しての答えはどうなるのだろう?
僕はそれでも食べられない。
心理的な何かが強烈にブレーキをかける。
それは、たぶん「人を食べた時点で自分も人ではなく食料であることを自覚するのが嫌だから」なのかもしれない。
それだわ ありがとう納得した
「何故人間は、人間を食べる事に対してそんな強烈なブレーキがかかるような心理構造を持つように進化したのか?」という事の理由が、記事に挙げている3つの理由という事なのでは?
群れで生きる動物が日常的にカニバったら、簡単に絶滅するじゃないですか。
カニバらない性質と群れをつくる性質を同時に獲得しないと群れをつくるようには進化できないですよね。
群れをつくっているのに絶滅していないということは、カニバらないということですよ。
つまり、なぜ人間は日常的にカニバらないのか?の答えは、日常的にカニバった奴らから絶滅し淘汰されたからでしょう。
食べるものがなくなれば共食いするというのは人間に限った話ではないし。
人間が日常的にカニバらないのはプリオンと直接関係ないでしょう。
むしろ、儀式的な人肉食がなぜ行われていたのか、儀式的な人肉食に何のメリットがあるのか、ちゃんと説明して欲しい。
古代中国の居酒屋メニューには、赤子(男女)、子供(男女)、女性とありましたよ。
戦争の捕虜の脳以外の部位をしっかり加熱して食べる場合は3つの理由がどれも制限にならない。結局、科学というより、倫理なんだと思う。タンパク源としては栄養価は高いはず。
古代中国の居酒屋では人肉は当たり前に赤子、子供、女性とメニューにあったし、奴隷は冬の非常食の役割も果たしていたよ。
この3つの理由はとても素晴らしい内容で、大勢の人間が頭にインプットした方がいいと思います。これにより より良い社会になっていくでしょう。
古代というか中国では現在でも地域によって人肉食はありますよ。
詰物等保存食にするのが主流だそうですが…。
❤️
乳児幼児を食べようとすれば保護者から攻撃、または報復される可能性があり、それも含めてコストが高すぎるのではないか、と思われる。
わざわざ殺してまでは食べなくても、死んでいる者なら食べても良いような気がする。飛行機事故や戦時の飢餓状態時に、食人を拒否し亡くなった話しも聞くし、食い意地の張った俺なら、その人に感謝しながら食うと思う、それが原因で死んでも、それは仕方ない、コスパの問題ではない、自己責任だ。
中国の話は何故か無視されているけど、確か、三国志演義でも、客をもてなす料理に自分の子供を料理するなんて話があったけどそれが一番の親孝行だそうだ。
南米の旅客機事故では事故で死んだ人達の肉を食べて山岳地帯の冬を生き延びた話がありましたね。生きるか死ぬかの切羽詰まった状況なら、誰だって生き延びる為に人肉だってウジ虫だって食べますよね?
霊長類って人間も含めてあまり大きな動物がいないから食用にするには不向きですね。日本にもサルは居るがサルはあまり食べない、基本イノシシ、シカですね。サルは、すばしこくて利口だから狩るには骨がおれるし、味は酸味があって不味いらしい。
古代中国の居酒屋の話、現在でもある人肉食の話し
詳しく教えて下さい
中国は現代でも日本の政財界のVIPのおもてなしパーティーで
でっかい船で法律のうやむやな海域に移動し
豪華な中華料理が出て
最後のデザートはテーブルに巨大な赤子インゼリーが出て来る
日本のVIPをビビらせるためと言われていますが
最大のおもてなしのおめでたい料理として現地人は拍手する流れ
信じるか信じないかはおまかせですが
昔は日本も多産だった(七五三迎えられず死ぬ子が多かったから)
避妊の知識も乏しく中絶の技術も無いので産んでから産婆がシメる
間引きが普通 7歳まではほぼ人権も無いので罪にならない
赤子の命はとても軽かった
日本は明治以降徐々に変わっていったが
中国は一人っ子政策前までは赤子は余ってたと言える
日常的に死者を食べていた種族なのに、なぜこれらの病気が急増するの?別の原因では?
正直気持ち悪いと思う、それでもなぜ食べるのか考えると、結局仕方がないからと思われる、理由をつけて理解しようと思っても忌避感は無くならないよね。吸血鬼やグールなどのモンスター扱いされて敵対攻撃されるのが最大のデメリットじゃないかな、クマと一緒。
以前、母から「昔、おじいちゃん家の蔵に、第2次世界大戦中のソ連で人肉を食べてたって写真がいっぱいあったよ」って話しを聞いたことがあります。
母は「歴史的に価値があるものだから残しておこう」と主張したらしいけど。
嫁いできた長男の嫁が「気持ち悪い」と言って焼却したらしい。
見たかったなぁ。
復讐心を持つ、かつ強く持つ動物に安易に狩猟の手を出さない人間の心理を考えると、安全コストの理由が一番納得できる。
同じ集団の中でも不安を抱えながら「食うか食われるか」の心配はきりがなくなる。精神的不安コストも決して無視できない。
人をカルには必ず体に負荷がかかるわけで普通に鹿などを狩った方が効率的だということは確かに一理ありますね
シンプルに生産性悪いからだよね…
多産じゃないし、10ヶ月待ってやっと産まれてそこからある程度になるまで育てるとして年単位でしょ。ほかの多産の家畜食べた方がいいよなって当然なったんだと思う。
部族の話はあくまで死んだ人間食ってたってことだし。
40ほど食べましたが、コスパ悪いです。肉は固いし美味しくないし追っては増えるしそこらのうさぎの方がマシでした。
あなたの肉は違うのかしら。
悪いのはコスト面、生産性、成長させて出荷するまでの時間、幼児から食べるとなると豚や牛と比べてサイズが小さい。
味は豚に似てるので決して悪い味では無いが感染のリスクがある
カマキリがコメントにあったけど産卵後に死ぬ一生に一度のカニバなので食文化としてカウントするのはおかしい
映画で、「ゾンビが人肉を喰らう」とおうコンセプトが発明されて、イタリア、イギリス、日本などで爆発的にゾンビ映画が生産・上映されてきました。国を超えて、現代の人々には人肉食への関心があるように感じます。この記事へのコメント数の多さや、記事自体が再掲されるのも、現代の日本人の関心の関心の高さなんでしょう。
戦前から今にたるまで流行っているドラキュラ映画も、人肉食への誘惑に近いものを感じます。
ゾンビやドラキュラは人間の心を失った怪物に過ぎず、それらが人間を襲うのは、人間が同族である人間を食べるのとは全く異なる事態なので、人肉食とは全く無関係な話に過ぎません。
ゾンビ映画が生産・上映されてきた事を理由に現代の人々には人肉食への関心があると見做すのは、クマやサメ、その他の猛獣、怪獣・怪物等々が人間を食う作品が生産されてきた事を人肉食への関心の高さの現れだと主張しているようなものです。
ゴーレムではなく、知識と知的能力の高い犯罪精神医学者ハンニバル・レクターを主人公とした「羊たちの沈黙」「ハンニバル」も世界的に興行的に成功しました。
タブーとなることを冒す怖いもの見たさな欲求なのか、(痴ほう症患者でしばしばみられる異食症のように)理性で押さえつけらていた根源的欲求なのか気になります。
映画最後の機内で子どもに人肉食を勧める場面はショッキングでした。昔話かちかち山でも「タヌキがおばあさんを鍋にしておじいさんに食べさせる」くだりがあります。子どもの提示する物語としては過激に感じますが、物語として長らく受け入れられてきたきたには、理由があるかもしれません
ハンニバル・レクターの話に話題がすり替わってるけど、ゾンビやドラキュラの映画の話じゃなかったの?
ハンニバル・レクターのシリーズが興行的に成功したとは言っても、ゾンビものや吸血鬼もののような爆発的なヒットをして同形式の別作品が量産されたものと比べれば、少数“派”にも満たない僅かな数の作品が制作されただけです。
ハンニバル・レクターなど比べものにならないほど多数制作されたゾンビものや吸血鬼ものにしても、戦争ものや恋愛もの、ガンアクション、格闘技もの、スーパーヒーローもの等々のメジャーな分野の作品と比べれば少数派に過ぎません。
制作された作品数の圧倒的な違いは、一般的な人々にとって、人肉食に対する関心がそれほど高いものではないという事を示しているように感じられます。
尚、かちかち山の話において、おじいさんがおばあさんの肉を食べたのは、タヌキに騙されて「タヌキの肉だと思って」食べてしまっただけであり、「人間の肉として食べた」というわけではないのですから、カニバリズムに対する興味とは無関係な話であり、例として挙げるのは間違っています。
>2つ目は「人肉の栄養価が低いこと」です。
>研究チームは「食人族が体重55キロの男性を食料にした場合に得られるカロリー量」を試算したのです。
>人体一つの総カロリー量は約12万〜14万キロカロリーになると算出しました。
>一見するとすごい高カロリーにも聞こえますが、実はこれは25人の成人男性が半日もつかどうかの栄養しか得られない数字なのです。
>毎日の栄養を効率的に摂る上で食人行為はまったく向いていません。
とあるけど、その論でいけば、55キロというのはニホンジカの体重と同程度だからニホンジカも狩猟の獲物として全く向いていないという事になる。
ウサギや大部分の鳥類、海の沿岸部や河川・湖で獲れる魚の大部分などに至っては話にならないという事になる。
貝や木の実の一個あたりのカロリーが人間一人分を上回るとは到底思えない。
それにもかかわらず、人類は有史以前より鹿やウサギ、鳥、魚、貝、木の実等々、一つあたりのカロリーが人間一人分よりも少ないものであっても食糧としてきた。
従って、記事にある2つ目の理由は、人が人を食べない理由にはなり得ないと考えられます。
昔のコンゴでは人肉がヤギ肉と同じように食されていたってWikipediaで見たぞ。
正直古い文献ばかりで現代における信用できる根拠とは扱われないが。
そもそもキリスト教化で人肉食が軒並み廃れて現代まで続いている人肉食文化が存在していない。
人間がどういう種族か、同じ人間を家畜と同じように食ってしまう種族なのかを知るうえで古い文献を研究することは大事だと思う。
ファンタジーでミノタウロス族が同族を捕まえて食料として人間族に売りつける牛身売買は商売コスト的には優秀だが人間族しかいない現実では人間が人間を食うよりも奴隷として働かせた方がコスト良くて社畜って言葉は良く出来てるなと思った
リスクとリターンが見合ってない
そんな事ないよ。その分美味しいから
少なくとも大半の現代人はおいしくはないだろうなケミカル臭くて
鳥葬のある地域でハゲワシ?だかも食べ残すか食わないんで、処理に困ってる話をだいぶ昔読んだな
残さず食べて貰えないとあの世に行けない的な思想なのに残されるんで、他の生き物の肉に包んでみたり仕方なく焼いたりしてるとか