寄生バチが語る失われた捕獲戦略
今回の化石寄生バチ(Sirenobethylus charybdis)が見せる“おしりで獲物を挟む”戦略は、現生の寄生バチでも報告がありません。
一般的には前脚や顎を使ってホストを制圧したり、麻痺毒で動きを止めたりするのが寄生バチの定番ですが、腹の先端を丸ごと捕獲器に変えてしまうという発想は、まったく別の進化の道筋を示しています。
また、開閉を可能にする筋肉の痕跡や、長い毛(トリガーヘア)によって瞬時にスイッチが入る仕組みがすでに白亜紀に完成していた点も驚きです。
なぜここまで特殊な器官が進化したのかは、相手となる獲物や生息環境の影響が大きかったと考えられます。
現代のドライニッドバチがはさみ状の前脚で素早くヨコバイを捕らえるように、この化石バチはおしりで静かに待ち伏せし、獲物が接近した瞬間にパチンと挟む“待ち伏せ型”だった可能性が高いのです。
白亜紀は、花粉を運ぶ昆虫の登場や被子植物(花をもつ植物)の多様化など、大きな変革期に当たります。その激動の時代にあって、昆虫同士の攻防や共進化が予想以上のペースで進んでいたのかもしれません。
実際、サーベルのような大顎をもつ絶滅アリや、カマキリのように変化した前脚をもつ昆虫の化石など、現生にはない形態が次々と見つかっています。
今回の発見は、寄生バチの多様性が白亜紀にすでに非常に高かったことを示すだけでなく、“ホストをどうやって immobilize(動きを封じる)するか”という寄生バチにとっての大きな課題に対し、かつて存在したまったく新しい解決策を具体的に見せてくれました。
現代の昆虫たちの姿は、長い進化の歴史のなかで残った戦略の一部にすぎず、かつては多様な捕獲方法が試されていた可能性があります。化石は、私たちが想像すらしなかった“失われた進化の枝”を教えてくれる貴重な証拠。
こうした多彩な捕獲パターンを再発見していくことで、今後は昆虫進化の流れをさらに深く理解できるかもしれません。






























![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
















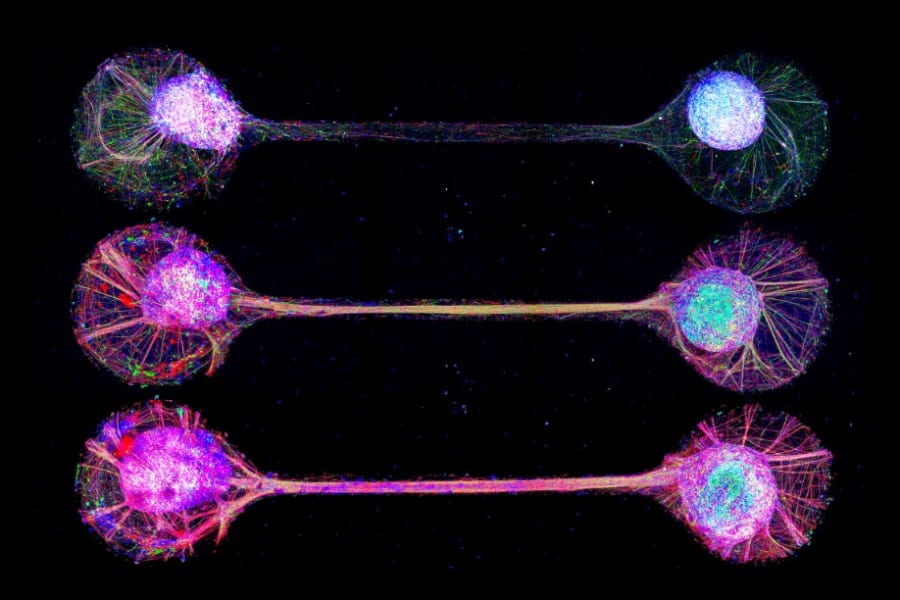




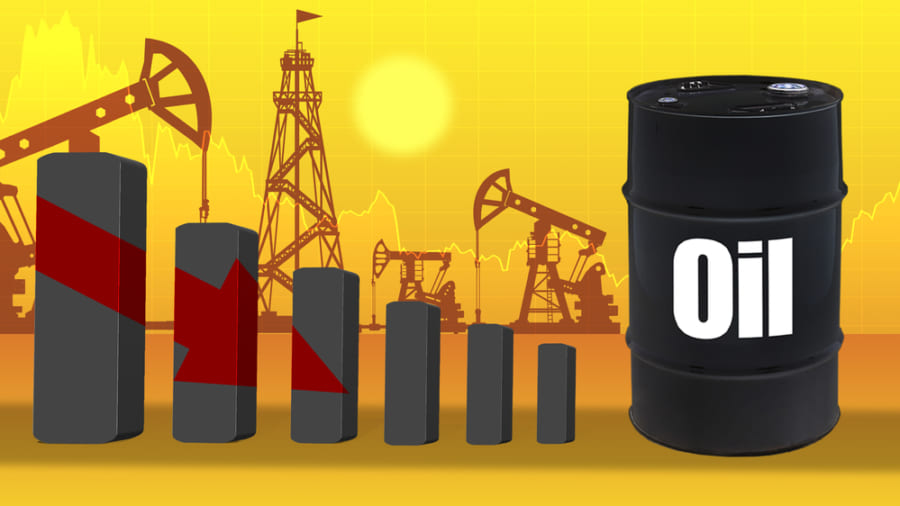






興味深いので原著論文にも目を通してみました。記事には書かれていませんが、現生種の無い新科新属新種の寄生バチです。科名からみるとアリガタバチ科に近縁なのかと思ってしまいましたが、原著論文での系統解析を見る限り、特にアリガタバチ科と近縁ではないようです。寄主がどんな昆虫なのか気になるところですが、原著ではカマバチと同じくヨコバイやウンカの可能性があると考察しています。でもヨコバイやウンカの行動からすると、ハエトリソウのようなトラップにかかるのかな、とも思ってします。あと翻訳の問題ですが、ドライニッドバチ(Dryinidae)はカマバチ科、トラップジョーアントはアギトアリですね。