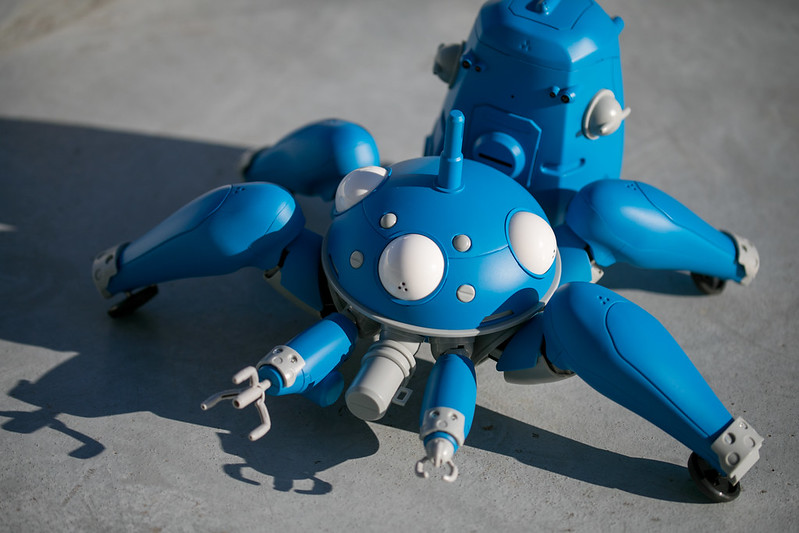子どもを望む時間すら奪われる労働漬けの生活

研究チームは、中国家族追跡調査(CFPS)の2020年版データを活用し、約2万人のサンプルを分析対象としました。
CFPSは年齢・性別・年収・健康状態・家族構成といった多方面の情報を集めているため、「労働時間」と「子どもを持ちたい意欲」が他の要因とどのように関連するかを詳細に検証できます。
さらに、省や都市ごとの地域差も視野に入れながら、“週40時間超”の残業が出生意思に与える影響を調べました。
研究デザインのユニークなポイントは、単に「労働時間」だけでなく、夜勤・週末勤務・オンコール(24時間連絡が取れる状態)など働き方の違いを細かく分類したことです。
夜勤による生活リズムの崩れ、週末勤務で失われる家族との時間、オンコール勤務の精神的ストレス──これらがどの程度、子どもを持つ意欲を下げる要因になっているのかを一括して分析したのです。
すると、労働時間をより細かく区切り、週20時間未満の場合はむしろ出生意欲が高い傾向があることが示されました。
一方で週40時間を超えると明確にマイナス効果が強まり、とくに40〜50時間労働のグループで出生意欲が最も急激に低下していることがわかります。
60時間以上の過重労働では個人差がやや大きくなるものの、全体としてはやはりマイナスの効果が強いようです。
興味深いのは、夜勤・週末勤務・オンコールといった「いつでも仕事モード」に近い人々ほど子どもを持ちたいと思う割合がさらに少なくなる点です。
具体的には、週0~20時間の労働にとどまっている人々(パートタイムや特定のフレキシブル勤務など)では、およそ65%が「2年以内に子どもを持ちたい」と回答しています。一方、週20~40時間のいわゆるフルタイム基準内の労働をしている人では、約50%が同様に「子どもを持つ予定がある」と答えました。
しかし、週40~50時間になると出生意欲は32%まで大幅に低下し、週50~60時間の残業が多い層では25%へとさらに落ち込みます。研究チームによれば、40時間を超えた時点から精神的・体力的負担が急増し、パートナーとの時間や自己啓発に費やす余裕が一気に減ってしまうことが原因の一つとしています。さらに、週60時間以上の過重労働に及ぶ層では、回答者全体の平均こそ22%となっていますが、個人差が大きく、中には「家庭を持つ気力がほとんどない」と答えた事例も散見されたということです。
勤務形態の違いも顕著でした。夜勤や週末勤務、オンコール勤務の経験が「頻繁にある」と答えた人のうち、「2年以内に子どもを持ちたい」とする割合は20%前後とさらに低下します。逆に、フレックス制度の活用が可能な職場やリモートワークが普及している職場では、この数字が35~40%程度にまで回復していることも分かりました。
研究チームは「長時間労働や不規則勤務の多い環境ほど、出産や育児に対して慎重になる傾向が明らかになった。特に週40時間を超えると、心理的負担と時間不足が本格的に出生意欲を下げるようだ」と指摘しています。
さらに、女性の方が男性より残業に対して敏感に反応するという傾向も見られました。
中国でも「子育ては女性が担う」という社会的プレッシャーが根強いため、長時間労働が女性に及ぼす影響はより大きいと考えられます。
また、結婚していない人ほど「これから家族を持つかどうか」を決める段階で長時間労働を理由に躊躇する可能性が高くなる点も印象的でした。
動物においても、厳しい環境下でのストレスが出生率に深く影響を与えることは多くの研究で示されています。
たとえば、エサの不足や気候変動、捕食者の増加などによって動物が慢性的なストレスを感じると、生殖行動そのものが抑制される場合があります。
これは、体力を温存して生存を優先するためにホルモンバランスが変化し、交尾や繁殖に向かうエネルギーが減ってしまうからだと考えられています。
実際に、野生生物の生息環境が損なわれた地域や、家畜でも飼育条件が悪化した場合に、繁殖率が顕著に落ちる例が数多く報告されています。
こうした現象は、人間における長時間労働や不規則勤務が出生意欲を下げる仕組みにも通じる部分があり、「厳しい環境=生殖コストの回避」という生物学的な傾向が、種を問わず存在するといえるでしょう。
なぜこの研究が革新的といえるのか?
第一に、中国全土をカバーする大規模かつ多様なデータに基づき、労働時間だけでなく勤務形態の細分化まで踏み込んでいることが挙げられます。第二に、「20時間未満で出生意欲が上がり、40時間を超えると大幅に下がる」という具体的な労働時間の区切りまで示している点は、今後の少子化対策や働き方改革を考えるうえで大きなヒントとなるでしょう。これらの包括的かつ多角的なアプローチは、中国のみならず世界的な少子化対策にも影響を与える可能性があります。


























![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)