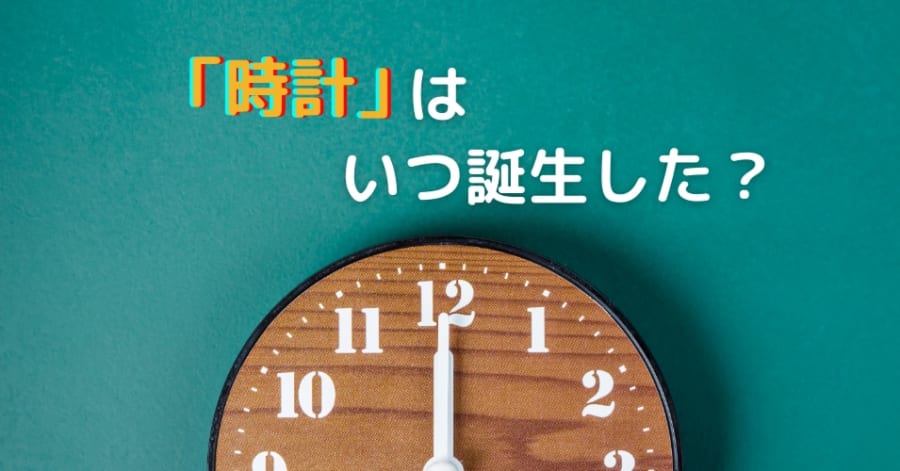拡大自殺とは何か:その概念と歴史

拡大自殺とは大まかに言えば、殺人を行った後(または同時に)自殺する行為を指します。
犯人が自分の自殺に他者を(相手の同意なく)巻き込むため、英語では「extended suicide(拡大された自殺)」とも呼ばれます。
要するに、自分一人で死ぬのではなく、他者を道連れにして死のうとする行動です。
精神医学の用語であり、診断名というより現象の名前として1990年代から欧米で使われ始めました。
中でも最も際立っているのは、アメリカで頻発する銃乱射事件(マス・シューティング)のなかにみられます。
多くの銃乱射犯が犯行後に自殺したり、警察に射殺されるケースが多いからです。
研究によれば、公開銃乱射事件の加害者の約半数は犯行に自殺念慮が結び付いています。
こうした犯人たちは犯行そのものを“死に場所”として選び、「栄光の炎の中で死ぬ」と語った例もあります。
「自分一人で死ぬのは馬鹿馬鹿しい。どうせなら大勢巻き添えにしてやる」「死にきれないから死刑になりたい」という心理が垣間見える場合もあり、動機は利他的というより復讐的・攻撃的です。
日本の無差別殺傷事件でも、「複数の人を殺せば死刑になると思った」と自供した例や、「一番手っ取り早く他人に殺してもらえる方法として人を殺した」という例が報告されています。
他にも典型的な拡大自殺にはいくつかパターンがあります。
ひとつは家族や親しい人を巻き添えにするタイプで、いわゆる無理心中(例えば親が子を殺して自殺するケース)も広い意味で含まれます。
犯人自身が「自分が死んだ後に残される家族がかわいそうだ」「この人を一人残しておけない」といった偽りの利他的動機を語ることもあります。
このように、拡大自殺は一言で言っても動機の種類や対象の選び方によって様々な形態があり得ます。
そのため厳密な定義や分類には議論もありますが、今回は「他者を殺めた後に自死する行為全般」にフォーカスしていきます。





























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)