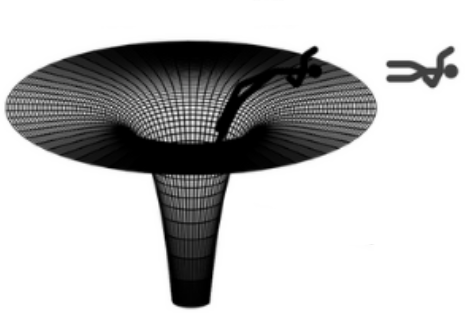ADHDと診断されると、ファストフードの消費量が増加
ADHDは、不安定な集中力や落ち着きのなさ、思いつきで行動してしまう衝動性などを特徴とする発達障害の一つです。
その多くは12歳以前の小児期に発覚することが多いですが、大人になってからでもADHDと診断される人は少なくありません。
ADHDについては常に多くの研究がなされており、これまでの研究では、ADHDのある子供が学校での集中力に欠けたり、対人関係でトラブルを起こしやすいことが知られていました。
その一方で、小児期に診断されたADHDが「運動」や「食習慣」といった長期的な健康行動に及ぼす影響についてはあまり明らかになっていません。
そこで研究チームは今回、ADHDと診断された子供が成人後に、どのような食習慣・運動習慣にあるかを調査しました。
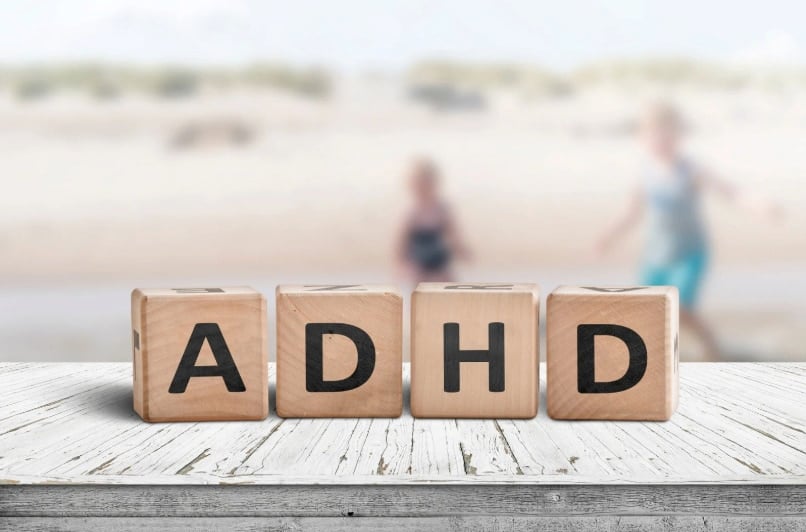
研究者らは、アメリカの青少年を長期間にわたって追跡した大規模な全国調査から、6814人のデータを使用しました。
ADHDの症状については、参加者が成人初期に達した段階で、自身の5歳から12歳までの行動を回顧的に報告することで評価されています。
ファストフードの摂取頻度や身体活動の状況は、思春期および成人初期において標準化されたアンケートで測定されました。
ファストフードの摂取については、参加者が過去1週間にファストフード店でどれくらい食事をしたかを報告し、思春期では週3回以上、成人初期では週4回以上の利用が「高頻度の摂取」と定義されました。
身体活動については、スポーツや運動などの中〜高強度の活動を前週に何回行ったかを尋ね、米国の健康ガイドラインに基づいて「運動不足かどうか」を判定しています。
年齢、性別、人種、家計所得、肥満、うつ状態、近隣環境といった他の因子を調整したうえで分析。
その結果、幼少期にADHDと診断されていた参加者は、成人後におけるファストフード摂取の増加と有意に関連していることが判明したのです。
具体的には、ADHDの既往歴がある人は、そうでない人と比べてファストフードを高頻度で摂取する確率が49%高くなっていました。
この関連は思春期には見られず、若者が自立し食事の選択権を持つようになる成人初期に顕著になることが示唆されました。
一方で、幼少期のADHDと思春期および成人期における運動不足との間に有意な関連は見られませんでした。




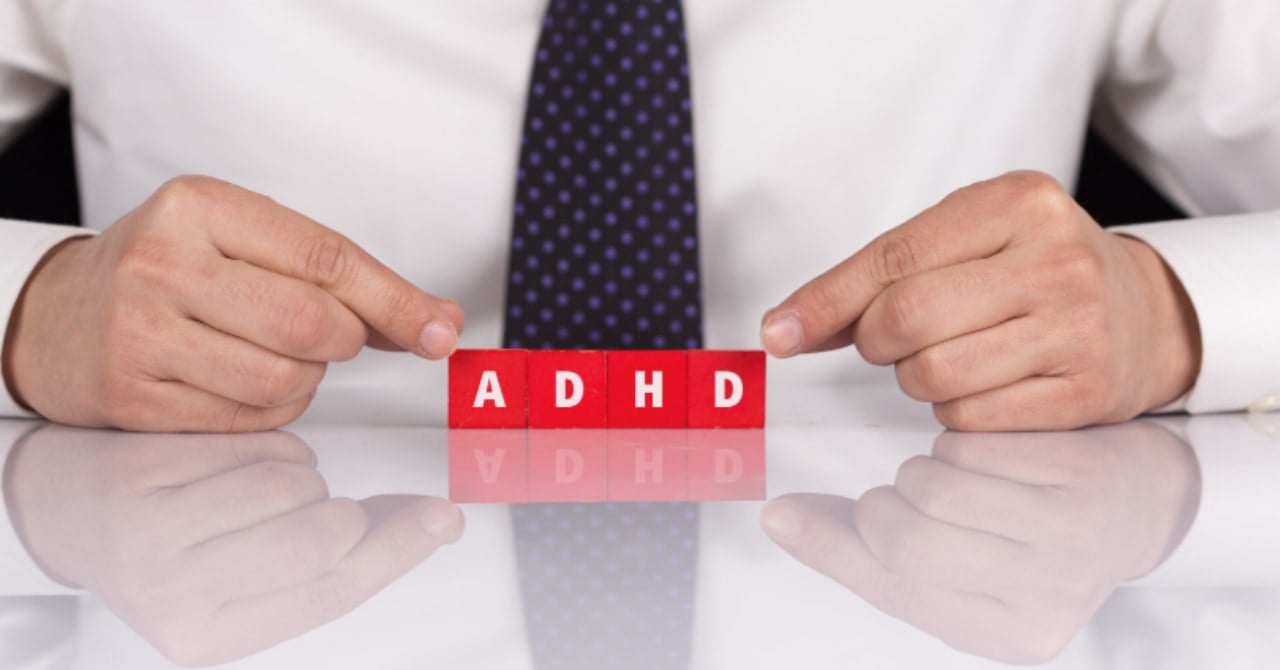


























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)