「木べら」効果がすぐになくなる理由と確実な対策
乾いたスポンジが空気を通し、濡れると孔がふさがれるのと同じように、木べらも乾いた状態では孔が有効に働きます。
しかし孔に水分や粘性成分が入り込んでふさがれると、その表面は、泡をはじけさせるほど多孔質ではなくなります。
また、木べら自体が熱せられると、表面温度を下げることもできなくなります。
木べらを鍋の上にずっと置いておくなら効果はありませんし、たとえ一時期効果を発揮しても、それがずっと続くわけでもありません。
「試してみたけれど効果を感じられなかった」という主張の背後には、こうした理由があるのです。

木べらトリックはあくまで時間稼ぎにすぎません。
では、より確実に吹きこぼれを防ぎたい場合は、どうすべきでしょうか。
こまめにかき混ぜることや大きめの鍋を使用すること、火力を調整して中火から弱火でじっくり加熱すること、そして目を離さずに調理を監視することをおすすめします。
当たり前のことですが、これらを習慣にすることで、キッチンでのストレスを大幅に減らせます。
もし、木べらを手に持っている状況で、吹きこぼれそうになった鍋が目に入るなら、すぐさまその木べらを鍋の上に置いてください。
応急処置としては役立つことでしょう。




























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)


















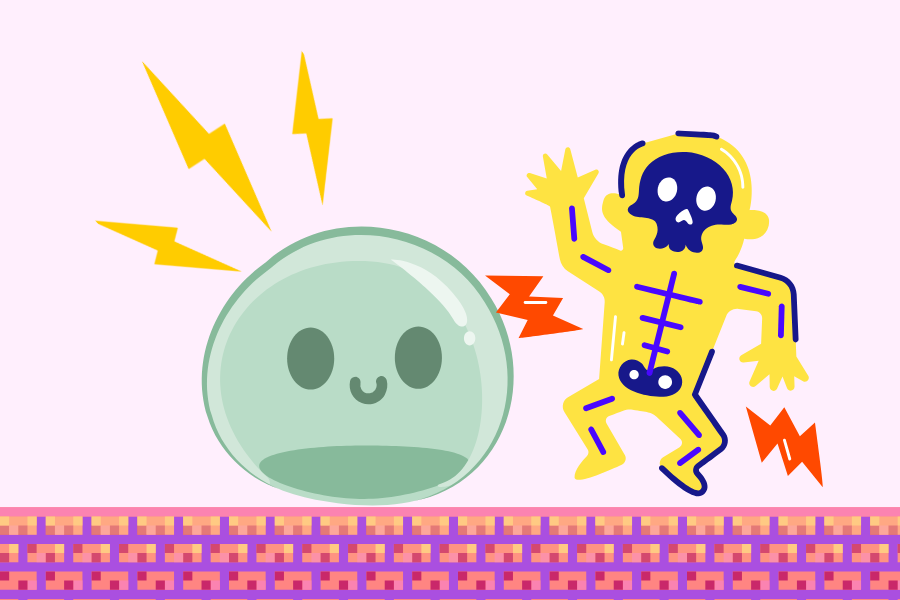









茹で汁に油を混ぜるとか色々あるけどみんななんでそんなに強火で茹でたがるのか。泡を生じさせるのはグルテンを無駄に流出させて金を捨ててるようなもの。90度くらいで茹でた方が吹きこぼれも栄養流出も無くて良いのに。和食に少ない水溶性繊維も溶け出してるから麺の茹で汁は飲んだ方が良い。インスタント麺だと麺を覆ってる酸化油は捨てた方が良いとも言われるけどパスタならそこは関係無い。
低い温度だと茹でむらができたりして
提供できなかったりするんよね
ケータリングで出すときいちいち全部チェック出来んから
手元になにもない時は泡に向かってフッと息を吹きかければ火を弱めるまでの時間が稼げる
100円ショップのアレじゃだめかい?
時点は落とし蓋
うちわであおげばいい。
自分用なら息かけても良いけど、表面温度変えるばら新鮮な空気送るのが一番有効。
手であおぐだけでも結構違う。