・コーヒーを1日2杯、30年飲み続けると、睡眠サイクルに悪影響を与える可能性がある
・コーヒーを多量に摂取してきた人の脳の「松果体」は、めったに飲まない人と比べて20%縮小していた
・松果体は体内時計を調整するホルモン「メラトニン」を分泌する器官であり、その縮小によって睡眠に悪影響が及ぶことが考えられる
「モーニング・コーヒー」や「食後のコーヒー」を習慣にしている人にとっては、少し恐ろしいニュースが舞い込んできました。
ソウル大学が実施した研究により、コーヒーの日常的な摂取が脳の特定の部位を縮小させ、数十年先には規則正しい睡眠を困難にさせる可能性があることがわかりました。
https://academic.oup.com/sleep/advance-article-abstract/doi/10.1093/sleep/zsy127/5053876?redirectedFrom=fulltext
基準となるコーヒーの量は、1日2杯を30年以上。脳内スキャンを用いた研究により、基準を超える量のコーヒーを飲む人は、めったにコーヒーを飲まない人と比べて脳の「松果体」が縮小していることが判明したのです。
間脳の一部である松果体はグリーンピースほどの大きさであり、体内時計を調整する「メラトニン」と呼ばれるホルモンを分泌することで知られています。つまり、松果体が小さいほど、分泌されるメラトニンの量も少なくなってしまいます。
これは、手軽な「興奮剤」として知られる「カフェイン」の、脳に対する長期的な効果を示した初めての研究です。162人の健康な年配者に対して、これまでどの程度コーヒーを飲んできたのかと、睡眠の状況はどうだったのかを質問しました。松果体の大きさについては、脳のMRIスキャンによって測定されました。
調査の結果「コーヒー愛飲者」の松果体は、コーヒーを飲まない人のものと比べて20%小さく、睡眠に関しても何らかの問題を経験していたことがわかりました。
この結果から研究者たちは、日常的なコーヒーの摂取が「人生の後半」において睡眠の質を害してしまう可能性があることを示唆しています。そしてこれに基づき、長年にわたる多量のコーヒーの摂取に対して警鐘を鳴らす研究者たちですが、この研究に対して「疑問の声」を投げかける専門家もいます。
睡眠に関する研究を36年以上にわたって実施してきたニール・スタンリー博士は、この研究の不十分な点を指摘します。「コーヒーによってカフェインの量は異なります。また、コーヒーではない別のものから長年にわたってカフェインが摂取された可能性もあります。この研究ではその点が考慮されていません」
スタンリー博士が指摘するように、これが「晩年の睡眠障害」と「コーヒーの摂取」を直接的に結びつけることに成功した研究とは言えなさそうです。しかし、もしこれが事実であれば「コーヒー・ラバー」にとってはショッキングな内容。この先さらに一歩踏み込んだ、詳細な研究が期待されます。
https://nazology.kusuguru.co.jp/archives/9420










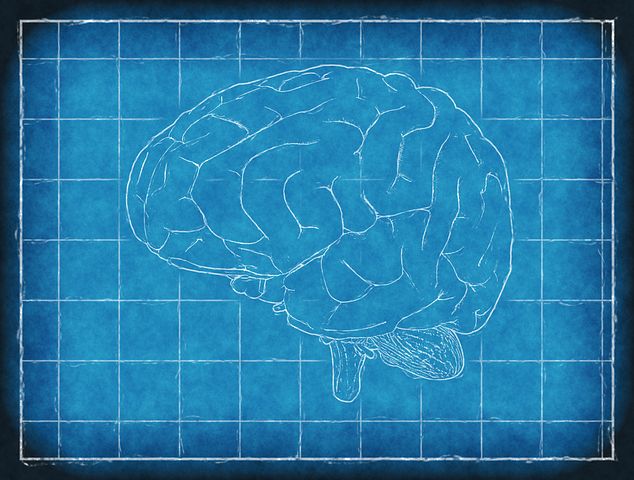






















![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)



























