DNAにも刻まれていた「乱獲の爪あと」
さらに驚くべきことに、こうした体の変化はただの“環境の影響”ではなく、タラのゲノム(DNA)にまで変化が起きていたことが突き止められました。
チームは、過去25年間に捕獲されたタラのDNAを網羅的に解析。
その結果、成長に関わる遺伝子の一部に、明らかな「方向性のある変化(進化)」が起きていたのです。
具体的には、タラの成長に関与すると考えられる336個の遺伝子領域で、ある遺伝子型が他よりも多く残る傾向が見られました。
これはつまり、「大きくゆっくり育つ」タラは漁で早々に捕まってしまい、「小さくても早く成熟する」個体だけが生き延びて子孫を残す――という自然選択ならぬ“人間選択”が起きていたことを意味します。

これまで進化は数千年、数万年という時間スケールで起きると考えられてきましたが、今回の研究は、たった四半世紀ほどの乱獲が、野生魚の遺伝子を根本から変えてしまったことを示す衝撃的な証拠です。
しかもこの変化は、単に小型化するだけでなく、成長に必要な代謝やホルモン、卵の浮力調節といった機能に関わる遺伝子にも影響を及ぼしていました。
環境の変化(たとえば水温上昇や酸素不足)ももちろん影響していますが、それだけではここまでの変化は説明できないと研究者は言います。
事実、過去25年で海水温の上昇によるサイズ減少は理論上6%程度と予測されていましたが、今回のタラの縮小は48%という、まさに「進化的変化」です。
2019年から東部バルト海のタラ漁は全面禁止となりました。
しかし、いまだにタラの体サイズの回復は確認されていません。
これは人間の手で急速に引き起こされた進化を元に戻すには非常に長い時間がかかることを示唆しています。
タラがもとの大きさに戻るには何世代もの自然な繁殖を待たねばならないかもしれません。













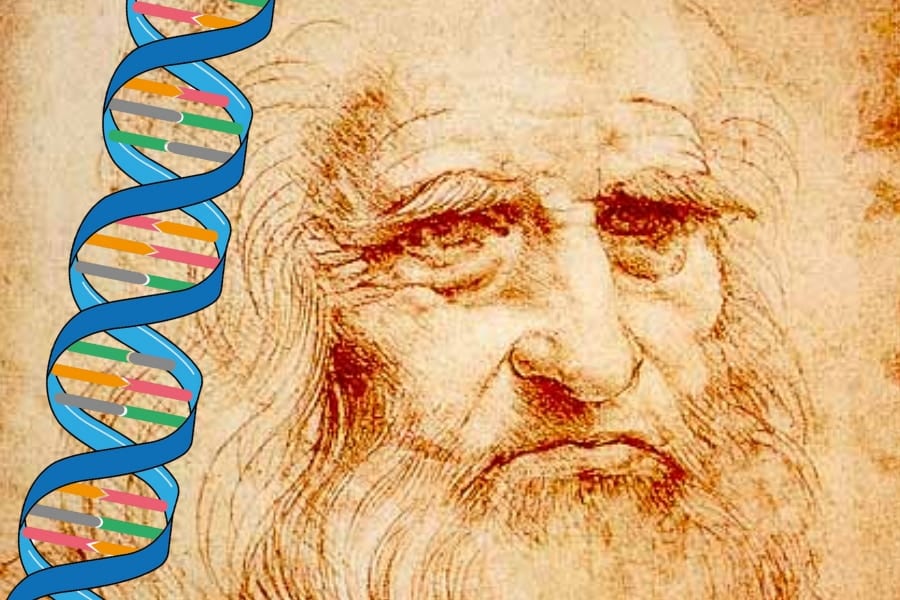














![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)
![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)




























というより戻ることはなさそうに見えます。
大きくならないといけない理由がもうないのですし。
人間という天敵に対応するための進化をしてしまったのですから、仮に戻ることがあっても人間が再び彼らを狩るようになれば最初の時よりも早く同じ進化をするようになるでしょう。
でも良いデータが取れたじゃないですか、人間に狩られるとどう進化するのかという傾向とその対応速度が分かったわけです。
他の魚や動植物も同じような進化をするかもしれないという想定を今後の狩猟計画に組み込むことで食糧生産の正確な見積もりができますよ。
種の中に変異が蓄積されていたところに、淘汰圧がかかった結果、そうでない形質の個体が優勢になった
ってだけで、ここのスピード自体は一瞬でも行ける
進化ってか淘汰
変異の蓄積にはやっぱり長い時間がかかる
興味深い研究の紹介をありがとうございます。ゾウの牙とかサイの角とかカブトムシの角とかも、人間が勝手に価値を見出して長い個体を乱獲するものだから、自然界ではどんどん短くなっているそうですね。ちなみに、「自然選択ならぬ“人間選択”が起きていた」と記事にありますが、自然選択の対義語として「人為選択」の方が適切な用語だと思います。
人為選択だと、その結果(縮小)を人間が求めていた(縮小させるために大きい個体を乱獲した)ように感じられるからではないだろうか。
(一部の)人間にとって望ましい形質を獲得させるための選別・淘汰圧を掛けること……いわゆる〝品種改良〟と、このタラの例は人間の意図がどこにあるのかは全く逆なので、それを明示するために敢えて聞き慣れない造語「人間選択」を選んだように私は思う。
単に小さいタラだけセレクションしてきただけなので、大きいタラをセレクションして海に戻せば良いだけ。
言うは易しだし、莫大なコストはかかるけど25年かけて養殖し続ければ元に戻るかも。
犬で言うならチワワとセントバーナードみたいな感じで。
物理的には可能かもしれませんね。
しかし、大型に該当する個体が既に相当数減っているので種の生存サイクルを維持するのに必要な染色体の多様性を維持出来るレベルで個体が残っているのかが課題となりますね
オオシモフリエダシャクの工業喑化とかあるから、「これまで進化は数千年、数万年という時間スケールで起きると考えられて」きたってのは言い過ぎじゃないかな
確かに人間もこの半世紀で容姿が良い方が増えたような気がします
劇的な変化が起こっています
もう半世紀もすれば猫みたいな容姿の方が好まれて世界が猫に埋め尽くされているかもしれません
ちっちゃくなっちゃった!
ほかのコメントでもあるように、元々あった遺伝的多様性の中から大きくなる個体群が人為的に淘汰されただけでしょ。
人間の集団の中にも身体の大きさや成長速度にばらつきは存在する。ある日宇宙人が侵略してきて、人間を家畜とするために、驚異となりうる一定以上の大きさを持つ個体をすべて間引いたとすれば、同じことが起こる。そうして身体の小さな人間集団の遺伝子を分析すれば、当然「以前の個体群とは遺伝子レベルで変化した」と言えるだろう。
だけど、それは進化なのかな?変化したのは母集団内の平均じゃないのかな?
私の理解では、むしろあなたのいう「淘汰圧による集団内の遺伝的特徴のシフト」こそが生物進化の定義だと思うんだけど、これを進化と呼ばないならあなたにとって進化とはどんな現象?
淘汰圧が自然か人為的(宇宙人為的?)かという違い?
集団内に同じ形質が完全に現れなくなったら進化ってこと?
それとも、もう元には戻れないくらい形質が固定化されて初めて進化と呼べるということ?
少なくとも、
>これまで進化は数千年、数万年という時間スケールで起きると考えられてきましたが、
「これ」を「進化」として捉えてるこの記事の執筆者と同様の認識に立ち、その上で、今回の記事の内容が「これ」に当たる出来事などではない、ということは確かだよね。
淘汰は進化のメカニズムの1因子であって、進化そのものではない、ですかね
極限を考えてみればわかりやすいかもです
例えば、のび太くんは自分以外の全人類を消してしまったことがあります
この場合、ヒト集団内の遺伝的特徴はのび太くん1個体のものへ収束しています
これをヒトからのび太くんへの進化と呼んでいいでしょうか
遺伝子プールの変動していくありざまを進化と呼んで、必ずしも形質の変化を伴う訳ではない前提が共有されてない気がする。
隔離があれば2集団間の遺伝子頻度が変化する。結果的に交配できなくなるまでゲノムが変わったら、種分化。
選択圧があれば1集団内の遺伝子頻度が変わる。(集団が徐々に変わってるように見えるが、祖先型が保存された生け簀があれば祖先と別種ができたように見えるはず)
>ヒト集団内の遺伝的特徴はのび太くん1個体のものへ収束
一個体だと絶滅しちゃってるけど
ペア、もし単為生殖する生き物が個体群作れば進化だよね(ボトルネック効果の典型例)
火星に移植に置き換えたら、進化して火星人に種分化したって表現するんじゃない?(入植者効果)
種と平均と分散をもつ集合として、平均が移動した場合は一律に進化と呼ぶ感じですか
一人だと絶滅は例外ですね
シンプルでスッキリしてますけど、
進化という言葉で表すものに対して狭義な、弱い気がします
酸素で巨大化する。そうでない環境でタラを大きくなっていた?。そりゃ、人間でも身長高い男がカツコイイ。あるはな。これ、水産学部では何も、昔から言われていた(こっからエンジン入るぞ。つい来いよ)。機械系はカマトトぶるが、乱獲がおこなわれる海域で成長が早く小さな魚が成熟するも。で、カマトトぶって、でも、機械は生産し魚群探知機で取りまくる。資源管理型漁業をノルウェーは先にすすめる(ゲーム理論と財産権制御)。二酸化炭素の排出権取り引き制度。あれはノルウェーの漁業管理が先に編み出した自然量の財産権取り引き制度のコビー。しかし、気象学は、俺等が編み出したばりの顔。東大ですら、影では、農水学部は馬鹿にすると聞く。世界で戦争で人を殺しまくり、影では、農水は下と見ている。これを載せはしないだろう。工学に発明権あるよね。払え。気象学は水産学に特許料を払え。お前たもやってるじゃないか。払え。
この内容、日本の水産資源学の教科書に30年前に、この予測がされていて、それは当然と思っていました。周りの意見を聞くと、日本の水産資源解析が先見の明があり、優れていることが分かりました。優れているので、気象学や工学に申し訳ありませんでした。恩恵は受けています。それは、利害関係のある医学には申し訳ないですが、この事が、小生に遺伝子は変わるという哲学を与え、コロナワクチンを打ちすぎて死亡する人がいる中、病院で、コロナワクチンを1回しか打たないという行動になっていました。命拾いという恩恵を受けてます。気象学、工学がレベルが低いのではありません。日本の水産資源解析学がレベルが高いのです。今後、水産資源は、食べれない奴が現れようが高くなります。結末は変わりません。戦争時は農民が強いのです。