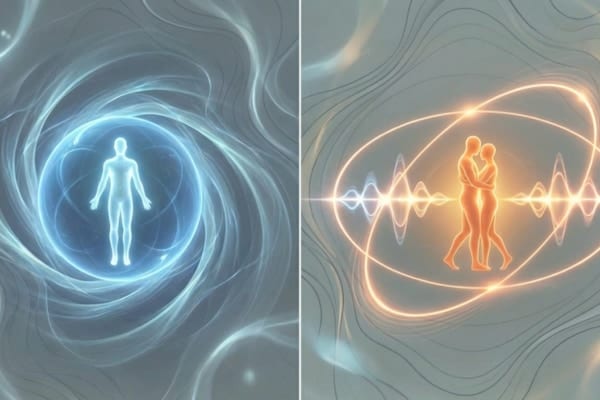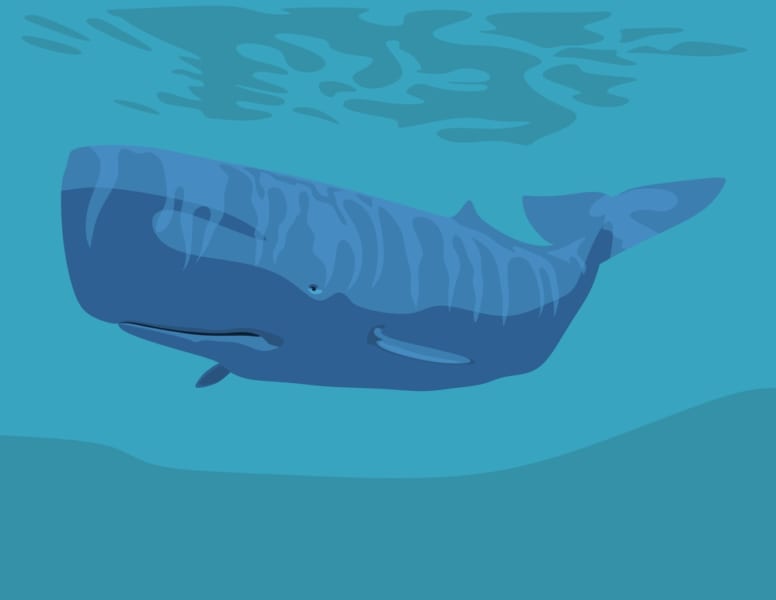道徳心には「6つの基盤」がある

社会心理学者ジョナサン・ハイトらが提唱した「道徳基盤理論(Moral Foundations Theory)」では、人間の道徳判断は6つの“直感的な基盤”に支えられていると考えられています。
この理論によれば、私たちが「良いこと」「悪いこと」と判断するとき、以下のような6つの感覚が無意識に、あるいは直感的に働いているとされます。
① 思いやり/危害(Care / Harm)
他者の苦しみを減らし、守ろうとする気持ち。赤ちゃんや弱者を守る感情に由来します。
② 公平さ/不正(Fairness / Cheating)
ズルを許さず、正当な報酬や分配を求める感覚。「フェアプレー」や「正義」に通じます。
③ 忠誠/裏切り(Loyalty / Betrayal)
家族や仲間、国に対して一体感を持ち、裏切りを嫌う心。チームワークや愛国心に繋がります。
④ 権威/転覆(Authority / Subversion)
上位者や伝統への敬意を抱き、社会秩序を重んじる気持ち。規律や年功序列などの感覚と関連します。
⑤ 純潔/堕落(Sanctity / Degradation)
身体や心の“神聖さ”を守ろうとする意識。性的節度や清潔へのこだわり、不快感などが含まれます。
⑥ 自由/抑圧(Liberty / Oppression)
支配されることを嫌い、自由や平等を守ろうとする衝動。権力に対する反発や抗議の基盤です。
これらは「道徳心のセンサー」のようなものであり、文化や時代を超えて人類に共通する心理的傾向です。
政治的立場によっても傾向が分かれ、リベラルな人は「思いやり」や「公平さ」を強く支持し、保守的な人は6つすべてを重視する傾向があると指摘されています。
では、これらの直感的な道徳観と、「知能の高さ」とはどのような関係があるのでしょうか?

































![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)