なぜ「AI」でもヒットしたのか?
では、Velvet Sundownはなぜここまで人気を集めることができたのでしょうか?
かつてSpotifyでデータ分析を担当していたグレン・マクドナルド氏は、「Spotifyのおすすめシステムが、かつてのような“人間の傾向”ではなく、“音響的特徴”をもとに楽曲をレコメンドする仕組みに変わっている」と指摘します。
このようなシステムでは、AI生成曲であっても偶然レコメンドに乗り、爆発的に再生される現象が起こり得るというのです。
また、ベテランの音楽A&R(アーティスト・アンド・レパートリー)も次のように語っています。
「音楽が素晴らしいからじゃない。AIだから注目されたんだろう。本物に見えないものが、今は逆に新鮮なんだ。でも、やがてAIが“本当に良い曲”を生み出すようになる。そのとき、誰も“AIかどうか”なんて気にしなくなるよ」
実際、The Velvet Sundownのケースは「AIによるヒットの第一波」として記憶されるかもしれません。
一方、フレロン氏自身はこう語っています。
「人々がAI音楽に対して強く反発する気持ちは理解している。だけど、それは過剰反応でもある。
テクノロジーは芸術にとって新しい道具だ。過去のアーティストたちも、シンセサイザーやドラムマシンを導入してきたじゃないか。
AIだって、その延長に過ぎない」
彼は「文化はルールに従って生まれるものではなく、奇妙な実験の繰り返しの中から発展してきた」と語り、AIという道具で新しい“音楽の現実”を描こうとしているのです。
The Velvet Sundownは、リスナーの耳を魅了した“実在しないバンド”です。
私たちは今、「誰が演奏したのか」という問いよりも、「それを好きかどうか」という問いのほうに重きを置く時代に入りつつあります。
このバンドが突きつけたのは「音楽の価値とは何か」「本物とは何を指すのか」という根源的な問題でした。
もしかしたら、AIが作った音楽をリスナーが受け入れる未来は、もうすでに始まっているのかもしれません。












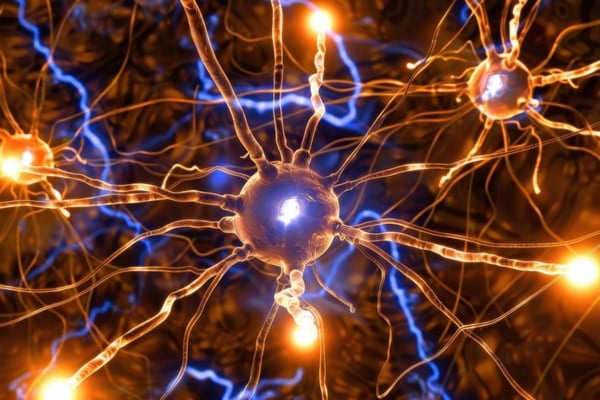
















![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)
![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)



















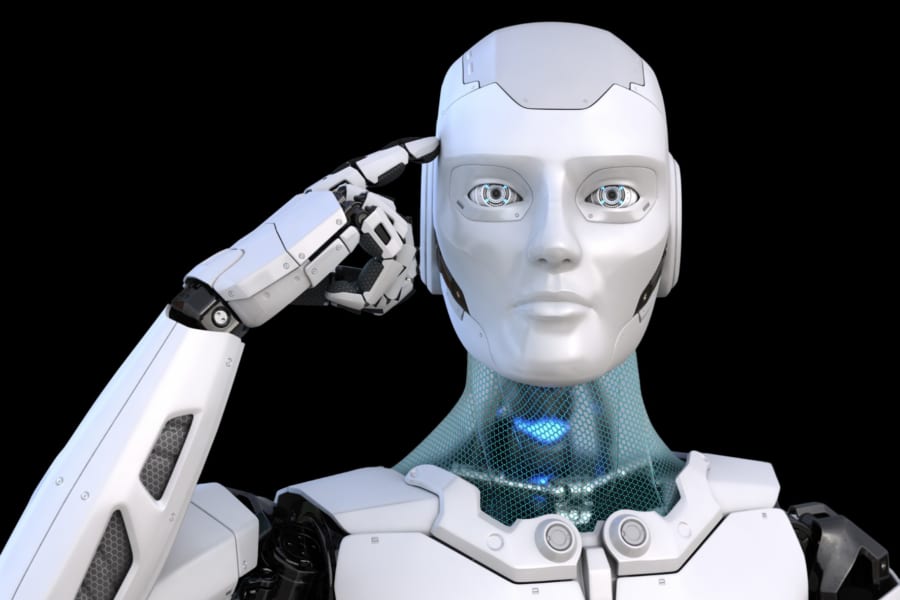








別にAIでも構わないと思いますし、AI出てくると人間では勝てないでしょうね。
よくクリエイティブな分野ではっていうのですけど、そのクリエイティブな分野って実は全くクリエイティブではないので、一番AIに勝ち目がない分野なんですよ。
音楽とかってすでに定石は出来上がっていて、それを少し手直しするだけになってるので、アクセス可能な過去の音楽全てを学んできているAIにはどうやっても勝てないのです。
囲碁とかチェスと一緒でこれからは音楽性云々ではなくて純粋に演奏楽しむとかそっち方面になると思います、楽しみ方がね。
普通に良い曲だったわ…
それな。
日本のYouTubeから派生なら
かみかぜmusic がわかりみが深い。
DTMやフィンガードラムが登場してきた当時も猛烈に反発はあったのだそうです。なので『過剰反応だ』というのも解らなくはないです。
ただ、これは存在そのものを作り上げているわけなのでどうなるんでしょうね。これも慣れるのでしょうかね。
AIに仕事が奪われる。と昔からよく言われますが、絵や音楽といった創作から追われるとは思いも寄らなかったです。
2日にフレロン氏インタビュー記事が出た翌日
フレロン氏が広報ではなく赤の他人だったと
3日、自ら報道しておりバンドもフレロン氏と無関係であると
表明しております。
上記含めた記事をYah⚪︎⚪︎ニュースが4日に取り上げているのに
10日になって中途半端な記事をあげるのは如何なものかと思いますが。
個人的にはAIバンドだと思いますが
本人が認めない限りは分からないですからね。
いい曲とは思わないけど、母国語じゃないからなのか全然違和感はないなぁ。
AIが作る音楽があってもいいけど
人間が作ったものだと偽るのはダメだよね
こういうクリエイティブ系は作品の元ネタを知ってる人の方が反発あると思う
今まで散々クリエイティブの道具がデジタルに置き換わってきたけど、それは作り手が新しい元ネタになってファンを獲得してきたから
スクリプトを打ち込むのがクリエイティブと思えるが境界線かもね
なので世代が変わらないと人間はAI芸術を楽しめないのかも
音楽自体のしゃらくささより、人間を偽ることに対するしゃらくささが文化に対する足蹴りに感じる。他人の限りある時間などどうでもよくなるのだろう。
最初AI疑惑について突っ込まれた時に認めてれば良かったのに。一度でも否定した瞬間、信頼は地に落ちる。その時点でThe Velvet Sundownは、“怠惰で退屈なAIバンド”のレッテルを未来永劫背負うだろう。どんなに人の心を打つ名曲を作れたとしても、ね。
日本でも既に「YAJU&U」というネットミームにあやかった音楽生成AI製の動画が3000万回以上再生されている。
音楽ではないが、Tiktokからの「トゥントゥントゥントゥンサフール」というAI由来の架空クリーチャーが世界中で流行している。ホラーゲームにもなり、日本のゲーム実況者がこぞって実況動画をあげている。
コンテンツがAI由来でも関係なくバスる時代に既に突入したといえるだろう。そしてその傾向は今後も続いていく。
膨大な優れた曲からつまんでんだからいいものできるに決まってんだろ。使用料払ったか?
ギターの音1音で『あ、これ〇〇だ』くらい分かるようになってるレベルじゃないと、もう違い分からんかもね。
ちなみに楽器を相当本気でやってたので(お金貰えるところまで)、リアルかそうじゃないかはすぐ分かるけど、集中しないで流されたらようわからんかもしれん。
ただ、このバンドに何も感じるものはないけど。
いい曲ですね。このまま核戦争が起きず奇跡的に人類のテクノロージーが進歩に続いたら、何れ映画マトリックスの世界のようにリアルタイムで現実が作られるようになるかもしれませんね。
AIか?って言われて否定した癖にAIの未来を語られても言い訳とかにしか感じないんだよなぁ……
あれ、これフェイクニュースじゃなかったっけ?
なんつーか、今の音楽がしゃらくせえって感じてる人に刺さる、ストレートでオールドファッションな曲だったな。
今のダンサブルな(そしてダンサブルでしかない)音楽の方がよっぽどAIで作ったっぽいわ。
能書きを食べるのは自称専門家
子どもたちは能書きも値札も食べません
そのものの本質を見抜いて良いものに集まるのです
専門家しか文句を言わないのであれば…?
単純に
「どうしてそんなウソつくん?」って話
虚偽の上に信頼関係を築くのは難しい
「だましてないよ?黙ってただけ」なんてのは屁理屈よ?
佐村河内氏のゴーストライターがマーラーぽい曲を作ったように
AIも何らかのアーティストの作風や何らかのジャンル・形式に類似した曲は無数に作れる
ただ独自の作風や新しいジャンルを切り開き様式美として確立していくのはやはり人間なのだろう
その場合AIは補助的に使われることはあるだろうが
才能のある人間の詳細な指示と調整を通じてオリジナリティを付与する必要があるだろう
野獣だってThe Real Tuesday Weldが元ネタだしパクり元が分かる人には分かる
それをオリジナルと言うのが不快
機械の道具はあくまで道具だった
AIは道具じゃなくて、AI自体が芸術を行っている。いやAIが芸術をやるのではなく、AIを使って人が表現をやるのか?
若干違和感を感じる曲だったが、言われなければ分からないかも。