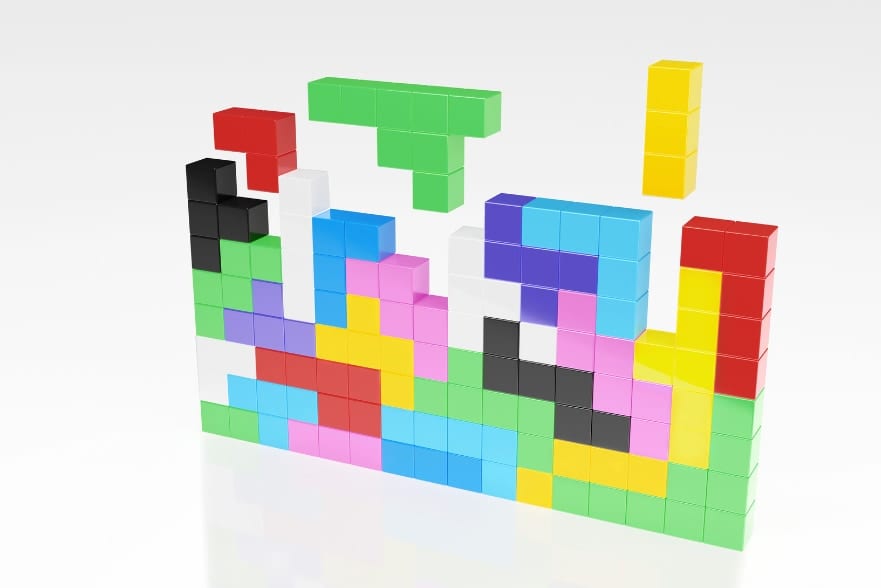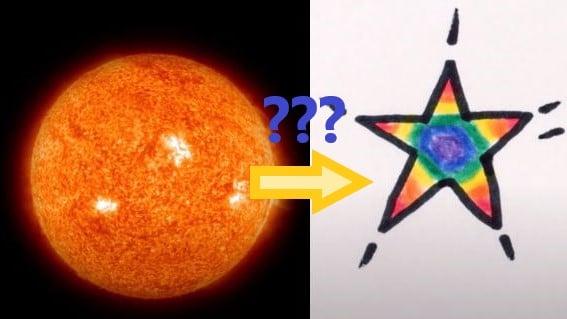ADHDの治療薬を飲み続けた成人の脳を分析
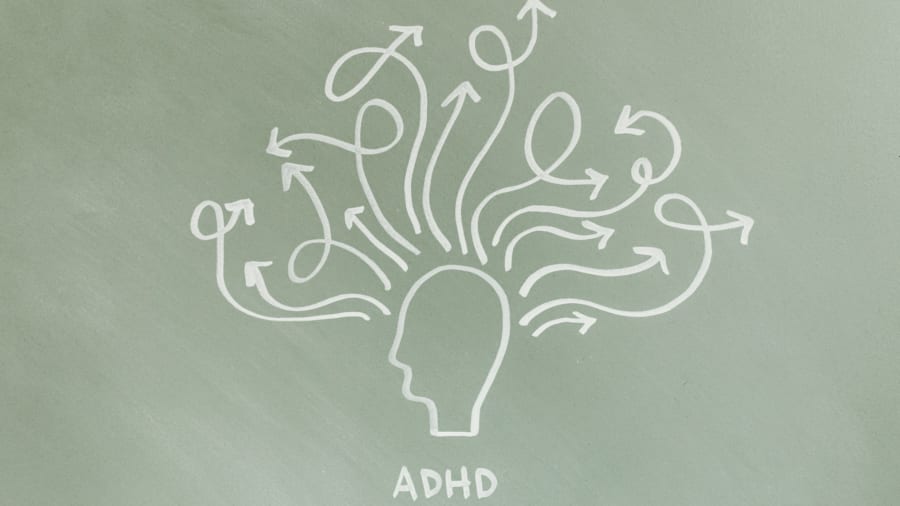
仕事や家事をしているとき、集中しようと思ってもどうしても気が散ってしまうことはありませんか?
やるべきことがあるのに、つい別のことに手を出してしまう、そんな経験は多くの人がしているはずです。
ADHD(注意欠如・多動症)の人たちは、そのような問題を日常的に抱えています。
ADHDは子ども時代に診断されることが多い神経発達症の一つですが、実は約半数以上が大人になっても症状が続いてしまうことが知られています。
集中力が続かず仕事や人間関係に支障をきたしたり、思いつきで衝動的な行動をとってしまったりするため、成人になっても適切な対処が必要なのです。
そんなADHD治療の主役となっているのが、メチルフェニデート(商品名リタリン、コンサータなど)やアンフェタミン系の薬(アデラルなど)に代表される「精神刺激薬」です。
これらは脳の中で注意や集中力に関わる神経伝達物質の働きを高める薬で、日本でも一部が広く使われています。
服薬した人の多くは実際に症状の改善を感じる一方で、「薬をずっと飲み続けて本当に大丈夫なのか?」と不安を感じる方も少なくありません。
なぜなら、薬を長期間服用すると、次第に効き目が弱まるのではないか(耐性がつくのではないか)という懸念や、脳に悪い影響があるのではないかという不安があるからです。
特に、大人になってから長期に渡って薬を飲んでいる人たちにとって、こうした疑問は切実な問題となります。
実際のところ、精神刺激薬を長期間使用すると脳にどんな変化が起きるのか、またそれがADHDの症状にどう影響するのかについては、はっきりとした答えが出ていませんでした。
脳の構造や機能の変化をMRI画像で確認する研究は子どもを対象としたものが多く、大人のADHD患者に関するデータは非常に限られていたのです。
そこでイギリスのブラッドフォード大学のSherief Ghozy博士らの研究チームは、「大人のADHD患者が精神刺激薬を長期間服用すると脳に何か変化が起こるのだろうか?」という疑問を検証するために新しい研究を行いました。
この研究で特に興味深いのは、「ADHD患者と健康な人を比べる」のではなく、「同じADHD患者でも、薬を飲んできた人と飲んでいない人では脳に違いがあるのか?」という点を調べているところです。
もし違いが見つかれば、それは薬の長期服用による影響を示しているかもしれません。
つまり、「薬がADHD患者の脳をどのように変えるのか?」ということを具体的に確かめることが、この研究の大きな狙いでした。
さらに研究チームは、ADHDの特徴の一つである「衝動性」にも注目しました。
衝動性といってもさまざまなタイプがありますが、その中でも特に面白いのが「冒険的衝動性(venturesomeness)」です。
これは単に衝動的に動くというよりも、「リスクは理解しているけど、それでもあえて面白そうだから挑戦してしまう」という性格を指します。
みなさんの中にも、危険だけど楽しそうなことについつい飛び込んでしまう方がいるかもしれませんが、こうした性格が薬を飲んでいるかどうかで違ってくるのかも、今回の研究の注目ポイントでした。
研究チームは、「薬を飲んでいる人」と「薬を飲んでいない人」のそれぞれの脳を詳しくMRIで調べ、ADHDの症状や衝動性との関連を探りました。
果たして、長期間の薬物治療は成人ADHD患者の脳にどのような影響を与え、またその脳の変化は症状や行動特性にどう影響するのでしょうか?































![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)