ADHD治療薬がもたらす「脳の変化」の真の意味は?
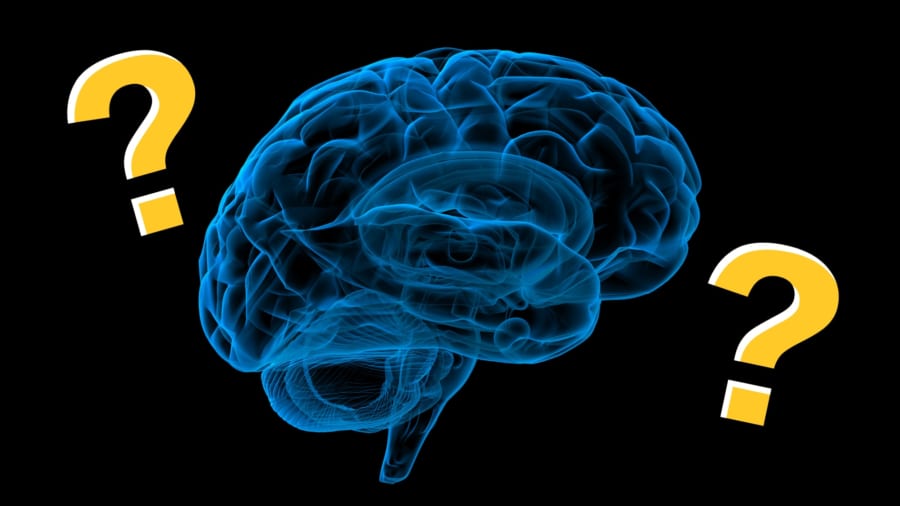
今回の研究によって、大人のADHD患者が精神刺激薬を長期間服用すると、脳表面のシワや谷が複雑になるという興味深い変化が示されました。
研究者たちは、ADHDの治療に使われる精神刺激薬によって脳の表面が複雑になる現象について、その変化が脳の発達や成熟を促している可能性を考えています。
脳の表面のシワが増えたり、谷が深くなったりすることは、一般的に脳が成熟していることや認知機能が向上していることを示していると考えられているからです。
特に眼窩前頭皮質と呼ばれる脳の部位は、感情をコントロールしたり、何かを決定するときの判断力や報酬を感じる仕組みに重要な役割を持っています。したがって、この部分の複雑さが増すことで、感情の調整や意思決定の力が向上する可能性があると推測されています。
また、「右ローランド蓋部」や「左補足運動野」などの領域が複雑になることも、物事を計画的に進めたり、注意を維持したりするなどの実行機能が改善する兆しになるかもしれません。
ただし実際の研究では、これらの脳領域が複雑になったからといってADHDの症状そのものが明らかに改善したわけではありませんでした。
そのため、研究者たちは「脳表面の複雑化が確かにポジティブな影響をもたらしている可能性はあるけれど、ADHDの症状が実際に良くなるかどうかは、まだはっきりとは言えない」と慎重に考えているのです。
つまり脳の構造変化と症状の変化は、それぞれ異なるメカニズムで生じている可能性があるということです。
加えてこの研究が示したのはもうひとつ興味深いことがあります。
それは、ADHD患者の中でも特にリスクを冒しやすいタイプの性格「冒険的衝動性」が、脳内の特定の領域、特に右中帯状回と右後頭葉上回という部位の灰白質体積と関係している可能性です。
脳の中帯状回は、感情や認知的な意思決定に関わる場所とされています。
一方、後頭葉上回は視覚情報を処理する領域です。
このふたつの部位の灰白質の体積が、「冒険的衝動性」という特性と相反する関係を持つことは、ADHDの人たちがリスクに対してどのように反応し、なぜ特定の行動パターンを示すのかという謎を解く鍵となるかもしれません。
もちろん、この研究にはいくつかの限界があります。
ひとつは対象者が26名と少数だったことで、より大規模な研究を行えば異なる結果が得られる可能性があります。
また、この研究は薬物治療によって脳が変化したことを明確に示しているわけではなく、最初から脳にこうした構造的特徴があった人々が薬物治療を選択したという逆の可能性も否定できません。
加えて、薬を服用していないグループには「不注意優勢型」のADHD患者が多かったということも結果に影響しているかもしれません。
つまり、ADHDのタイプによっても脳の構造や行動特性に違いがある可能性があるのです。
それでも、この研究が私たちに教えてくれたことは非常に重要です。
今回の結果は、「薬を飲めばADHDの症状が簡単に治る」というシンプルな期待に対して明確に疑問を投げかけています。
むしろ、「薬物治療はADHDの症状そのものではなく、脳の別の側面に影響を与えている可能性がある」という新しい視点を提供しているのです。
私たちの脳は非常に複雑で、ある部分の構造が変化してもそれがすぐに行動や症状に現れるとは限りません。
しかし、その複雑さの背後には、まだ解明されていない多くのメカニズムが潜んでいる可能性があります。
今回の研究結果を踏まえると、ADHDの治療法やサポート方法を考える際には、「脳の構造的変化」と「症状改善」を切り離して、それぞれを詳しく調べていく必要があるでしょう。































![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
















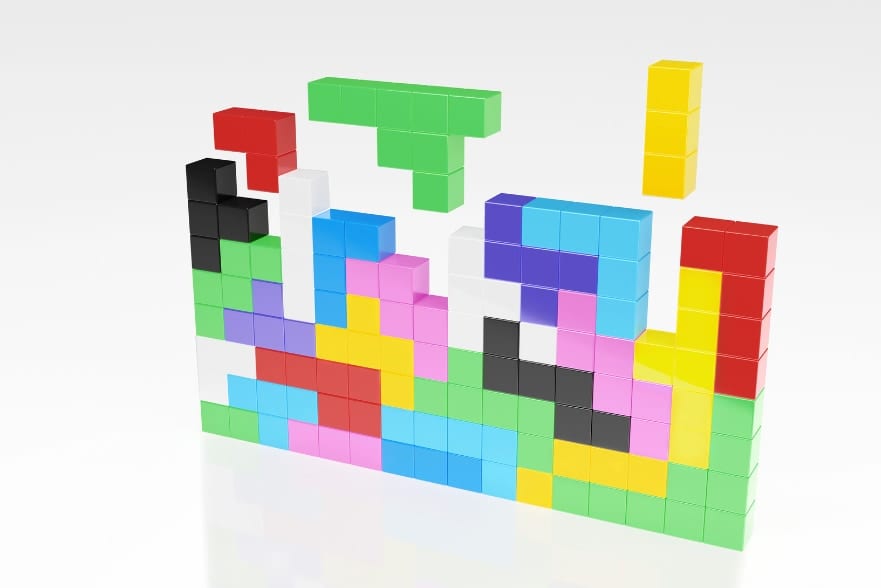





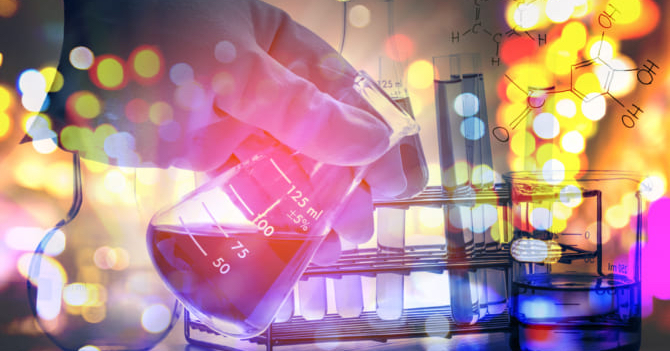






ハードウェアは再構成されてアップグレードされたけど、肝心のファームウェアは更新されず昔のままなので以前使われていた機能だけを使っている状態なのかな?
つまりハードの互換性は完璧ってわけだ。