隠せない心臓の動きと社会階層の関係

人間関係は社会階層を容易に飛び越えられるのか?
研究チームは、米サンフランシスコ都市圏で募集した成人男女264名(132ペア)を社会階層に関する事前調査によってグループ分けし、年齢・性別・人種が似た者同士で2人1組のペアを作りました。
ただし、実験途中の機器トラブルや参加者の離脱により2ペアが脱落し、最終的に130組(260名)で分析を行いました。
ペアのうち、48組(約37%)は似たような階層どうしのペア(高×高や低×低)、82組(約63%)は違う階層の人どうしのペア(高×低)でした。どちらのペアも、初めて会う相手どうしです。
実験ではペアの2人にいくつかの課題を行ってもらいました。
まずは自己紹介も兼ねたカジュアルな対話から始まり、協力して行う単語ゲーム、そして中立的な第三者に評価されるスピーチ課題まで、徐々に踏み込んだコミュニケーションを取っていきます。
最初の対話では「好きな食べ物や買い物をする店」などを話題にすることで、互いに相手の生活ぶりから社会階層をそれとなく感じ取れるよう工夫されていました(直接「年収はいくら?」と尋ねなくても、会話の端々から相手の暮らしぶりは伝わるものです)。
そのあと2人で協力してゲーム(言葉当てクイズ)をしたり、スピーチ課題に挑戦したりと、少しずつ仲を深める流れが用意されていました。
この研究が面白いのは、会話中に「心臓の動き」も調べていたことです。
もっと正確に言うと、「心室がギュッと縮んでから、大動脈という血管の弁が開くまでにかかる時間(PEP)」を特別な機械で測っていました。
このPEPが短くなると、緊張したり感情が高ぶっていたりすることを意味します。
つまり、「今この人はどれだけドキドキしているか」が体のサインとしてわかるのです。
また、会話中の挙動(はきはき話せているか、貧乏ゆすりなど落ち着きのない動作が出ていないか)もビデオ映像から専門家が評価しました。
さらに各タスクの後には、相手のことをどれくらい「好き」だと感じたか、どれくらい自分と「似ている」と感じたかについてアンケートに答えてもらいました。
こうしたデータを総合的に分析した結果、まず明らかになったのは、社会階層が低い人ほど、相手の体の反応に自分の体もよく反応していたということです。
相手の心臓がドキドキすると、自分の心臓も同じようにドキドキする――そんな風に、お互いの感情の波に「生理的に」合わせていたのです。
具体的には、低階層グループの参加者では会話中のPEPの変化が相手のPEPの変化とより密接に連動しており、まるで相手の感情の起伏に自分の心臓が寄り添うような状態になっていたのです。
しかもそれは、相手が同じ階層でも違う階層でも同じでした。
社会階層が低い人は、ある意味で誰に対しても生理反応が同調しやすいということが、体の反応からもわかったのです。
つまり社会的地位が低い人は、相手の階層に関係なく常に「相手本位」で敏感に反応していたと言えます。
次にわかったのは、相手が低い階層の人だと、会話が全体的にリラックスした雰囲気になりやすかったということです。
高い階層の人も低い階層の人も、相手が低い階層だったときのほうが、声がはっきりしていたり、落ち着いた動きだったりして、安心して話しているように見えました。
なお研究チームは、当初「高階層の人は会話の主導権を握りやすいのではないか」と予想していましたが、支配・主導の度合いについては階層間で差が見られませんでした。
これは、実験の課題が順番に発言機会を与える構成だったため、階層に関係なく互いに発言しやすい状況だったからだろうと考えられます。
しかし最終的な「好き」という評価に関しては、やはり自分と同じ社会階層の相手に対して高い好感度が示されました。
どのペアでも会話自体は概ねポジティブで楽しいものとなりましたが、対話後に「相手のことをどれくらい好きになったか」「相手と自分はどれくらい似ていると感じたか」を尋ねると、参加者たちは一貫して同じ階層同士のペアのほうを高く評価したのです。
言い換えれば、たとえ初対面の相手に丁寧に合わせてくれる心地よい交流があったとしても、人々の心の深い部分では「自分と似た者同士」のほうに安心感や親近感を覚えていたということです。
この傾向は社会心理学で昔から知られる「ホモフィリー(類は友を呼ぶ)」の原理そのものだと言えます。
今回の実験は、生理反応や行動観察といった無意識レベルの指標と、本人が感じたことを尋ねる意識レベルの指標を同時に測定しましたが、両者の間にはこのような「ずれ(ギャップ)」があることが浮き彫りになりました。
相手に対する生理的・非言語的な反応ではプラスの効果が現れても、最終的な好みの部分では同じ階層の相手を選んでしまうのです。




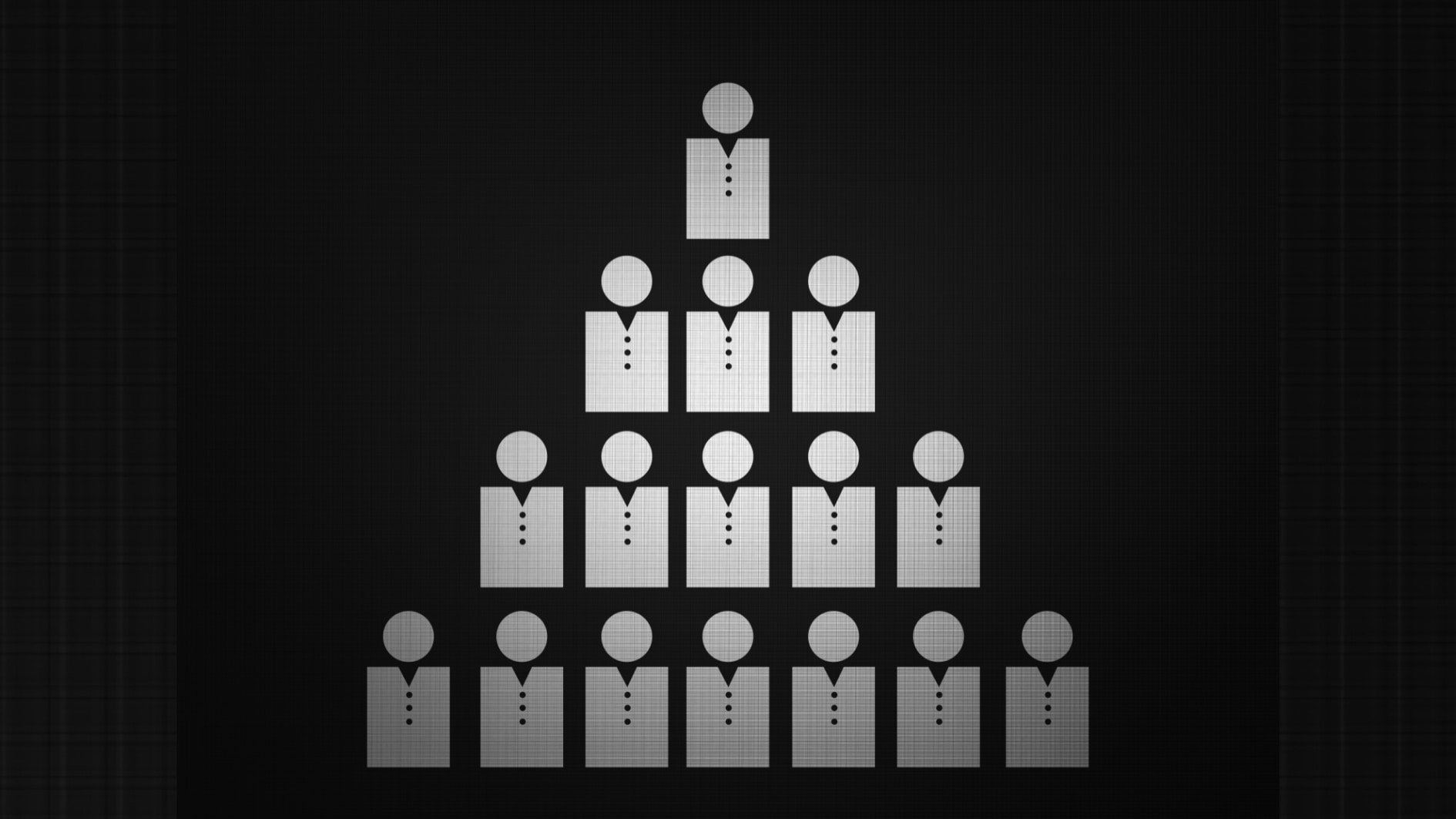






















![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)


![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)



























