社会階層を超えた交流は「諸刃の剣」なのか?

社会階層とは、収入や学歴、職業、そして社会における地位の自己評価などからなる人々の社会経済的な位置を表す概念です。
一般に、社会階層が高い人ほど多くの資源にアクセスでき、社会的なアイデンティティや機会を脅かされにくいとされます。
一方で社会階層が低い人は、より多くの社会的困難に直面し、その結果として周囲の環境や他者の行動に敏感になりやすい傾向があると考えられています。
世界的に広がる経済格差により社会の分断が懸念されるなか、研究者や政策立案者は異なる階層間の交流を促進することで相互理解を深め、分断の橋渡しにしようと模索しています。
例えば大学や職場、地域社会で多様な階層の人々が交流する取り組みが進められていますが、こうした接触は「両刃の剣」とも言われます。
確かに直接の交流は人々をつなぐこともできますが、同時に違いを際立たせてかえって不快感や緊張を生む場合もあるのです。
現に、人々は想像以上に自分と異なる社会階層の他者との交流を避けており、たとえ交流が生じてもあまり親密さやつながりを感じられていないという研究報告があります。
特に自分自身が社会階層で下位にあると感じている人ほど、階層の異なる相手との接触に尻込みしがちな傾向も報告されています。
こうした背景を踏まえ、本研究では「初対面同士で、しかもお互いの社会階層をさりげなく認識した状況なら、人々の交流はどうなるのか?」という疑問が探られました。
社会階層によって、人は初めて会う相手への注意の向け方や振る舞い方が変わるのか。
そして会話を終えたとき、相手への感じ方(好感度)は階層の違いによって左右されるのか――。
特に研究チームは、一対一でリラックスした状況を作った場合、社会階層の違いが交流の質にどのような影響を及ぼすかを検証しました。
特に、「似た者同士効果」によって、同じ階層の人同士の交流のほうが好まれるのか、それとも階層の異なる相手とも同様に好ましい交流が成立するのかを確かめることを目的としました。
果たして人間関係は社会階層を容易に飛び越えられたのでしょうか?




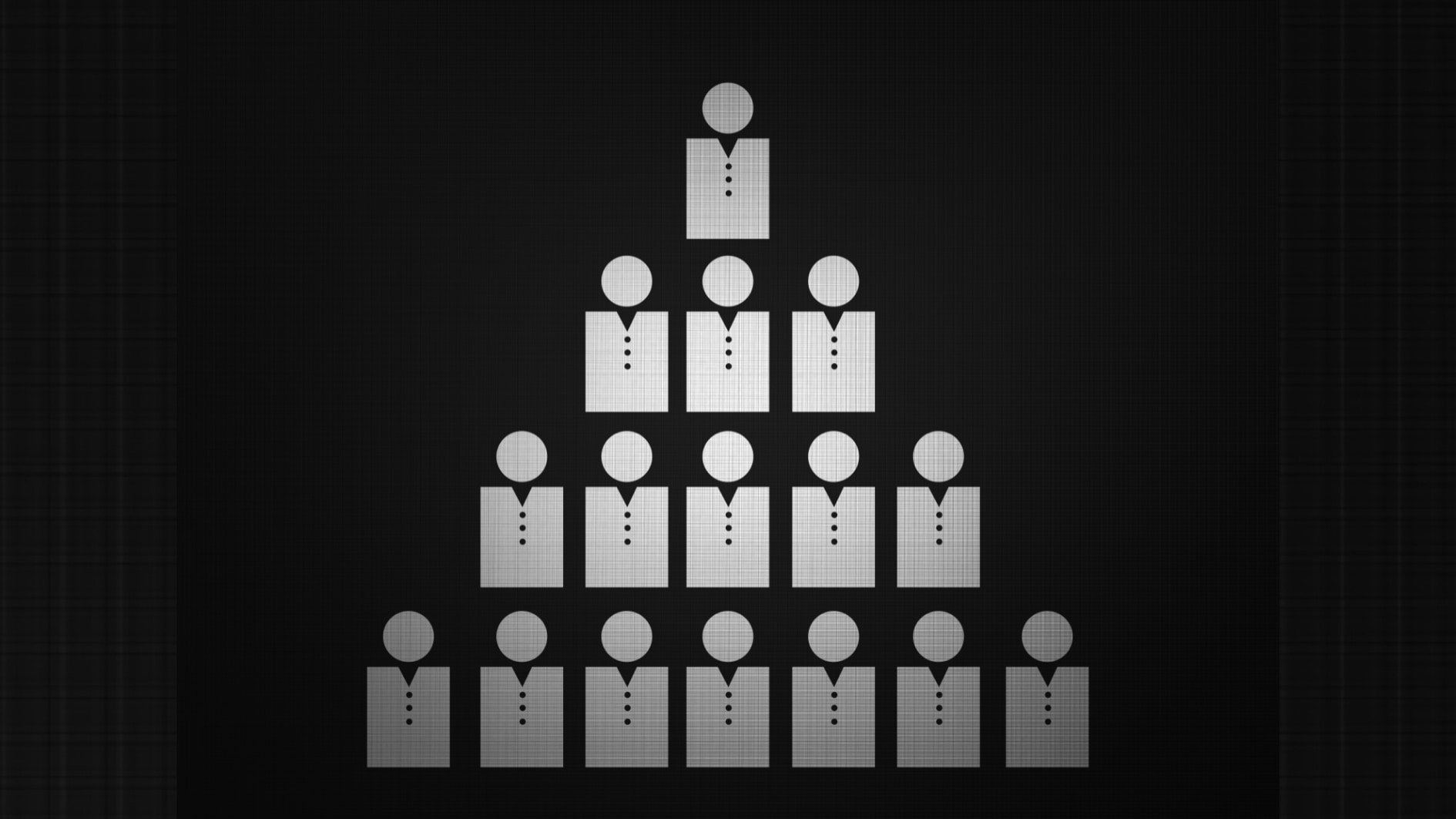
























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)


![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)



























