社会階層を超えた壁は心や体に影響を与える
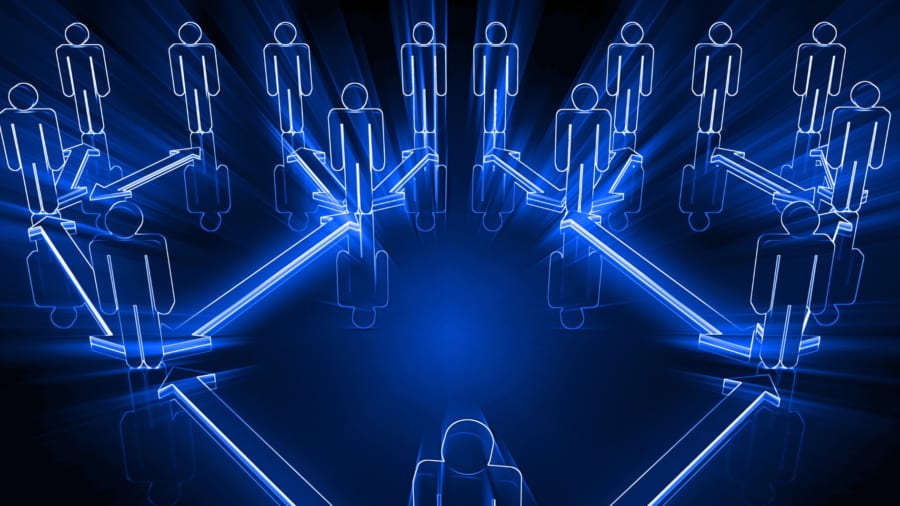
今回の研究で明らかになったのは、社会階層が低い人ほど、相手の気持ちに敏感で、無意識のうちに気を配っているということです。
実はこれ、これまでの心理学の研究でも「そうかもしれない」と言われてきました。
たとえば、社会階層が高い人はお金や教育、立場に恵まれていることが多く、まわりの人や状況にそれほど振り回されることなく、自分の意見をはっきり言える傾向があります。
それに対して、階層が低い人は、社会の中で困難なことに直面することが多くなりがちです。
そのため、人の表情や雰囲気、ちょっとした言い回しなどに敏感になっていきます。いわば「空気を読む力」が自然と育っていくのです。
今回の実験でも、社会階層が低い人は初対面の相手に対しても、自分の心の動きや体の反応を相手に合わせるようにしていました。
これによって、相手もリラックスしやすくなり、会話全体が落ち着いた雰囲気になったのです。
まるで「この人といると安心するな」と感じるような、そんな雰囲気を生み出してくれていたのかもしれません。
不思議なことに、こうした「安心感」があっても、参加者たちが「この人が好き」「また話したい」と思った相手は、やっぱり自分と同じような社会階層の人でした。
たとえ相手がやさしくしてくれていたとしても、「自分とちょっと違う」と感じる相手とは、なかなか仲良くなれないというわけです。
これは、心理学の世界で「似た者同士効果」と呼ばれる考え方とも一致します。
人は、自分と似たような人のほうが安心しやすいし、好きになりやすいという、人間らしい本能とも言えるものです。
研究チームの人たちは、「たった一回の短い交流だけでは、階層を超えて仲良くなるのは難しいのかもしれない」と考えています。
この研究からわかるのは、社会階層の違いは、ただのお金や学歴の問題ではなく、人との関係の作り方にも影響しているということです。
そして、リラックスした会話ができても、それだけでは「仲良くなった」とは言いきれません。
もちろん、この研究はアメリカの特定の地域だけで行われたものなので、文化や国が違えばまた別の結果になるかもしれません。
けれども、この研究は、社会の中にある目に見えない「階層の壁」が、どんなふうに人の心や体に影響しているのかを教えてくれる大切なヒントになっています。




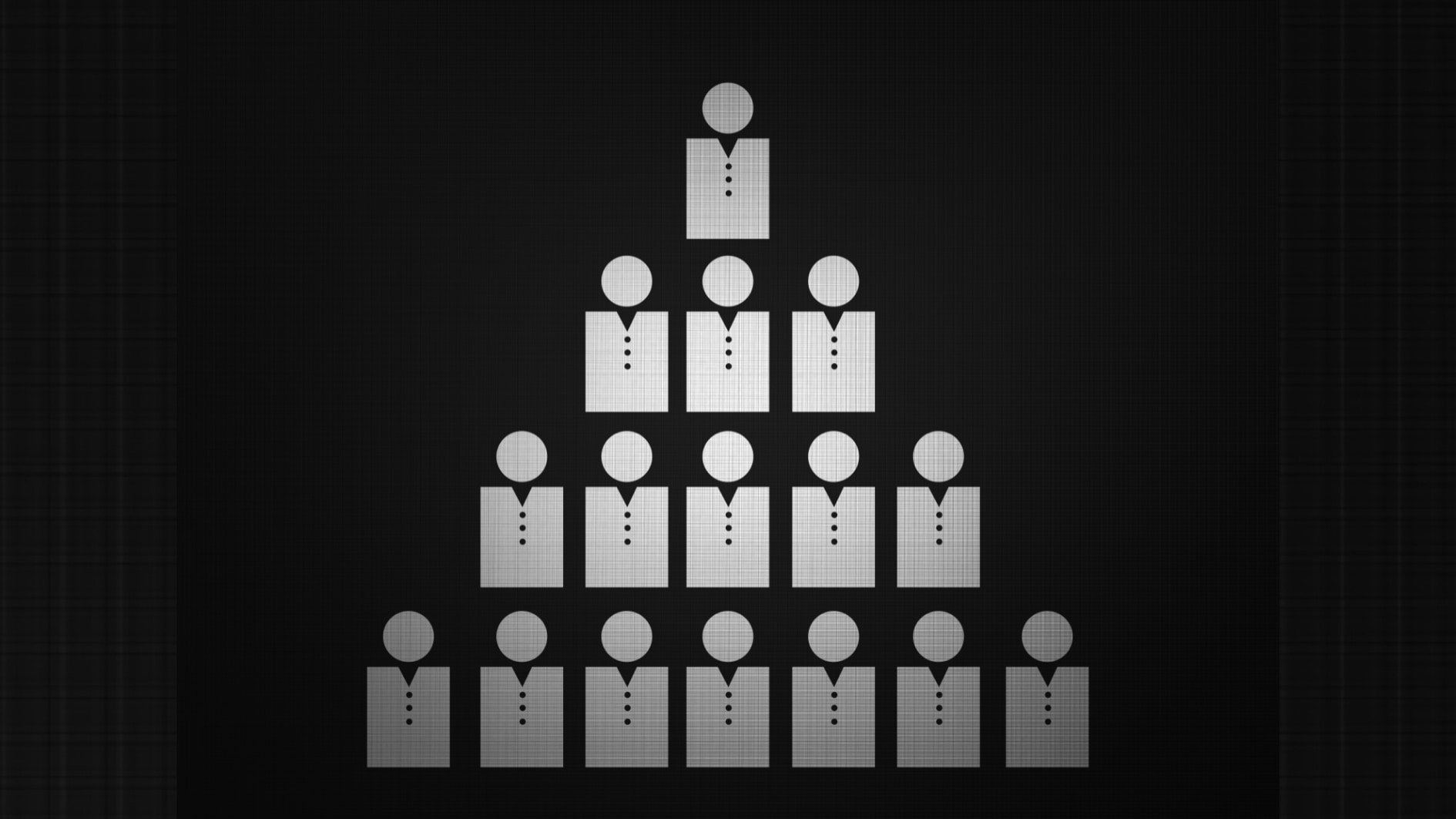























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)


![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)




























階層低いと協力しないと生き残れないですしね。
日本における世界でも類を見ない同調圧力の強さは国民のほぼ全体が社会階層が低い人の特徴が出ていますね。
これは日本人が奴隷なような扱いを受け続けてもはや気付かなくなってしまったからでしょうか。
それとも過去に奴隷のような扱いを受けた人たちが日本にたくさん移住してきてエピジェネティックな形質が保存されているのでしょうか。
単に島国であることと、人口密度の高さからだと思います。
島国のイギリスは日本と比べたらむしろアメリカ的で民衆が自由を求めたり自己主張をするよ。
良いか悪いかはさておきこういう類友精神が階層の固定化に寄与してるとしか思えないんだよな
ですよねぇ!