自分責めからの回復に必要なこと

以上の結果から、「自分を許せない」心理には過去への強い囚われ、過剰な責任感、理想の自分とのギャップ、そして感情を避けようとする対処癖が複雑に絡み合っていることがわかりました。
一方で「自分を許せた」人たちは、過去を受け入れつつ未来に目を向け、自分の責任は認めながらも限界も理解し、そして自分の大事な価値観に立ち返って行動することで前に進めていました。
あえて比喩で言えば、どうしても自分を許せず苦しんでいる人は、自分の心の車にブレーキ(罪悪感)をかけっぱなしにして止まってしまっている状態です。
論文は、こうした状態では過去の出来事が何度も頭に浮かび、行動の前進を妨げることを示唆しています。
ここから抜け出すには、ブレーキとアクセル、そしてハンドルをバランスよく使う必要があります。
具体的には、責任をきちんと認める(むやみに言い訳しない)と同時に、自分にも限界があったことを理解するという両立思考を持ち、さらに価値アファメーション(自分の大切な価値を再確認し、それに沿って行動すること)を行うことです。
これこそが「ワーキング・スルー(向き合って考え抜く)」のプロセスであり、痛みから逃げずにこの作業を続けることで、心のハンドル(価値観)が効き始め、少しずつ前進できるようになります。
時間はかかりますが、ブレーキを少しずつ緩めることが「自分を許す」ことにつながります。
今回の研究は、従来の量的データだけでは捉えにくかった「本人の語り」を用いた質的研究であり、自己許しの心理的プロセスをより立体的に示した点で意義があります。
特に、自己許しが単なる“一度きりの決断”ではなく、状況や心境の変化によって揺れ動きながら続くプロセスであることは重要です。
研究では、自分を許せた人であっても、罪悪感が再び顔を出すことがあると記されていますが、それでも価値観に沿って未来へ舵を切り直せることがわかりました。
また、「自己許しができる人とできない人が明確に二分されているわけではなく、多くの人にとって自己許しは継続的な揺らぎを伴う」とも示されています。
つまり、自己許しとは一瞬で完了するものではなく、試行錯誤を重ねながら少しずつ心を修復していく営みなのです。
では、この知見は私たちの日常や周囲の支援にどう役立つのでしょうか。
自分自身の場合、もし過去の失敗にとらわれて苦しんでいるなら、「時間が解決する」と放置せず、勇気を出して自分の感情や過去と向き合うことが大切です。
それは簡単ではありませんが、研究が示すように、それこそが前進するための有効なプロセスだからです。
同時に、「自分が完全に悪いわけではない」「人は誰しも限界や過ちがある」という自己への優しさや理解も忘れないでください。
この自己への共感と教訓の両方から学ぶ姿勢が、次の一歩への原動力になります。
周囲の人を支援する場合も、この研究はヒントを与えます。
研究チームは、自己嫌悪に苦しむ人を支えるとき、安易に「あなたは悪くない」と否定するのではなく、その人が抱える罪悪感や恥の背景を一緒に探り、現実的かつ適切な責任の捉え方を支援する重要性を示唆しています。
それによって本人は自分の中のモラルの傷(moral injury)を癒し、再び自分の価値観に沿った生き方(モラルの回復)を取り戻せる可能性が高まります。
言い換えれば、「自分を許す」ことは過ちをなかったことにするのではなく、本当に大切なものを見失わずに生きるためのプロセスなのです。
「自分を許すのが難しい理由」は、人間の心の複雑さを映す鏡でもあります。
しかし今回の研究は、その複雑さの中にも共通する心理的パターンや道筋があることを示しました。
たとえ心のブレーキを長く踏み続けてきたとしても、責任を認め、限界を理解し、価値観というハンドルを取り戻せば、少しずつでも前へ進めます。
自分を許すことは容易ではありませんが、過去から目を逸らさず向き合い、そこから学んだ教訓を胸に、自分の大切なものに向かって舵を切り直すことで、長い停滞から抜け出せるかもしれません。
今回の研究は、その希望のシナリオを裏付けています。














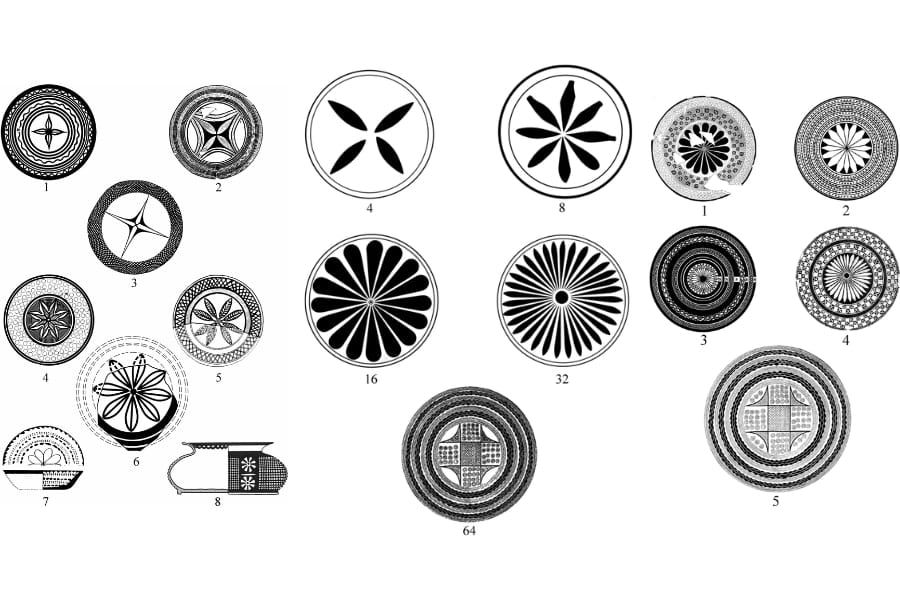

















![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)




























しかしながらあんまり自分を許し過ぎるのも問題ですからバランスが難しいですね。
「許し過ぎる」とはどういう事ですか?
自分を許せない人の「他の作業に逃げてしまう」とは別という事ですよね。
単純に気になるので、例えとかあると助かります。
サバイバーギルト/サバイバー症候群からの脱却プロセスに似ていますね。パトリシア アンダーウッド先生の論文は下記です。
https://webview.isho.jp/journal/detail/abs/10.11477/mf.7008200416
過去の出来事を苦しく思うのは記憶が雑念として立ち現れるからであって、
割り切って考えれば雑念という生理現象をどう対処するかにつきる
向き合うのであれば、雑念という現象に向き合うべきであって、
その内容に向き合うべきではないと考えます
神様、仏様、オド・ラグナ様。生涯、○○しないと誓います。
二元論的価値観から脱却することが自己を赦す事であり、なるべくして今がここにある。と言う価値観へ辿り着いた。
現在は、全てはただの現象であり、自分はそれを見させられてるだけ、というステージに入りかけている。
賛否あるコグトレの宮口幸治は自己肯定感を満たす唯一の方法は承認を受ける事みたいな主張をしています。自己否定から抜け出すには他人からの承認が必要です。もしそれ無しに自己肯定出来てしまうなら自己愛性パーソナリティ症候群だらけになってしまうし、人に好かれなくても幸福感が一人で満たせるからそれで良いという考えになり社会秩序も乱れかねません。
その上で一人で出来る範囲の事、すべき事としてどう考えるかの話なら支持出来るけど、この手の話は往々にして「全ては自分の考え方次第」みたいな理想論的根性論に陥りがちです。
またよくあるパターンとして、歴史を史学からしか見ない、心理を心理学から見ない視野の狭さゆえにいつまで経っても理解度が高まらない事があります。リンゴがあったら農家は熟し方や形を語る、料理人は美味しく作る方法を想像する、栄養士は栄養摂取の食べ合わせを考える、商人はどう高く売るか計算する、政治家は関税について議論するように何通りもの視点を持たないとリンゴの扱いに長けた事になりません。心理なら精神医学は勿論、社会学や文化人類学や進化生物学などからも一通り眺める必要があります。
日本は権威主義直系家族社会と言って差別的排外的で自己責任論が大好きな国民性です。他人を頼る事を悪と見做すから人々の繋がりが希薄になりエンドルフィンが不足し孤独から鬱になり医療費も浪費します。このタイプの社会の長所は個人能力と技術力が高まりけじめがある事、短所は満足度が低く視野狭く生産効率が悪く社会硬直しずるずる衰退し易い事です。自他を承認したがらないので一旦自他からスケープゴートに叩き落とされた人は這い上がれません。韓国も良く似た社会で閉塞感が漂います。治安は良くなるけどそれも自己都合を犠牲にした上に成り立っているのでトータルの満足度はさほど高まりません。駅でも飲食店でも職場でも腹立った時にガーっと怒鳴れるのと、それを全て禁止されて家に持ち帰って愚痴るしか無いのとどっちが自然で健全かという話です。情動は抑圧されると増幅します。喜怒哀楽を常識的なレベルで表出できるのが幸福度の高い社会です。ただこういう事を言うと必ず「じゃあ世紀末カオス社会になっても良いってのか」みたいなストローマンが必ず現れるのがうざいです。対極しか想像できないのは想像力=共感力の欠如です。
「自分に限界がある」って逃げ癖ある人がよく使うよね
自分を許すことができない私は、また同じ失敗を繰り返そうとしていることに今日気がつきました。