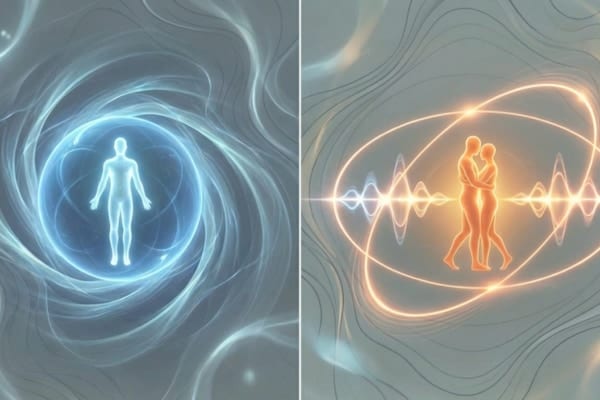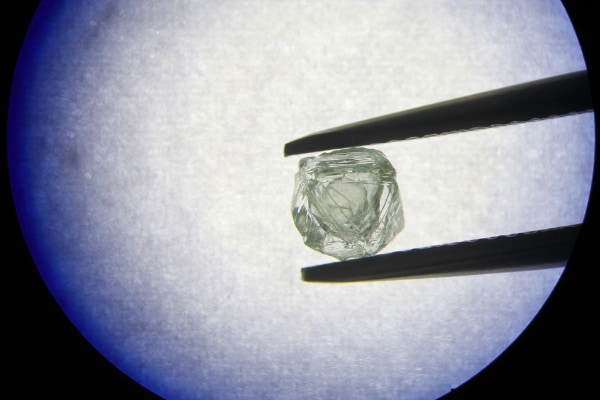3人に1人が人混みが苦手「環境感受性」

人混みや明るい場所が苦手、ちょっとした音でも集中できなくなってしまう。そんな経験はありませんか? 実は、こうした特徴を持つ人は意外と多いのです。
これは「環境感受性」と呼ばれる気質によるもので、外からの刺激にどれだけ反応しやすいかを表しています。
こうしか感覚の敏感さによる個人差は、これまでの研究で「低い(29%)」「普通(40%)」「高い(31%)」という分布になることが分かっています。つまり、3人に1人は人混みや明るい場所など刺激の強い場所が疲れて苦手、という悩みを抱えていることになるのです。
そして、こうした外部刺激への過敏さは、心の不調と関連している可能性があります。
というのも、心の健康と性格の関係については、これまでも多くの研究が行われており、「神経質な人ほどうつや不安になりやすい」といったことは、すでに広く知られているからです。
しかし、光や音、人の感情などに敏感に反応する「感覚処理感受性(SPS)」という気質については、心の不調との関係が指摘されてきたものの、全体像がまだよく分からない状態でした。
そこで研究チームは、思春期から成人を対象に「敏感さ」と「うつ・不安などのメンタルヘルス問題」の関係を改めて整理することにしました。目標は、過去の研究結果をまとめて、どの程度関連があるのかを数値で示すことです。この分野では初めての本格的なメタ分析(複数の研究を統合した解析)でした。
今回の研究では国際的なガイドラインに従って、事前に研究計画を国際的なデータベースに登録し、心理学・医学分野の主要なデータベースを幅広く検索。必要に応じて論文の著者に直接連絡を取るなど、見落としがないよう注意深く文献を集めました。
対象となったのは「12歳以上を対象とした査読付き論文」で、敏感さの測定には最も広く使われている標準的な尺度(成人向けのHSPS、子ども向けのHSCS)を用いた研究に限定しました。
また、同じデータが重複して数えられないよう、分析方法にも注意を払いメンタルヘルス問題についても、WHO基準やDSM-5に記載された一般的な診断に限定し、臨床現場で広く使われている信頼性の高い測定尺度を対象としました。
最終的に、厳しい基準をクリアした33件の研究を用いて、うつと不安の2つの領域についてメタ分析を実施しました。これにより、「敏感さ」と「心の不調」の関係を、研究間のばらつきを考慮しながら、正確に調査したのです。




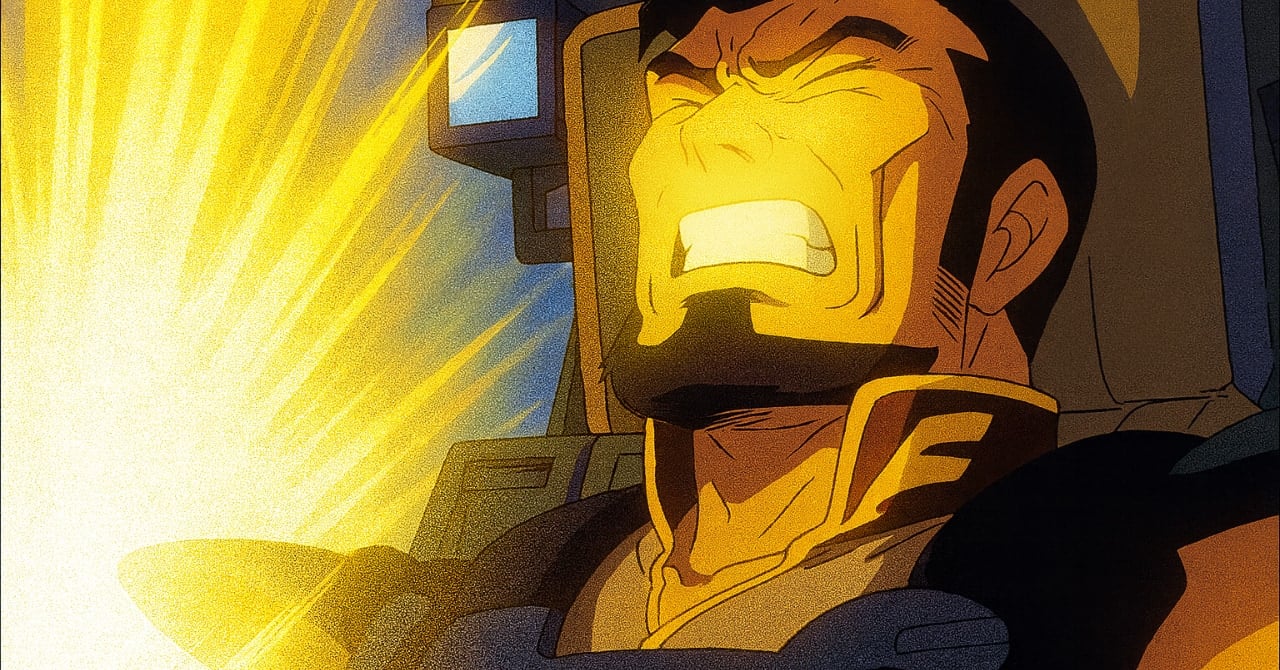



























![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)