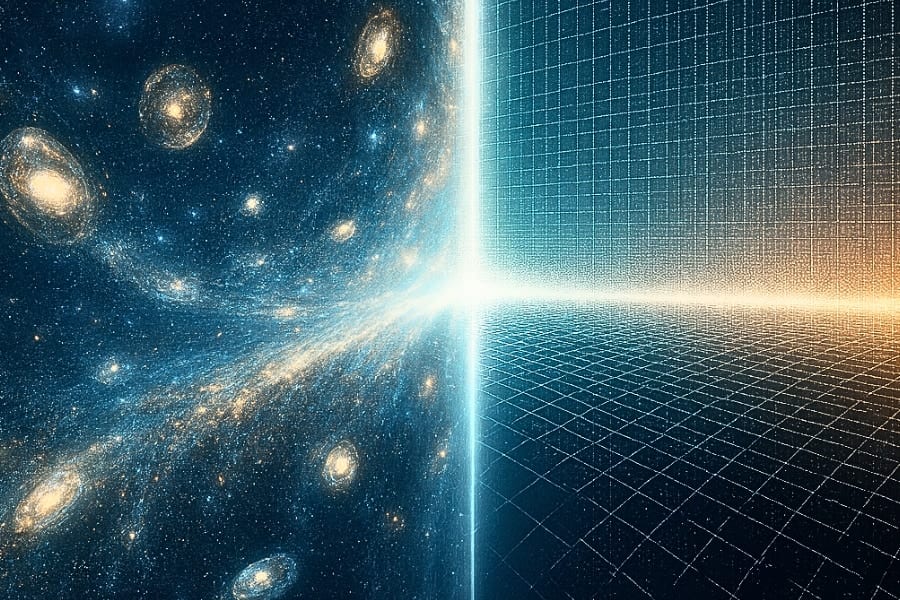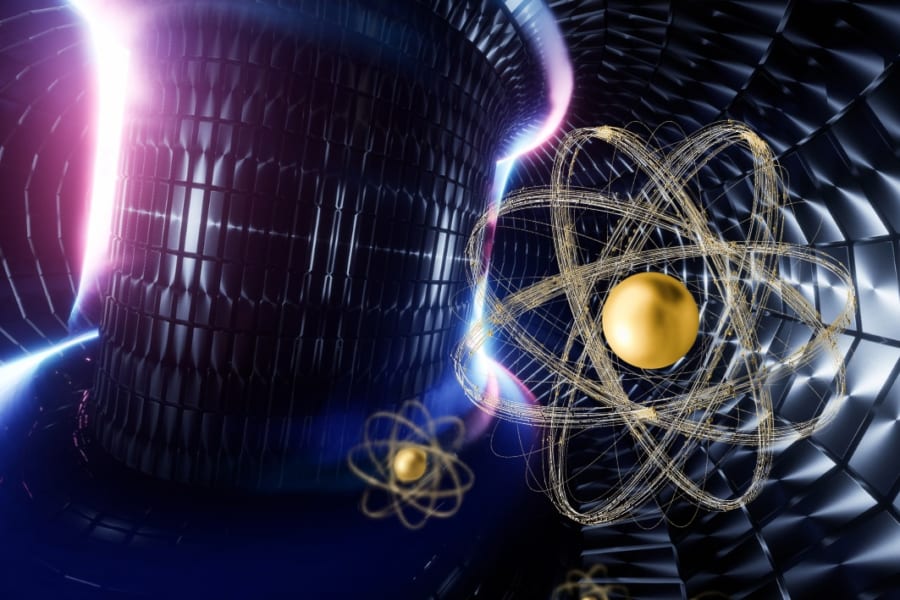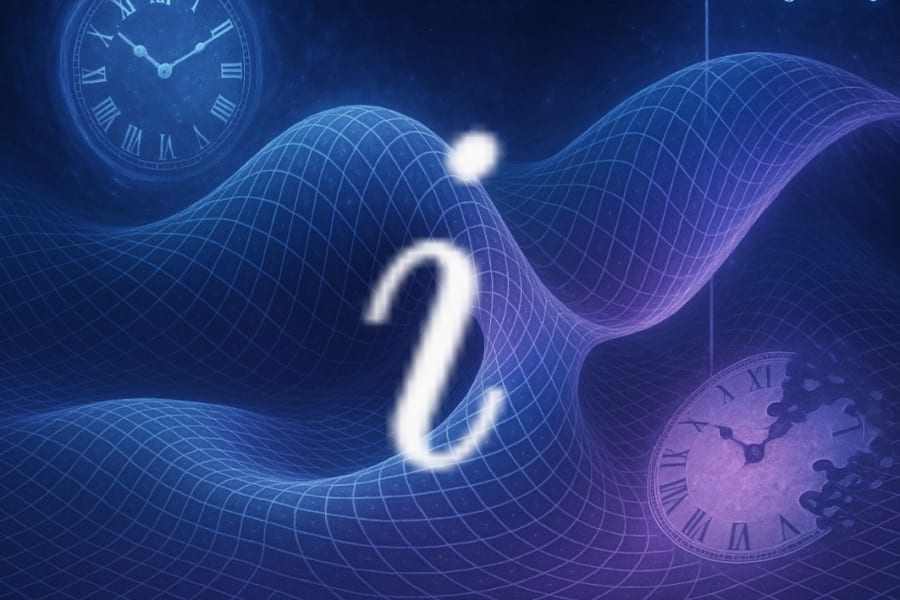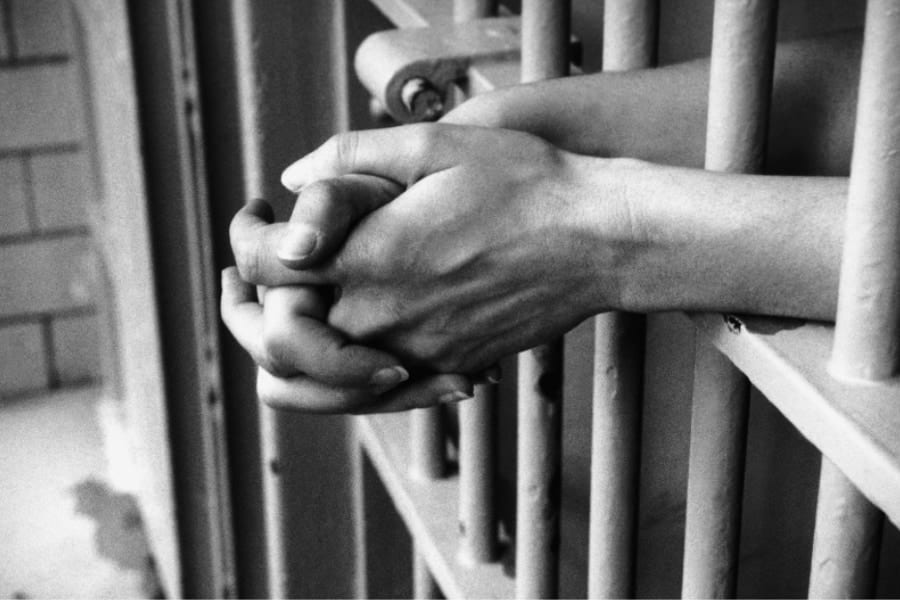ブラックホールはツルツルか、それともフサフサか?

この不思議な疑問を解明するために、科学者たちはブラックホール同士が衝突・合体する瞬間を観察しました。
とはいっても、実際にブラックホールを目で見ることはできません。
なぜならブラックホールは、光さえも飲み込んでしまうほど強い重力を持っているからです。
そこで研究者たちは、ブラックホールの衝突で発生する「重力波(じゅうりょくは:時空のさざなみ)」という特別な波に注目しました。
重力波とは、宇宙で大きな物体が激しく動いたときに生じる「時空のさざなみ」のようなものです。
ブラックホールが2つ合体すると、新しく1つの大きなブラックホールが誕生します。
そのとき、この新しいブラックホールは、まるで巨大な鐘が鳴るように震えます。
この「震え」は短い時間で徐々に弱まって消えていきますが、この現象を科学者たちは「リングダウン(鳴り止み)」と呼んでいます。
実はこの振動には、複数の「固有振動モード(こゆうしんどうモード:特徴的な揺れ方)」があります。
固有振動モードとは、簡単に言えば「音色」や「音程」のようなもので、ブラックホールそれぞれが持つ特徴的な振動パターンのことです。
ギターやピアノの弦がそれぞれ特有の音色を出すのと似ています。
これまでの研究では、ほとんどの場合、観測で確実に捉えることができたのは、この振動モードのうち最も強く明確な「1種類の音色」だけでした。
ブラックホールがもっと複雑な振動パターンを持つ可能性も指摘されてはいましたが、非常に弱い信号だったため、明確な証拠はなかなか得られませんでした。
ところが、今回の研究では特別な工夫によって解析方法を改善し、それまで気付かなかった「二つ目の振動モード(音色)」を発見することができました。
これは非常に重要な進展です。
なぜなら、1種類の音色だけを調べるよりも、2種類の音色を調べるほうがブラックホールの正体をより詳しく調べられるからです。
ちょうど、ある楽器を「ド」の音だけで聞くよりも、「ド」と「ミ」のような2つ以上の音を聞くことで、よりはっきりその楽器の特徴をつかめるのと同じです。
もしブラックホールに理論で予想されていない「毛」(特別な性質や特徴)があるなら、この2つの振動モード(音色)の間に何らかのズレや違いが現れる可能性があります。
つまり、ブラックホールの特徴が本当に質量と自転だけでは説明できない何かがあるなら、振動のパターンも理論から少しズレてしまうはずなのです。
しかし、今回の解析結果では、二つ目の振動モードを加えて詳しく分析しても、どちらの振動モードも単一のブラックホール(つまり質量と自転だけで決まるブラックホール)の特徴として説明できることがわかりました。
この結果は、アインシュタインが考えた一般相対性理論で予測された振動パターンとぴったり一致しており、理論と観測結果との間に矛盾は見つかりませんでした。
言い換えれば、今回調べたブラックホールに限って言うならば、余計な特徴(毛)は見つからず、本当に「質量と自転だけで説明できるシンプルなブラックホール」であることが示されたことになります。
科学者たちは、この解析を始める前には「もしかすると理論にはない『余計な特徴』が見つかるかもしれない」と期待もしていました。
しかし、今回の分析結果からは、そのような新しい物理を示す兆候は見つかりませんでした。
これはつまり、現時点の観測技術や対象となったブラックホールでは、アインシュタインの予言を超える新たな性質を発見することは難しい、ということを示しています。
この研究の特に注目すべき点は、「二つの音色を同時に捉える」という難しい観測が現行の観測装置でも可能だったことです。
本来なら、こうした複雑な振動パターンをはっきり捉えるには、さらに進化した次世代の観測計画(2030年代に予定されている高感度な望遠鏡)が必要だと考えられていました。
しかし今回は、GW190521という特別に大きく強い重力波を放った非常に珍しいブラックホール合体の観測データを使ったことで、この難しい観測を一足先に達成できたのです。
研究者たちは、現在の技術でもここまで詳細なブラックホールの振動を検出できたことに大きな驚きと喜びを感じています。




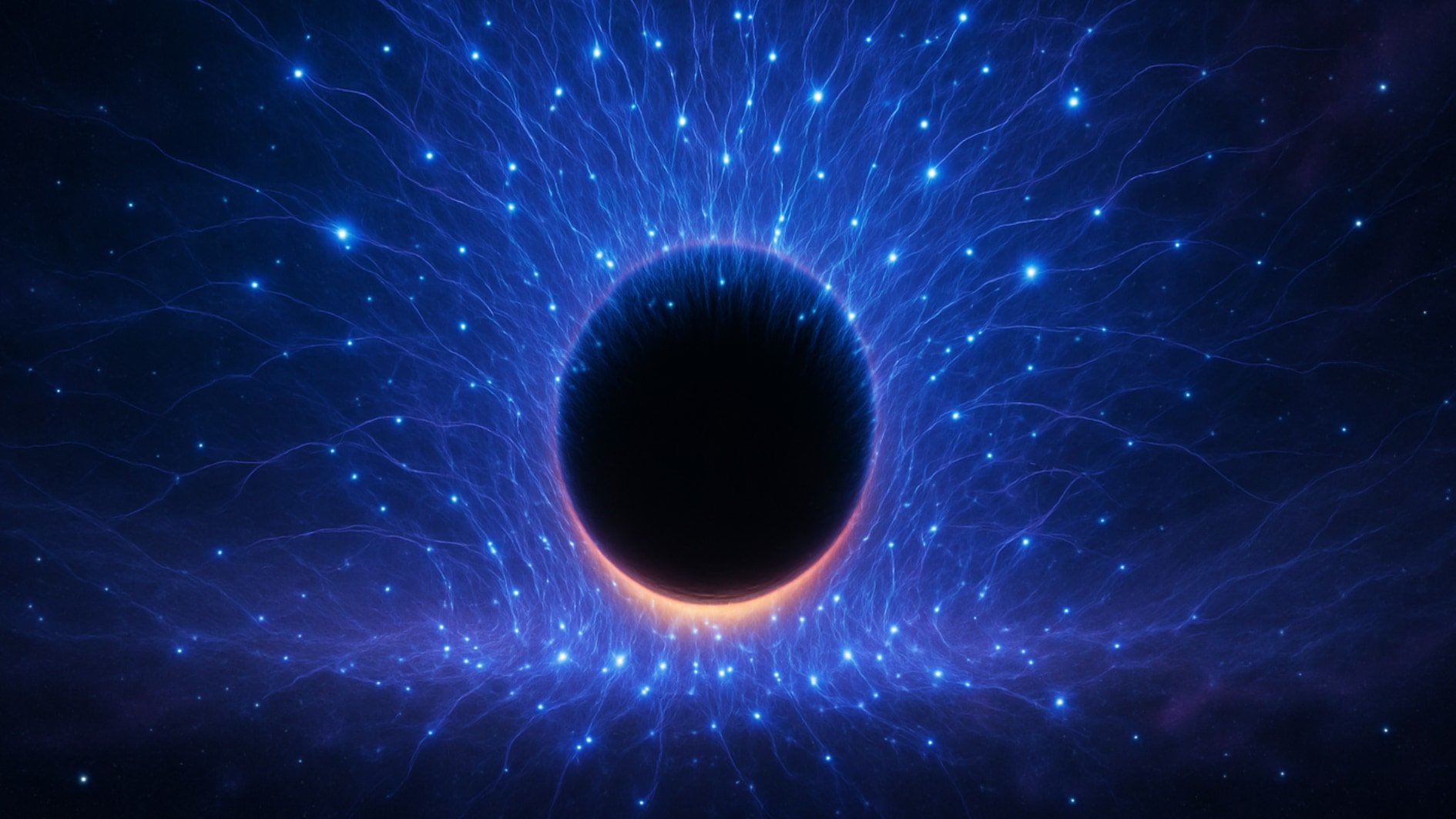






















![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)