努力では解決できないADHDの“脳のちがい”が見えてきた
TS法を用いた今回の研究では、ADHDの子どもたちとそうでない子どもたちの脳を、これまでにない精度で比べることができました。
その結果、ADHDの子どもたちの脳には、実際につくりの違いがあることがはっきり示されました。
特に大きな違いが見つかったのは、「中側頭回(ちゅうそくとうかい/Middle Temporal Gyrus)」という部分です。
この場所は、ものごとに注意を向けたり、情報を整理したり、感情をコントロールしたりする働きを持っています。
ADHDの子どもたちでは、この中側頭回の灰白質の体積が少し小さくなっていました。その差は統計モデルでも偶然ではないと確かめられています。
同じような傾向は、脳の前の部分である「前頭葉(ぜんとうよう/Frontal Cortex:大脳皮質の前部)」や「側頭葉(そくとうよう/Temporal Cortex:大脳皮質の側部)」にも見られました。
これらの領域は、注意や計画、気持ちの切り替えといった、人間らしい思考や行動のコントロールに深く関わっています。
ADHDの特徴的な行動や感じ方は、脳の構造の違いと結びついている可能性が高いということが、今回の研究で科学的に裏付けられました。
このように脳構造の違いが原因と言われると、「ADHDはすべて生まれつき決まっている」と考える人もいるかもしれません。
しかし脳の形や大きさには、遺伝の他に、成長過程や子ども時代の経験や環境も関係してきます。
たとえば、生活習慣やストレス、学びの機会など、さまざまな要素が脳の発達に影響を与え脳構造を変化させることはよく知られています。
このため、ADHDを「先天的な脳の病気」や「持って生まれた運命」と単純に決めつけるのは早計で、後天的に生じる可能性も十分にあるのです。
大切なのは、ADHDは努力不足や怠けで生まれるものではなく、脳そのものの特徴が関わっているという最新の科学的な視点です。
実際、今回のように脳の構造を詳しく調べる研究が進むことで、ADHDの早期発見や、一人ひとりに合ったサポートの開発も期待されています。
今後はさらに多くの子どもや大人を対象に、国や文化の違い、成長にともなう変化まで含めて調べていくことが課題となります。
脳科学の進歩によって、ADHDの理解は大きく変わろうとしています。
子どもや周りの人を「なぜできないのか」と責めるのではなく、「どうすれば力を発揮できるか」「どんなサポートができるか」を一緒に考えていくことが、これからの社会でますます重要になっていくでしょう。この研究は、そうした未来への一歩となる成果です。




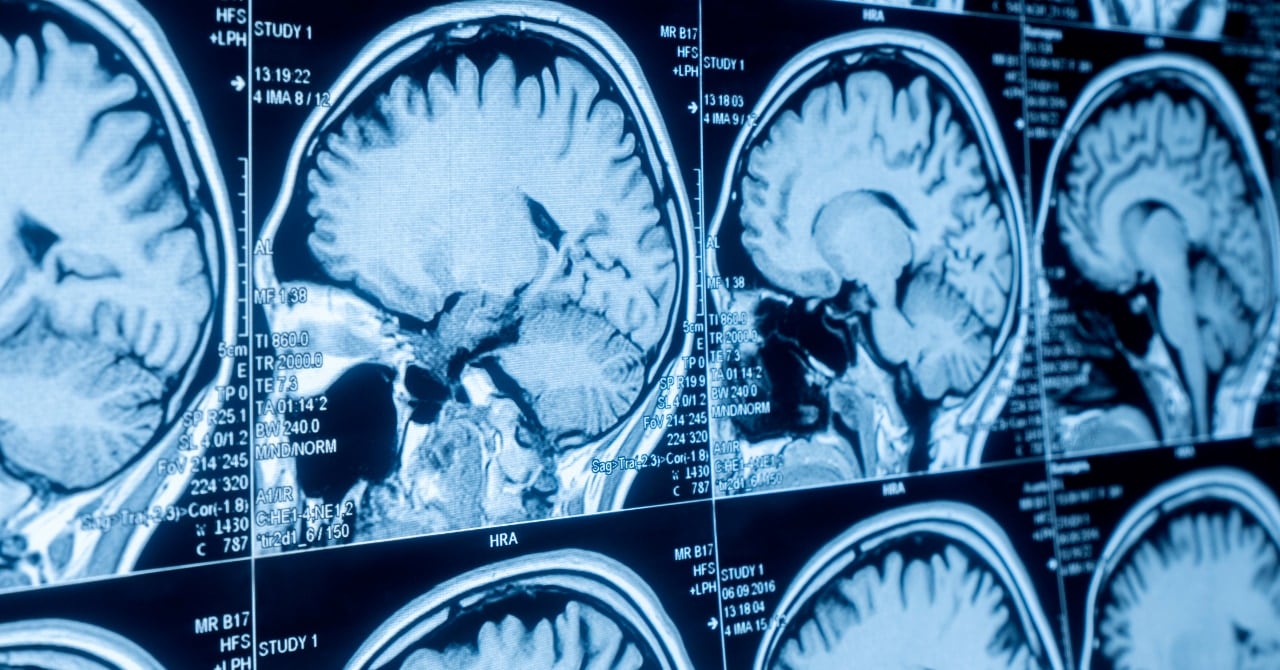























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)
![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)



















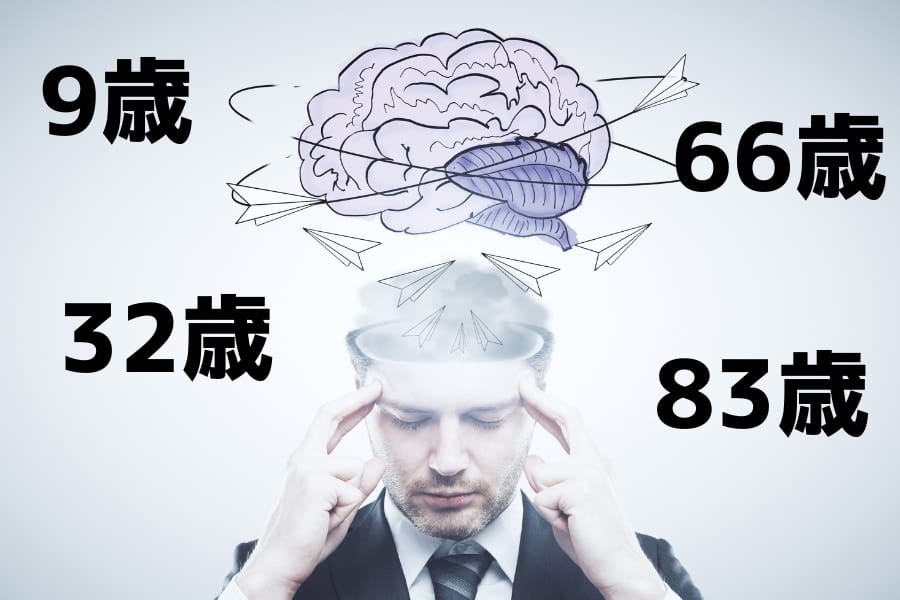








甘えではなく脳の構造の違いということがわかって良かった。だが脳の作りが少し違うだけでこんなにも生きづらくなるのだろうか?
そりゃそうだろ。世の中全部が正常な人間を基準に作られてるんだからな
日本人の頭蓋骨は上から見ると円に近い形だけど、ヨーロッパ系の人々は前後に長い楕円形が多いように見えます。日本国内のMRI装置間で補正できたとしても、欧米の研究での画像と対照するのは大変そうです
後天的に脳に異常が生じる場合があるとなると、結局「本人の努力不足や家庭環境のせいで脳が変化した→本人の甘えや親の教育が悪い」ということを言い出す人がいそう。
ここ10年ほど前から増えてるとなるとYouTubeやショート動画ばかり見て育った結果かなと思うが
そう思う。特にショート
それもあるかもしれないけれど、ADHDの存在を知る人が多くなってきた事も関係する気がする。こんなにも流行るとは思わなかった。増えたから流行ったのかもしれないけど。。。
ここ10年で増えたってデータはどこから?発達障害者支援法の改正が2016年で行政から支援受けやすくなって診断数が増えたんじゃねえの。
日本は島国なので、海洋マイクロプラスティックの問題が大きそうですね。
…ですよね
じゃなければあんなに毎日忘れ物したり、散らかして平気なわけがない
本当に当事者なら平気じゃないですね。ありとあらゆる方法を試したり、忘れ物とか散らかった部屋に絶望と後悔を感じてるのに怒られてしまい、自分でもなんとかしたいと頑張るけどまだできなくて、自尊心がなくなるかわりに緊張が増えて、パフォーマンスも更に落ちて、それでまた怒られて・・。ADHDは共感したり人の感情に敏感でもあったりするので人に迷惑かけてることも人一倍分かるけどどうしようもないので全く平気ではなく、何とか相手の負の感情を宥めようとまた違うエネルギー使って疲れ果ててまた失敗して、みたいな。お薬とか支援で何とかなっていった時、本当に【え、定型の人ってこんなに疲れないで済むの?こんな緊張も不安もない世界って心が軽いんだ】って人生変わったように感じたりするものです。
研究結果、ADHDの理解・支援に一歩前進、期待しています。
しかし、コメント欄を見ると、世間の理解を得るには、研究よりも困難を伴うことが予想されます。マスメディアの理解協力も不可欠ですが、現状マスメディアもSNSもデマの拡散という意味では期待できません。
それでも研究を進め、新しい支援の形を模索し、繰り返し広報に務めるしかないのですが。研究者の皆様、期待しています。
脳が違うってつまりは、それもそれで、どうしようもないが偏見とも言えちゃう
全然努力せず、環境のせいにする奴はダメだとすることもできる
それが当たり前だとして良い面は、社会全体としてあるのだろうと思う
ADHDだと判明すれば、環境を変える必要があるように、その人への対処が変わる
このメカニズムが、ADHDの診断を欲しがる人が多い現象の原因で
つまりは、ADHDと診断してほしいという人や、自称ADHDは、努力をしないことの正当化
を目指しているとできる。
ADHDに対する偏見もそうだけど、この、ADHDを守る仕組みの逆利用が厄介
努力なくしてできるタイプも、ADHDを気取ってるんじゃないかと、叩かれる対象になる
出る杭は打たれるという、よくあることの一部としても、この逆利用はありえちゃってる
根性論?よ消えなさーい