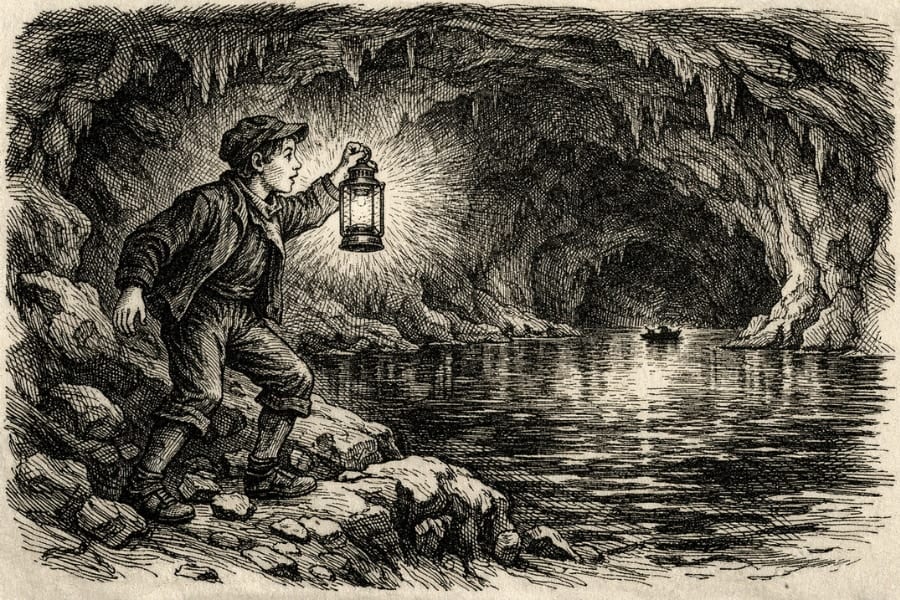銅の大釜に眠った2万枚の銀貨

人がスコップで偶然発見した銀貨の話が伝わると、ストックホルム県行政庁の専門チームがすぐさま駆けつけ、発見現場を緊急調査しました。
具体的には、財宝が埋まっている場所を丁寧に掘り進めて、中から出てきた銀貨や装飾品を一点ずつ傷つけないよう慎重に取り出し、きちんと記録していったのです。
この慎重な作業は、手術で医師が患者の体内から大事なものを取り出すようなイメージですね。
さらに驚くことに、この財宝はかなり大きな銅製の釜の中にまとめて入れられたまま埋められていました。
釜自体は土中で長い年月を経てボロボロになっていましたが、中の銀貨や装飾品はほとんどが良い状態で残されていました。
発見した人がすぐに専門家に知らせたことが幸いし、貴重な歴史遺産は安全に回収され、丁寧な調査に回されることになりました。
調査の結果、財宝の中心を占める銀貨の多くが12世紀(1100年代後半頃)に作られたものであることがわかりました。
中でも特に専門家たちの関心を引いたのは、一部の銀貨に刻まれていた「KANUTUS(カヌートゥス)」という文字でした。
これはラテン語で「Knut(クヌート)」、つまり当時スウェーデンを統治していた国王クヌート・エリクソンの名前を示しています。
このクヌート国王は12世紀末の重要な王で、この刻印のおかげで、財宝が埋められたのは12世紀末ごろではないかと考えられています。
しかし、この財宝に含まれていたのはスウェーデン産の銀貨だけではありませんでした。
当時のヨーロッパでは、さまざまな地域で個性的な銀貨が作られ、広く流通していました。
今回見つかったものにも、ヨーロッパ各地から集まってきたと思われる珍しい銀貨が混ざっていたとされています。
特に目を引いたのは「司教貨」というちょっと特殊なコインでした。
これは当時のカトリック教会の司教が自分の名前で発行していた銀貨で、司教が手に持つ曲がった杖(司教杖)をデザインとして使っているのが特徴です。
今回発見された財宝の中には、この司教貨が複数枚含まれており、宗教的にも経済的にも非常に珍しい発見となりました。
また、銀貨だけではなく、美しい装飾品の数々も見つかっています。
銀製の指輪やペンダント、ビーズ(pärlor)で飾られたものなど、多種多様な装飾品が一緒に収められていました。
さらに、フィリグリー(細い銀線をより合わせて模様を作る技法)の装飾があったことも報じられています。
こうした財宝の組み合わせを見ると、これが単なるお金の集まりではなく、長い時間をかけて受け継がれてきた貴重品だった可能性もあります。
まるで「タイムカプセル」のように、12世紀の人々の生活や価値観を閉じ込めていたのかもしれません。
さて、ここで当然浮かぶ疑問がありますね。
「なぜこれほどの宝物をまとめて土の中に埋めたのか?」ということです。
考古学者たちは、財宝の置かれ方や周辺の土壌の様子まで詳しく調べ、この謎を解き明かそうと今も現場で調査を続けています。
特に今回のように大きな釜に財宝を入れて埋めるというやり方は、中世ヨーロッパでは戦争や災害から大切な財産を守るため、あるいは神様への捧げものとして奉納する目的で行われることがありました。
この「大釜にいっぱいの銀貨」という光景を見た考古学者の一人は、「まるで虹の端に眠る宝物を本当に見つけてしまったような気分だ」と語っています。
言い換えると、この財宝はただのお金や宝石というだけでなく、当時の誰かが未来に向けて特別な想いを込めて地中深くに封じた「心のこもった宝物」だったのかもしれません。
そう考えると、この偶然の発見は単なる幸運ではなく、過去から現代への大切なメッセージを伝える出来事だったとも言えるでしょう。












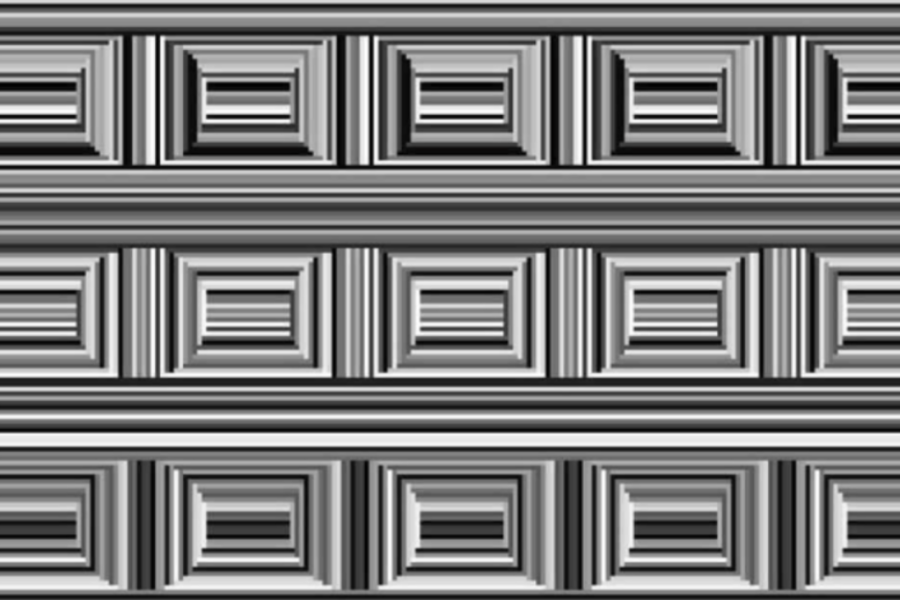
















![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)
![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)