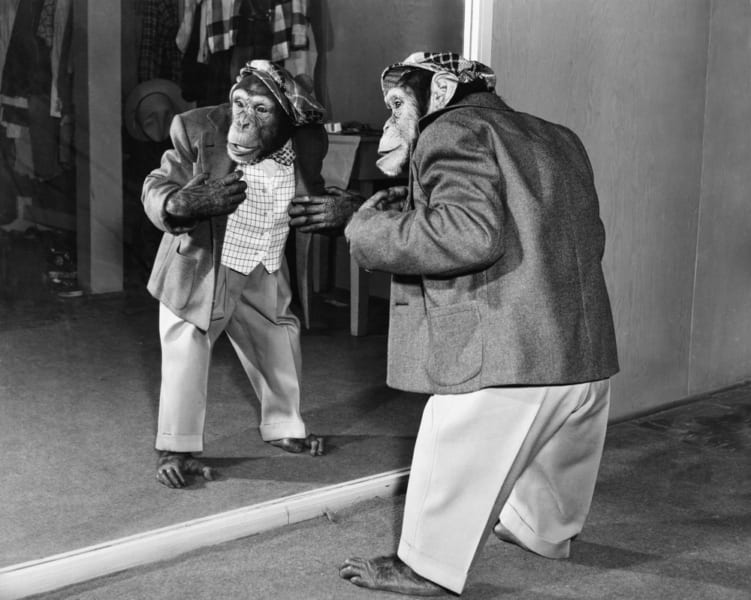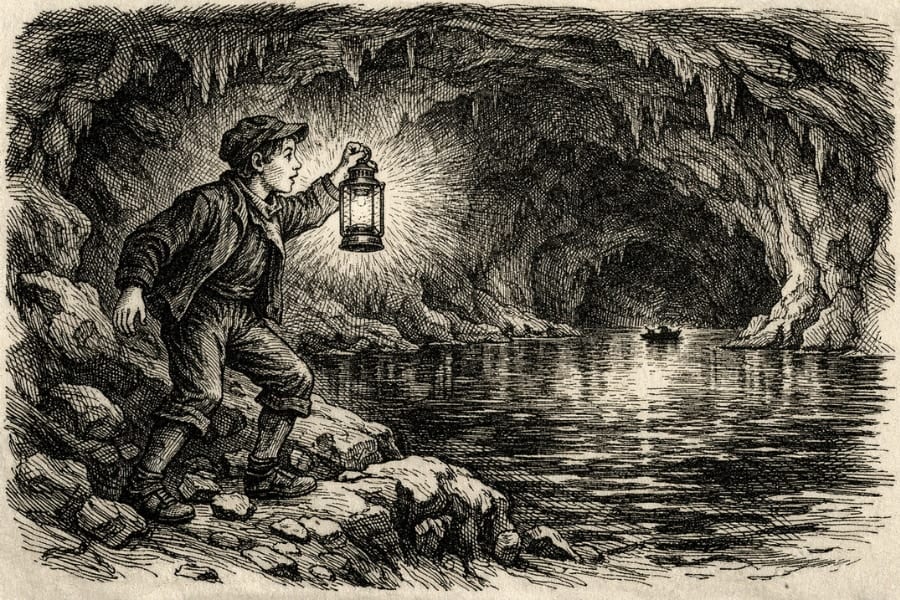小さな魚が持ち歩く「刺すパートナー」

研究チームがまず行ったのは、2018年から2023年までの5年間、フロリダ沖(アメリカ)やタヒチ沖(仏領ポリネシア)で撮影された膨大な夜間潜水の写真を丁寧に分析することでした。
さて、問題の写真には、体長わずか数ミリから数センチという、とても小さな魚たちがたくさん写っていました。小指の爪より小さいような幼魚たちです。
彼らが何の種類の魚なのかを特定するためには、ヒレの形や棘の数、体の模様といった細かな特徴を手がかりにします。ちょうど人間の指紋で個人を見分けるように、小さな魚たちにもちゃんと識別できる目印があるのですね。
そんな風に写真をよく調べてみた結果、4つの異なる「科」(魚の種類を大きく分けるグループ)の幼魚が、漂うイソギンチャクの幼生とセットになっていることが分かりました。
それが、アジ科・マナガツオ科・アリオマ科・カワハギ科の幼魚たちでした。
しかも、それぞれの幼魚がイソギンチャクを利用する方法もさまざまでした。
カワハギの幼魚は、小さなスナギンチャク科(パリトア属)の幼生を口にくわえて運び、自分の身を守るように泳ぎ回っていました。
また、アリオマ科の幼魚はチューブイソギンチャク(細長い筒状のイソギンチャク)の幼生に寄り添いながら、まるでボディガードに護衛されるようにしていました。
さらに興味深かったのは、マナガツオ科(Brama)の幼魚のケースです。
彼らもイソギンチャクの幼生を口にくわえていましたが、中には腹ビレ(お腹の部分にある小さなヒレ)で幼生を抱えるようにして「乗り物」のように使っている魚もいました。
まさに「動く武器庫」のような使い方をしていたわけです。
最も印象的な行動を見せたのが、カワハギの仲間です。
この幼魚はイソギンチャクを口にくわえたまま活発に泳ぎ回り、研究者が観察のために近づいた際にも防御のような姿勢を取る様子が見られました。
そして、しばらくして幼魚がイソギンチャクを放して泳ぎ去ったあとも、そのイソギンチャクには傷がありませんでした。
まるで幼魚が力加減を心得ているかのようですね。
また、アジ科の幼魚(Caranx cf. latus)も興味深い行動を見せました。
ダイバーが近づくと、自分とダイバーの間にチューブイソギンチャクの幼生がくるように素早く位置取りを変え、生きた盾のように使っているように見えました。
ここで疑問がわきます。
「そんな小さなイソギンチャクが盾になるほど強力なのか?」と。
実は、イソギンチャクの幼生も小さいながら「刺胞(しほう)」という小さな毒針を持っていることがあります。
もちろん、この毒は大型の捕食者を倒せるほど強烈ではありませんが、魚の赤ちゃんを食べようとする相手に対して「これを食べると痛い目に遭うぞ」と思わせるには十分な刺激になるかもしれません。
例えば、辛すぎるトウガラシを一度かじってしまったら、次からはもう食べようとは思いませんよね。
幼魚にとっては、このイソギンチャクがまさに「小さな電気クラゲ」のような存在として役立っていると考えられます。




























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)
![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)