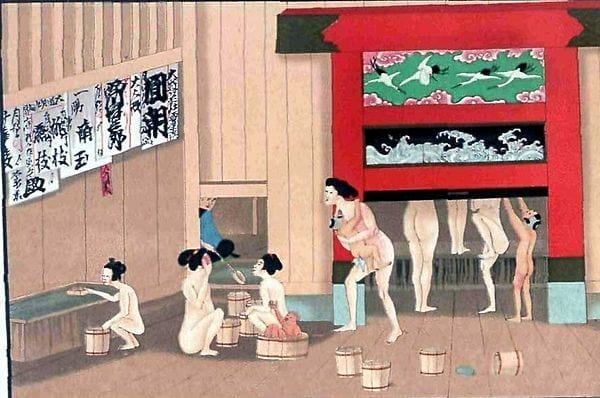世界最初の「鳥類の家畜化」の可能性も
本研究で対象としたのは、約1万8000〜6000年前のヒクイドリの卵、計1000個以上の断片です。
卵殻サンプルを分析し、データをまとめた結果、大半の卵殻がヒナの孵化直前か直後に当たることが分かりました。
遺跡で見つかる鳥の卵は、基本的に人々が食用にしていたものだと考えられます。
しかし、その場合、卵殻の痕跡は孵化のずっと前の状態となっているはずです。
なぜ、今回遺跡から見つかったヒクイドリの卵の殻は、多くが孵化直前の状態だったのでしょうか?
ここから予想されるのは、当時のニューギニア人が、ヒクイドリの生卵を食べず、孵化直前のヒナを加熱して食べていた可能性です。
孵化直前のヒナを食べるというのは、馴染みのない地域の人にとっては少しショッキングな食べ方ですが、東南アジアの広い地域で「バロット」という名で親しまれています。
しかし、卵殻の焼け具合を調べたところ、その多くに加熱の痕跡がない事がわかりました。
これは当時の人々が、ヒクイドリをそのまま孵化させていた可能性が高いと考えられます。

そこで、研究チームが考えたもう一つの可能性が、ヒクイドリの飼育です。
卵を孵化させるためには、ただ内容物を食べるためだけに卵を収穫していては実現できません。
これはこの時代の人々が、意図的に孵化させることを目的として卵を集めていた可能性があることを示唆しているのです。
これは驚くべき事実です。
ダグラス氏は「この結果は、人類による鳥類の家畜化を示す世界最古の例であり、ニワトリやガチョウの家畜化に数千年以上も先行していると考えられる」と述べています。
ただし、当時の飼育環境や技術を踏まえると、ヒクイドリを集団で家畜化するのは難しく、危険もかなり多かったはずです。
それでもヒクイドリを飼育していたとすれば、どんなメリットがあったのでしょうか。
もしかしたら、番犬ならぬ番鳥として居住地の見張りをさせていたのかもしれません。





























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)