「忘れる」ことの意味とは?ハエから線虫の研究へ
私たちの脳は、毎日膨大な情報を受け取っています。
だからこそ「忘れること」は、脳が“本当に必要な情報だけ”を選び残すために必要です。
しかし、こうした「忘却」という現象が「どのような仕組みで起きているのか」については、長年ほとんど分かっていませんでした。
「不要な記憶が消される」プロセスも謎にに包まれていたのです。
ところが近年、ショウジョウバエ(Drosophila melanogaster)の研究で「忘れることは受動的というよりも、神経回路の働きによる能動的なプロセスである」ことが示されました。
特にハエの脳では「ドーパミン」という神経伝達物質が忘却に関与していました。
ドーパミンといえば、快感・喜び・意欲・運動・学習に関わっていることで有名です。
では、この仕組みは本当に他の生き物やヒトにも共通するものなのでしょうか?
そこでフリンダース大学の研究チームは、「線虫(Caenorhabditis elegans)」という極めてシンプルな動物モデルに注目しました。
線虫は体長1ミリ程度、わずか300個の神経細胞しか持たないにもかかわらず、ヒトと約8割もの遺伝子を共有しています。
分子レベルでも多くの共通点があるため、脳の基本原理を調べるのに適した生き物です。
実験では、線虫に「特定の匂い」と「エサ」を組み合わせて覚えさせ、どれだけ長くその匂いを“エサの手がかり”として記憶し続けるかを測定しました。
同時に、ドーパミンを作れない変異体や、特定のドーパミン受容体が壊れた変異体など、様々な遺伝子改変株を使い、ドーパミンと忘却の関係を徹底的に調べ上げました。



















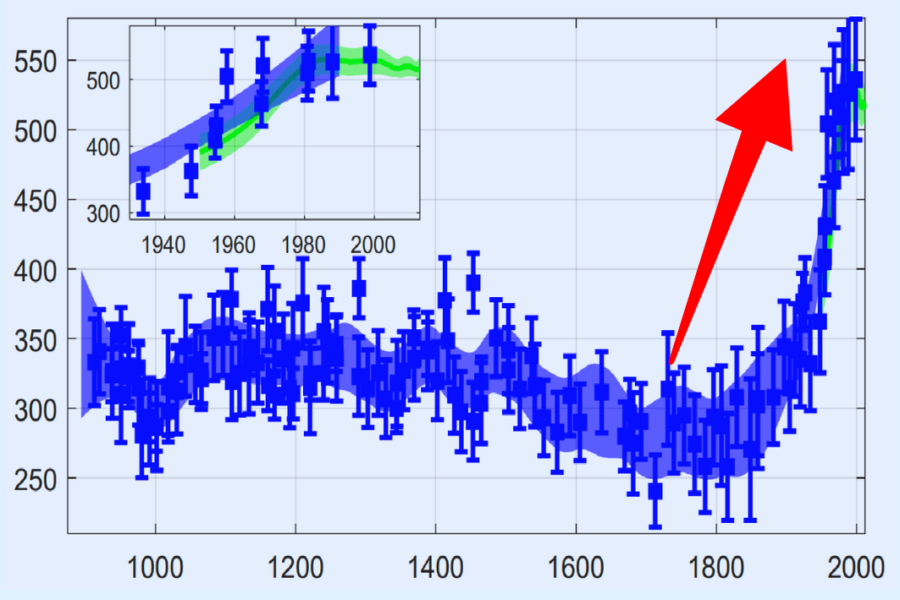

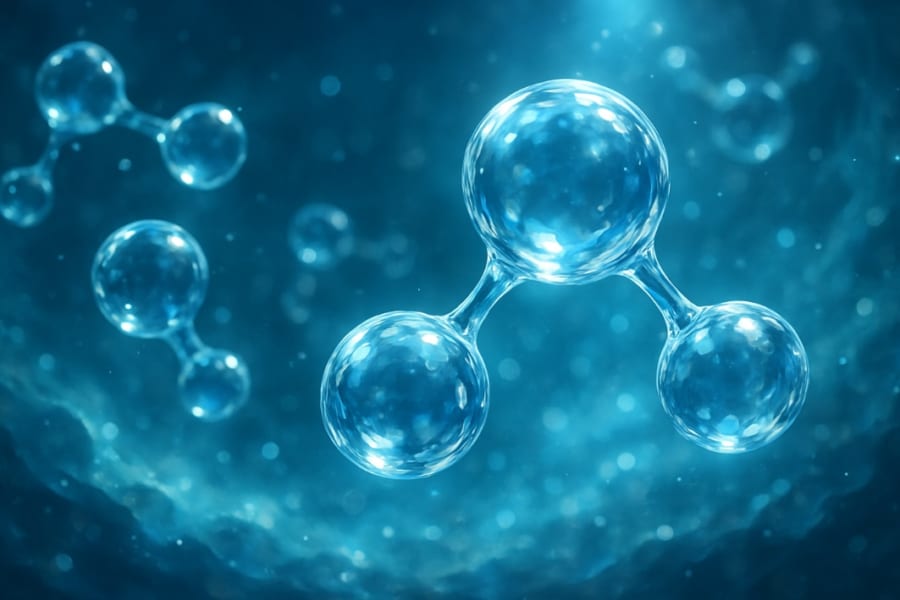



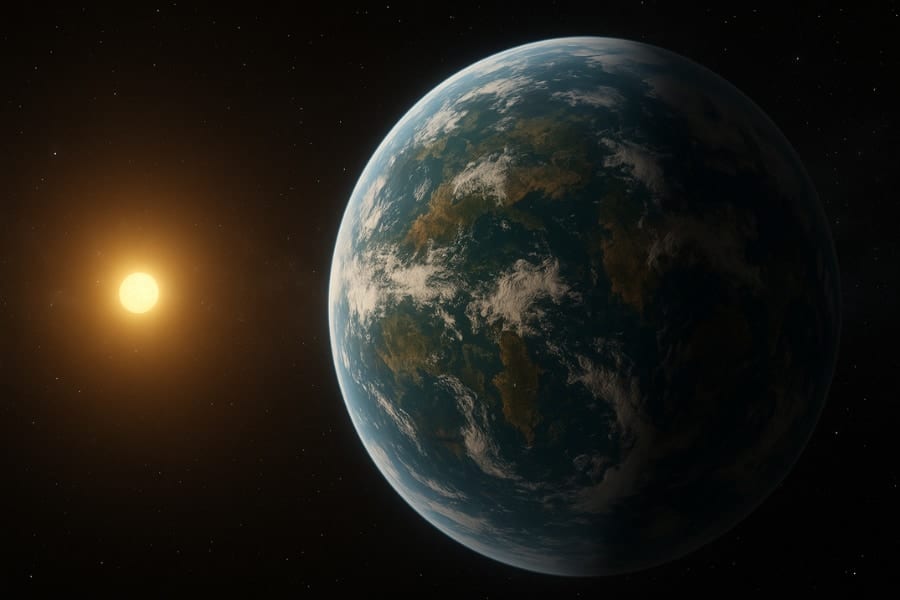







![【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 知育玩具のシルバーバック 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)
![ラボン(Lavons) 柔軟剤 特大 シャイニームーン[フローラルグリーン] 詰め替え 3倍サイズ 1440ml](https://m.media-amazon.com/images/I/41ze0Blp9fL._SL500_.jpg)



























