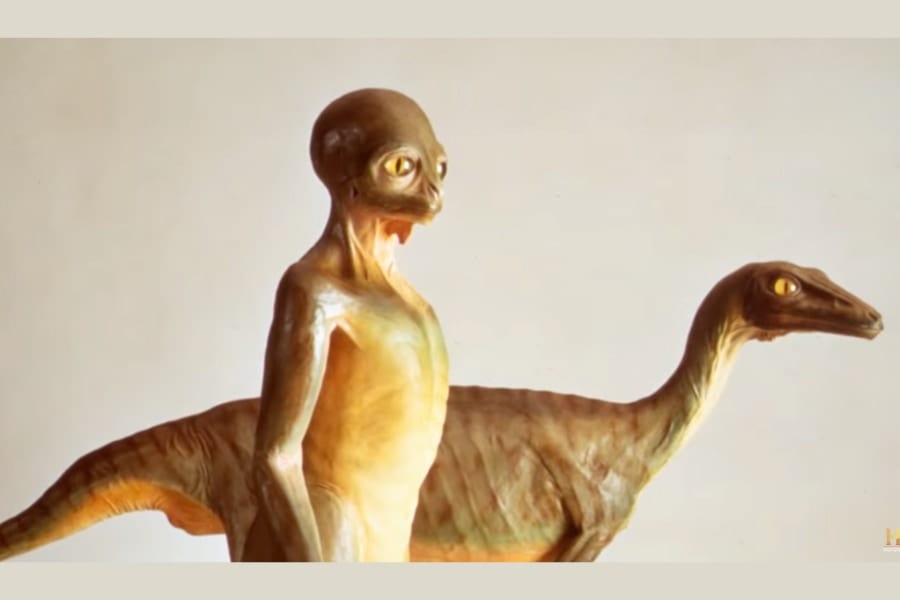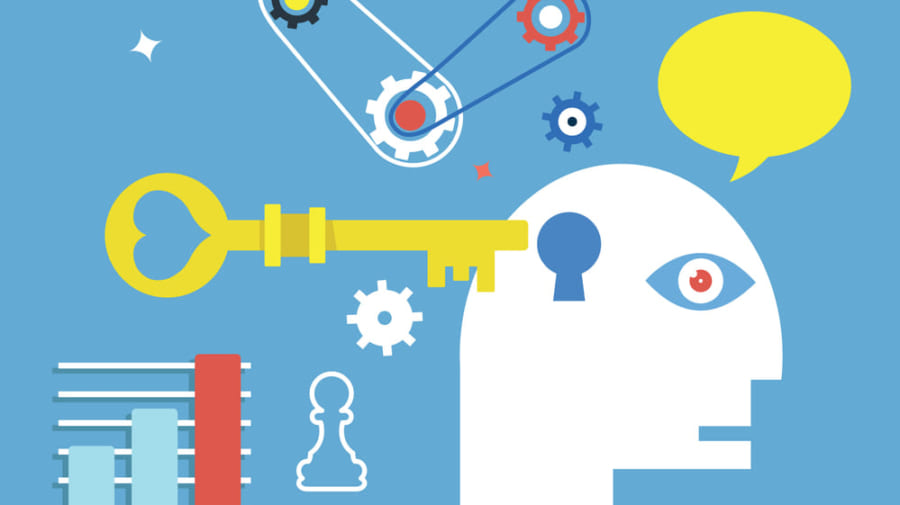ラプトルの鉤爪はどんな用途で使われたのか
ヴェロキラプトルは約8300万〜7000万年前の東アジアに生息していた小型の肉食恐竜で、ユタラプトルやミクロラプトル、デイノニクスといった他のラプトル類と共に「ドロマエオサウルス科(Dromaeosauridae)」に分類されます。
ドロマエオサウルス科の恐竜はジュラ紀(約2億130万〜1億4550万年前)に登場し、白亜紀(約1億4500万〜6600万年前)の前期〜後期にかけて繁栄しました。
俊敏性に長けた細い体が特徴的ですが、最も注目すべきは後肢の第2指が発達した鋭く大きな鉤爪です。
古生物学者の間では、この鉤爪が獲物を「切り裂く」攻撃用に使われたとする意見が多くを占めています。
その説を支持しているのが、1971年にゴビ砂漠(モンゴル)で見つかった「ヴェロキラプトルとプロトケラトプスの闘争化石」です。

この化石は、2頭が争ったまま砂丘の崩落か砂嵐に巻き込まれて同時に息絶えたと考えられています。
両者は互いに致命傷を負わせており、特にヴェロキラプトルは相手の首の辺りへ鉤爪を命中させていました。
それゆえ、揉み合いの中で鉤爪が攻撃に使われたことは確かでしょう。
一方で、ドロマエオサウルス科の鉤爪は「湾曲して丸みを帯びており、肉を切り裂くような切断には向いていない」とする研究報告もあります。

そうした研究から「鉤爪は攻撃を主要な目的とはしておらず、他の使い方があったのではないか」とする声が出てきました。
さきほどの闘争化石についても、たまたま鉤爪が突き刺さってしまっただけで、切り裂くことはできなかったと見られます。
しかし、恐竜たちはすでに絶滅してしまっているため、生きた行動例は調査できません。
そこで研究チームは今回、南米の捕食鳥として知られる「アカノガンモドキ(学名:Cariama cristata)」を調べることにしました。
































![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)