泳ぐ「スピード」も、主食に関係している

では、体が小さいイルカやシャチは、プランクトンで十分な栄養を摂取できないため、泣く泣く魚を食べているのでしょうか?
いえ、彼らには「スピード」という武器あるため、プランクトン以外の生物を狩ることができます。
そのため、プランクトンよりも大きな魚を狙うことができるため、それらを主食にしているのです。
一方で、シロナガスクジラの泳ぐスピードはどうでしょうか?
体が大きくなった分、彼らは俊敏な動きをすることができません。そのため、速く泳ぐ魚を狩るのは不得意としています。
捕まえるのが不得意な魚を主食としてしまったら、どうでしょう?
彼らは自分の大きな体を維持するためのエネルギーが十分に得られず、飢え死にしてしまうでしょう。
つまり、大きな海洋生物は俊敏な動きができないため、「プランクトンでないと、捕食できない」という理由もあるのです。
大きい動物、小さい動物の主食の比較

「体の大きい生物ほど、個体数が多く、動かないものを主食としている」法則は、実は陸上でも同じです。
例えば、ライオン、チーター、ゾウ、サイ、スイギュウのうち体が大きいのはどの動物でしょう?
そうです、ゾウ、サイ、スイギュウなど後者の動物になります。
彼らは、草を主食とする草食動物なのです。体の大きなジンベエザメ等と同じように、量が豊富にあり、動きも少ないものを主食にしているということです。
一見、「体の大きな生物ほど、小さい生物を食べる」というのは効率が悪いように感じますが、むしろ身体が大きいと効率が良くなる食餌方法なのです。
単純に生物の身体のサイズと、食べているもののサイズだけを比較すると不思議な話に思えます。
しかし、その餌がどれだけ獲得しやすいか、そしてどうすれば効率よく食べられるか、という点に目を向ければ身体が大きいほどプランクトン食になるというのは不思議なことではなくなるのです。





























![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
















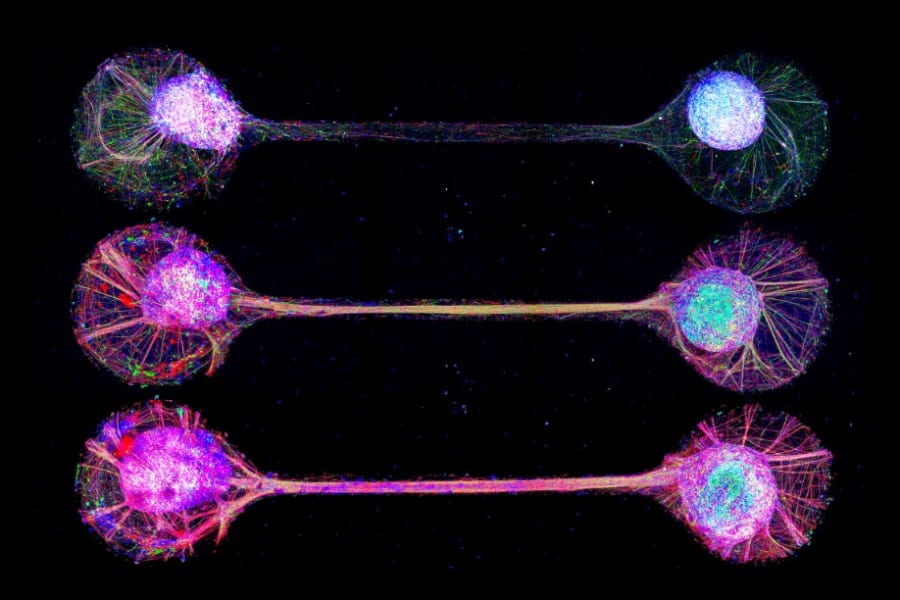











知識を得たくて記事を読むのに、
質問がナンセンスは、その言い方自体がナンセンスだわ
よく食べることが大事であると。
食べられてばかりのプランクトンさんにも活躍の場をですね。
記事の説明を採るとすると、セミクジラ成獣よりも体の小さいヒゲクジラの幼獣は、物理的に必要な量の餌を補給できないことになります。一方で、体表面積/体重比や体組織の代謝レベルの違いから、成獣に比べてカロリー補給に励む必要がありそうです。
マンボウ成体は、クラゲなどを捕食しているそうですが、幼体は甲殻類や小型の魚も捕食するとのことです。ひげクジラ類も、成獣と幼獣で、狙うプランクトンの種類が違うかもしれませんね。
マンタとかウバザメは?と思ったけど哺乳類と魚ではまた必要エネルギーが違うか
文章が「〇〇になります」の誤用の口語体が多くて、内容とミスマッチで読みにくいかな。