7000年間、孤島で近親交配を続けたトナカイの一族
舞台は北極圏にあるノルウェー領の群島として知られるスヴァールバル諸島です。

この極寒の地には、島の固有種として「スヴァールバルトナカイ」というトナカイの一種が生息しています。
最初のトナカイは約7000〜8000年前にロシアの島々を経由して、スヴァールバル諸島に入ってきました。
それ以来、他種のトナカイとは完全に隔離された状態にあり、7000年以上の期間を近親交配を繰り返しながら島で生き続けています。
研究主任でノルウェー科学技術大学のニコラス・ダセックス(Nicolas Dussex)氏は「すべてのトナカイの種の中で、スヴァールバルトナカイは最も近親交配が進んでおり、遺伝的多様性が最も低いことが分かっている」と話します。
にもかかわらず、本種の個体数はここ数十年で急速に増え続けており、現在では約2万2000頭を突破するまでになっているのです。

さらに、寒さの厳しいスヴァールバル諸島への適応にも成功しています。
例えば、他種のトナカイに比べて短足になっているのですが、これは体熱が逃げるのを抑える効果があると考えられます。
またトナカイの主食である地衣類の他に、さまざまな植物を消化する能力があったり、同島の極端は季節変化に合わせて体内時計を調節する能力も身につけています。
近親交配が深刻化しているのに、彼らはどうしてこんなに絶好調なのでしょうか?
有害な遺伝子を一掃する「浄化」が起こっていた!
研究チームはその秘密を探るべく、特に近親交配の進んでいるスヴァールバルトナカイの群れ91頭を対象に、遺伝子調査を行いました。
その結果、これらのトナカイは過去に、有害な遺伝子をコロニーから一掃させる「遺伝子の浄化(Genetic Purging)」を起こしていたことが分かったのです。
これは一体どういうことでしょうか?

近親交配が高度に進んだコロニーでは、両親から有害な遺伝子を受け継ぐ可能性が高まり、それが顕性遺伝子として表に現れやすくなるのでした。
こうした有害な遺伝子は、先天性疾患や健康状態の悪化として発現します。まさにカルロス2世のように。
すると、これらの個体は遺伝的な適応度が低下するせいで、繁殖の機会を得る前に死亡するか、繁殖しても子孫の数が少なくなるのです。
何とか生まれた子孫も同じように遺伝的適応度が低いため、繁殖する前にどんどん数が減っていきます。
一見すると個体数が減っているようですが、実はこのおかげで有害な遺伝子が子孫に受け継がれる確率も減少するのです。
これを「遺伝子の浄化(Genetic Purging)」と呼びます。
浄化が起こる前は個体数の激減が見られますが、表面的には種のピンチに見えて、本当は危険な遺伝子を取り除いている過程でもあるのです。
スヴァールバルトナカイも19C後半〜20C初めに一度、絶滅寸前に追い込まれていますが、その後に急速に数を増やしました。
同じ現象はニュージーランドに生息する「カカポ(学名:Strigops habroptilus)」でも確認されています。

カカポは1万年もの間、島に隔離された状態で近親交配を進めており、1995年には60羽まで激減。
しかし現在は200羽を超えるほど回復しています。
研究主任のダセックス氏は「近親交配は長期にわたって高度に推し進められると、種の繁栄にとって有益に働く可能性がある」と述べました。
トナカイもカカポも近親交配で訪れる一番の峠を越えたと言えるのかもしれません。




























![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)



















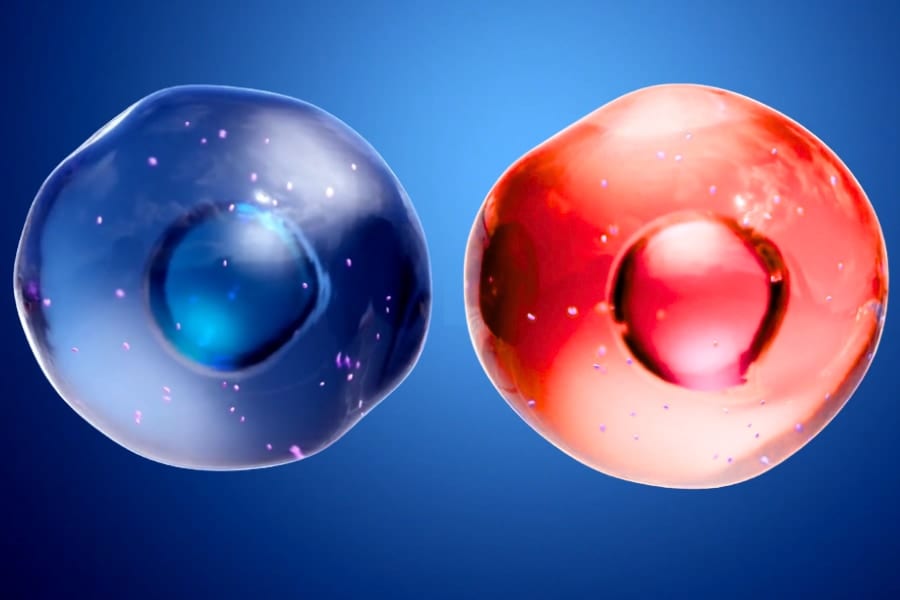

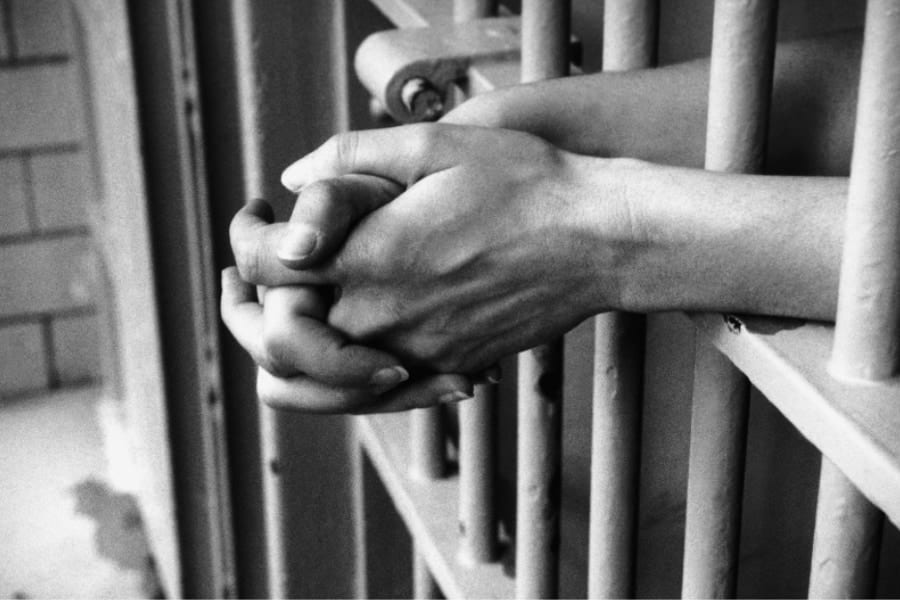






日本犬の紀州犬も血筋を調べ辿ると一頭の雄犬の血が必ず入っているらしい。
(過去にその犬の血が入ってない紀州犬が欲しくて必死に調べてた先生がいた。
先生によると近親交配で産まれる特殊な犬と言っていました。)
説明が間違っているように思います。
1ページ目に
>遺伝子の中には、生存に不利に働く(中略)それが顕性(優性)遺伝子として子供の体に現れやすくなるのです。
とありますが、潜性遺伝子が顕性遺伝子“として”(つまり変化して?)現れるわけではないと思います。
2ページ目も
>近親交配が高度に進んだコロニーでは、(中略)それが顕性遺伝子として表に現れやすくなるのでした。
と、1ページ目の間違った前提に基づいて、潜性と顕性を取り違えて書かれているので、もしかして記事を書かれた方は間違って理解しているのかと思い、ご指摘させて頂きました。
確かに、潜性遺伝子のホモ型だと表現形に病的な有害形質が発現するってことで、潜性が顕性になる、ってことではないよね
たしかにそうですね
潜性遺伝子、顕性遺伝子は別個のものですよね
この話が本当なら、以前の記事で紹介されていた、1組の男女から種は繁栄するか、という内容について、さすがに1組は極端でも、ある程度の組がいれば優秀な遺伝子だけで繁栄することが可能と言えるようになりますね。
そのことを「最小存続可能個体数」と呼びます。
ようするにハプスブルク家は近親交配を短期間で進めすぎたために
有害な遺伝子(主に、潜性=劣性)が表現型として現れる率が高まりすぎて滅亡した。
一方でトナカイやカカポは近親交配でありながら7000年~1万年かけて有害な遺伝子を徐々に取り除いた。
また、初期集団もおそらくハプスブルク家のような極端な少ない数からではなかったというのもポイントだろう
適者生存の原則の前には近親交配も膝をつくことになると。
カカポが激減したのは人間が島に上陸したため。
その後人間による保護活動で数が増えたと本で読んだことがあるのですが。
現代の技術であれば、昔のハプスブルク家の数多くの失敗やトナカイ、カカポなど何万年などと長い年月を要さずとも遺伝子の浄化の短縮化は可能。
詰まるところは効率的な組合せであり、詳細な検査も必要だが2022年の論文でヒトゲノム解析完了したのでその成果も大きい。
後は倫理的な安楽死の問題さえ解決すれば生まれる前の検査後に処分が可能となりさらに容易となる。
更に研究が進めば安楽死すら必要無くデザイナーベビーの様にピンポイントでの編集も可能となるので第一世代、第二世代と短期間での遺伝子の浄化が済む事も容易に想像が出来る。
UNIVERSE25と言う、4組(8匹)のネズミが25回とも繁殖・増殖後、絶滅すると言う結果が得られたと言う実験がありますが、トナカイの件、個人的には生きた化石と言われるシーラカンス等、どうして絶滅していないのか、その違いが気になるところではあります