朝練習を取り入れながら競技力を高める学生アスリートの特徴
前に説明したイギリスの学生アスリートを対象とした調査では、対象者は、週末にはスポーツ活動や授業が計画されていませんでした。
そのため、平日と週末の睡眠サイクルにバラつきが生まれやすかったと予想されます。
エリートラグビー選手を対象としたある研究では、睡眠の規則性を表す指標であるSRI(Sleep Regularity Index)というスコアが悪い人は、睡眠時間が短いことが示されており、睡眠に一貫性のないアスリートは、睡眠問題を抱えている場合が多いです。
したがって、例えば、平日も週末も午後9時に寝て、午前5時に起床するといった一貫した生活リズムを確立することができれば、朝練習を取り入れても、良質な睡眠を確保しやすいと考えられます。
箱根駅伝の強豪校の中には、門限や消灯時間を定めた上で寮生活を送りながら朝練習を行っているチームがあります。
これらは、朝練習を含めた日々の規則正しい生活が、むしろ睡眠の一貫性を保つことにつながっていると解釈できます。
一方、例えば、学業のタスクが多く、アルバイトや一人暮らしをしている学生アスリートの場合には、そういったサイクルを確立するのは難しいでしょう。
また、クロノタイプと呼ばれる、一般的には「朝型」「夜型」と評価される人が自然に持つ体内時計は遺伝に加え、年齢の影響も受け、大学生年代では夜型に移行し、およそ60歳で朝型に戻る人が多いとされています。
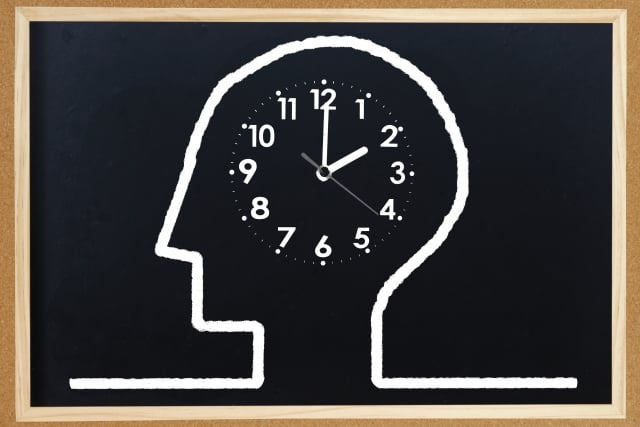
これに基づくと、学生アスリートの場合、仮に睡眠の一貫性を保つ努力をし、早めに寝床についても、すぐに寝られない問題を抱えてしまう人もいると考えられます。
そのような人の場合、朝練習を避けた方が学業とスポーツの両立にはプラスに働くでしょう。
まとめると、朝練習そのものが原因ではなく、朝練習をすることで睡眠時間が確保できなかったり、睡眠の一貫性が失われやすい現実が問題と言えます。
近年では、始業時間の早い1限目に授業があること自体も睡眠や学業にマイナスの影響を与えると言われています。
多くの学生が充実した生活を送るためにも、社会に根強く残る伝統を変え、一人ひとりの体内時計に合った過ごし方を目指す時代が来ているのかもしれません。






























![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)



























