「人の顔を覚えている」とはどういうことか?
私たちはよく会う人の顔を見たとき、自然と親しみの感情を覚えます。
では、この親しみの正体とはなんなのでしょうか?
通常こうした問題を調べる研究では、2Dの静止画写真が用いられます。しかし、今回の研究チームはより自然な状況で、顔を見るという視覚処理と、親しみを感じるという脳機能を確認するために、人気ドラマ「ゲーム・オブ・スローンズ」を用いることを考えました。
このドラマには熱心なファンも多く、繰り返し見ているという人も簡単に見つけられます。
なにより本作を選んだ理由について、研究者は「強い個性を持つキャラクターたちがたくさんいるからだ」と話しています。
研究で集められた参加者も、半数が繰り返しこのドラマをよく視聴する人たちでした。
そこで、チームは参加者にドラマを視聴してもらいながら、そのときの脳の反応をfMRI(機能的磁気共鳴画像法)を用いて測定していったのです。
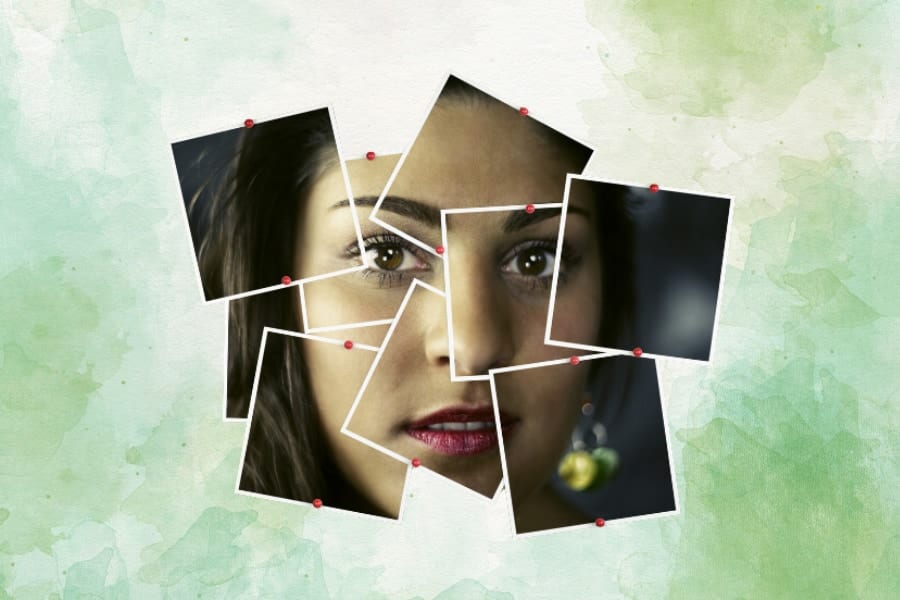
するとドラマをよく見る人達は、馴染み深いキャラクターが登場した際、視覚領域と非視覚領域(意味的情報、エピソード記憶、感情処理に関与する領域)の間での機能的結合が強化されることが観察されました
つまり、顔を見てそれが誰だか認識する際に、私たちは顔という視覚情報だけを頼りにしているわけではなく、その人物を見た際の過去のエピソードや、その際どんな感情を抱いたか、その人物の社会的な立場、という複雑な情報処理を行っていて、両者の情報の結びつきを改めて強化させていたのです。
この結合が活性化すると、私たちはその人物に親しみという感情を感じるようです。
一方で、このドラマをあまり見たことがない人たちは、情報同士の結合があまり強化されませんでした。これはその登場人物にあまり親しみを感じないと同時に、誰であるのかの認識も困難にさせている可能性があります。
これまで顔の認識や親しみの感情は、主に顔という視覚的な情報の処理であると考えられていました。しかし、今回の結果は、それが非視覚領域のかなり複雑な処理も関連しており、両者の結合の強化が大きく関与していると示されました。
そこで、次の研究チームは、この実験を相貌失認症の患者に対しても行い、その結果を比較してみることにしました。
相貌失認(または失顔症)は人口の約2%に見られる脳疾患のひとつです。
症状には軽いものから重いものまで個人差が見られますが、一般的に「人の顔が覚えられない」「知っている人の顔を見ても誰かわからない」といった症状が起こります。
発症の理由は様々で、生まれつき持つ先天性の場合もありますが、外傷や脳血管障害など後天的な理由で発症することもあります。
普通であれば、知っている人の顔をチラッと見るだけで、それが友人だったり家族であることがわかります。
しかし相貌失認であると、知人も赤の他人も含めて、すべての人の顔が同じように見えてしまい、それが誰なのかよくわからなくなるのです。
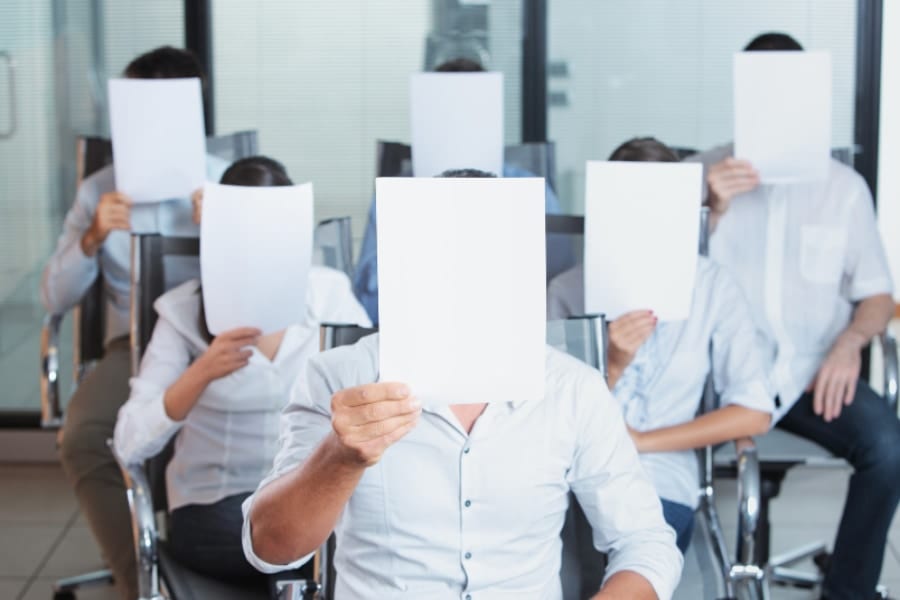
具体的なシチュエーションを挙げれば、
・以前会ったことのある人の顔を忘れてしまって、挨拶されてもよくわからない
・待ち合わせの場所に行っても、知人を見つけるのが難しい
・ドラマや映画を見ていると登場キャラの見分けがつかず、人物関係やストーリーが追いづらい
・学校や職場でよく会う人でも、プライベートに街中で遭遇すると他人に見える
相貌失認にはこのような症状がありますが、その脳メカニズムはまだ詳しくわかっていません。
研究チームは今回の実験を通じて、私たちが人の顔を認識する際にどのような脳機能を使っているかに加え、相貌失認が起こる仕組みも解明しようと考えたのです。
では実験の結果を見てみましょう。
































![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)



























