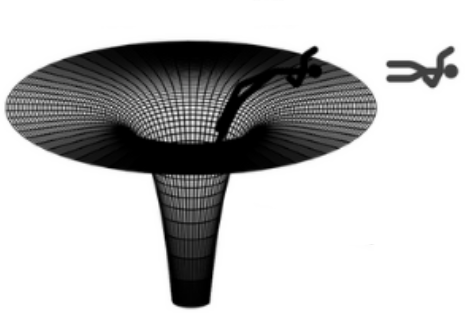ウイスキーの天下だったアメリカ、反社会的な場所となっていた酒場

時は19世紀半ば、アメリカの片隅。ウイスキーの香りが風に乗り、遠くの丘の向こうにまで漂っています。
酒の歴史は社会の歴史であると言わんばかりに、この琥珀色の液体はアメリカの日常を支配していました。
その理由は単なる酔いを求める以上に深いものです。
例えば、スピリッツ信仰と呼ばれる奇妙な思想――風邪や骨折から蛇の咬傷に至るまで、すべてを癒す万能薬としてのウイスキーへの崇拝があったのです。
加えて、経済的事情もまたウイスキーを推し進めました。
開拓が進んだことで広大な中西部で穀物の過剰生産に陥ってしまった農民たちは、その解決としてウイスキーを作り、売ることで生計を立てていたのです。
塩漬け豚肉より収益率が高く、輸送しやすく、腐る心配もない。
誰もが銅製の蒸留器を抱えていた時代です。
しかし、この黄金の時代にも欠点が潜んでいました。
他の飲み物が高価であったことと、利用が難しかったことです。
水は不潔で、ミルクは子ども用。紅茶はボストン茶会事件以降、愛国心の問題で遠ざけられるようになり、ワインはエリート専用でした。
一方でウイスキーは庶民の手に届きやすく、塩辛い豚肉を流し込むにも最適だったのです。
こうして1830年、アメリカ人の酒の年間平均消費量は約36リットルに達しました。
だが、問題は飲み方です。フロンティア精神が混じり合う中、ただ酔いを楽しむだけではなく、破滅的な飲酒文化が生まれたのです。
これにより今でいうアルコール中毒になる者が続出し、これに対抗する形で禁酒運動が始まったのは自然な流れだったのかもしれません。
また当時の酒場は売り上げ至上主義の道を突き進んでおり、決して褒められた場所ではありませんでした。
一日24時間、週7日休みなく営業するその姿は、まさに利益を追求する狂気の沙汰であるといえます。
さらに子どもへの酒の振る舞いすら行われていたのです。
この子どもへの酒の提供についてビール醸造業者協会のスポークスマンは、「子どもに数セント分の酒をおごるのは賢い投資である。その連中が常習的酒飲みになれば、何倍にもなって帰ってくるからだ」とまで語っており、未来への投資として考えられていたことが窺えます。
またその陰では、売春婦や賭博が跋扈し、時には麻薬さえも売られることがありました。































![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)