最上級の親孝行とされた割股

余談ですが唐宋の時代、人々の心を掻き立てた奇妙な儀式がありました。
その名も“割股(かっこ)”。
これは病気に苦しむ親や舅姑のため、自らの股肉を切り取って提供するという、現代人には理解しがたい孝行の極致です。
儒教の論理では、父母から授かった肉体を傷つけることは禁忌。
しかし、孝を尽くすためならば、その禁忌すらも踏み越えてよいという理屈が、この儀式を支えていたのです。
この“孝”の実践は唐代以降、社会の奨励と官憲の顕彰を受けて広まりました。
例えば『新唐書』には、明州のある医者が『本草拾遺』に人肉が病に効くと記したことが契機となり、多くの孝子が自らの股肉を切り取って供したとあります。
一方、割股がさらに時代を超えて活発化する背景には、国家の政策的な思惑もありました。
しかし、割股に対する批判も少なくありませんでした。
唐代の韓愈(かんゆ)は、割股が命を危険にさらす行為であり、万が一命を落とせばそれこそ不孝であると論じました。
それだけでなく、税役を逃れるために割股を行う者もいたと言います。
このように、割股は美徳としての“孝”と実利を目的とする行為の狭間で揺れ動いていました。
仏教の影響も割股の背景には見逃せません。
仏典には、人肉を薬として用いる例や捨身行の思想が記されており、これが割股の思想的起源となった可能性があります。
しかし、唐代の早期には割股を実践する者は稀であり、それを敢えて行った人物は後世の模範とされました。
やがて南宋に至ると、士大夫たちの間で割股に対する意識が肯定的に転じ、道学派を中心に民衆教化の手段として“孝”の概念が利用されるようになりました。
これにより、割股は単なる個人的な孝行の枠を超え、社会的な制度として根付いていったのです。
唐宋時代の割股は、親への孝行という名目で語られながら、実際には社会や政治、宗教の影響を受けた複雑な文化的現象でした。
その血生臭い物語は、現代の我々に、人間の信念が持つ力と恐ろしさを静かに問いかけているようです。














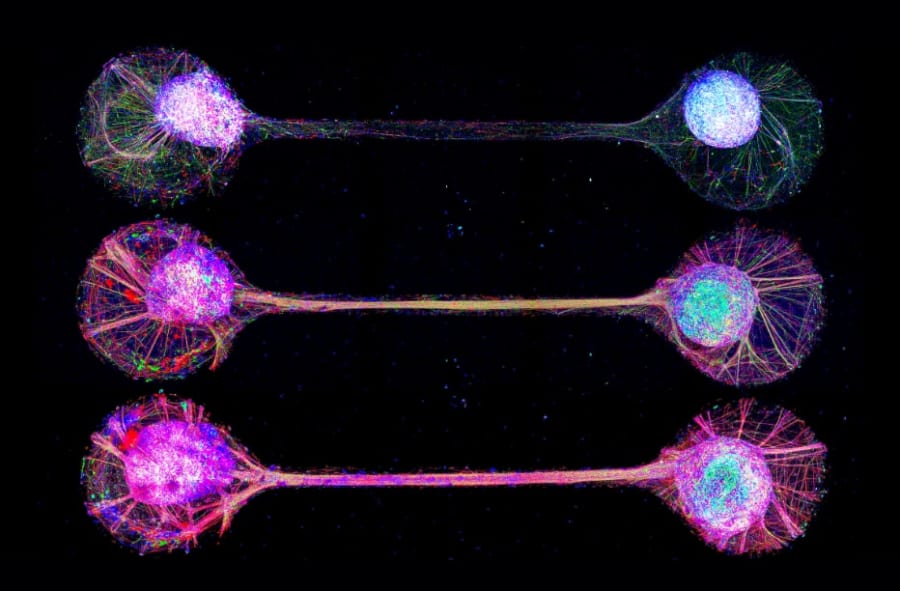


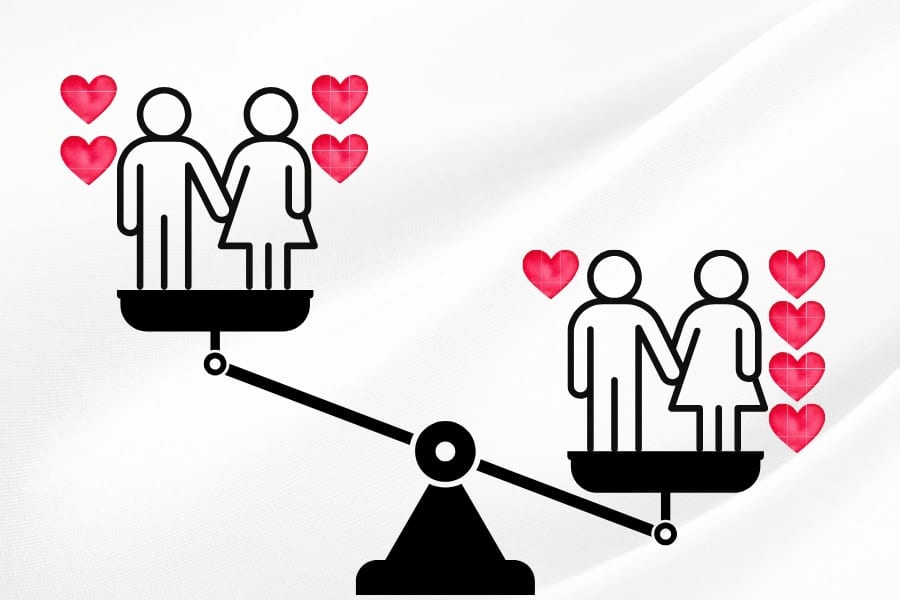












![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
























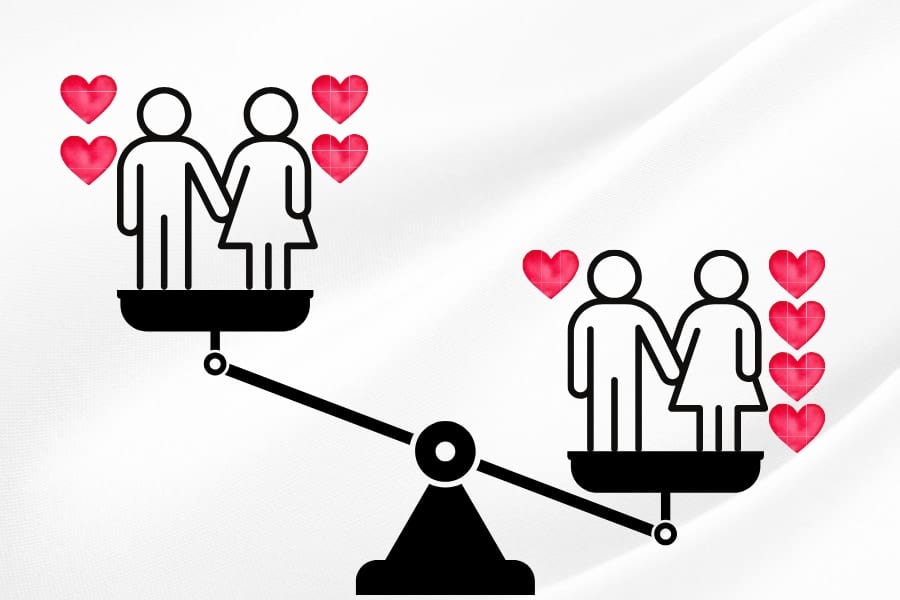



儒教の毒についての本もおすすめです。
儒教の本質と呪縛―社会をゆがめる根源
儒禍―中国二千年の呪縛
黄文雄 (著)
儒教 怨念と復讐の宗教
浅野裕一 (著)
なぜ論語は「善」なのに、儒教は「悪」なのか 日本と中韓「道徳格差」の核心
石 平 (著)
参考にします
両脚羊
魯迅が嘆き孔子も食べてた人肉食
野蛮な行為だわ
でも私たちもセックスをしてるから
輸血や臓器移植に変換してみれば、私たち現代人にも当時の人々の心情が(少しだけ)理解出来るかも。
数百年後には技術も進んでいて、輸血も野蛮極まりない行為とされているかも知れませんね。
『モラル』という人類が産み出した概念は、とかく移ろいやすいナマモノですから。
中国の人肉食事は単に野蛮なだけだ
未開無知残酷な社会の象徴だ
格好屁理屈付けなくてもよい
中国の人肉食事は単に野蛮なだけだ
未開無知残酷な社会の象徴だ
格好屁理屈付けなくてもよい
戦争で食べるものが無くなり
一村襲い村人全員皆殺しにして食べ
村1つ亡くなった此が現実の中国だ
一応日本でも食人文化はあったけどな、他を批判するのがそんなたのしいか?
文化とは社会で共有される習慣や価値観のこと
中国では美談とされほど文化になっていた
日本に食人事件はあっても文化なんてねえよチンク
あらあ
普通に市場で檻に入った人が食べるために売られていたそうですから
自分がそっち側になるかもって想像しなかったんだとうか?
男尊女卑と同じく認められないです。
日本やゲルマンに古代からある人柱の延長バリエーションでしかないなら特別な思想や価値観など要らないだろう、説明であれ正当化であれ
若い時読んだ本のジョーク話。
食糧の尽きた難破船に乗った乗組員達が最終手段で自分自身のチ〇コを切り取って食べようとしたとき、その中の1人が
「待て、みんな!どうせ食べるなら大きくしてから食べようぜ!」
という話があった。
わかりかねる
何の肉であれ、飢え死にしかけた時に食う肉に勝るものなしということか。
楽に往生したいものですね
ガ島の人肉食は戦争の犠牲
雪山遭難でも人肉食があった
フランスの猟奇殺人で人肉を冷蔵庫で保管しながら食べていた犯人(日本人)もいた
人肉は国を問わず散見する
中国だけではない
戦争時も雪山も佐川くんも人肉食は犯罪の範疇だった。善行とみなされていたのが中国。その違いは大きい。
日本でも胎盤を食べる地域があるのも気持ち悪い
美容液とかで聞くプラセンタって胎盤のことなんよね。
悪いけど全く古代の倫理観という問題だけで片付けられる話ではないわ。
秀吉の小田原城水攻めや、ガ島、ホロドモール、アルゼンチン?の航空機事故など歴史的に人肉食が極限の状態で行われたのは事実だけど、それが美談として語られたり積極的に賞味(調理方法まで確立してた)のは世界でも一部の原始的な部族を除けば貴方がたぐらいではないでしょうか。
今の中国人に対し嫌悪感を激しく持っている訳ではありませんが(少なくとも自分は)、なかなか相容れない感情を持ってしまいますよね。この手の話は
こういう記事自体がタブーですよね。実際に本当だったか分からない話しや、未開時代の漢方的な昔の風習とかの話しを持ってきて、人肉の習慣があるだと書いたり、そもそも中国という千にも及ぶ民族と広大な土地の一部をかいつまんで語るのが悪質。一部では非常に残酷な遊牧民に晒されたりと、日本人には分からない感覚も有るだろうに、こんな記事を書くほうが野蛮なら、乗じて中国叩きするネトウヨも自身のほうが野蛮。この記事、人種差別としか思えません。
少なくとも人を騙すのは悪いとするのが日本、騙されるのが悪いとするのが中国、一般論です。
福沢諭吉翁も中国と係わるなと忠告してくれています。日本が中国に手を出したのが運の尽き、1000年は祟ると覚悟をしたほうが良い。
中国に日本がどんなけいやなことされてると思ってるん
何が人種差別なん!
学生の頃今から40年くらい前に何かの雑誌か本かで読んだ記憶があります。昭和初期まで街頭処刑がされた後に縛られた罪人が観衆に肉を削がれて持ち帰られていく激痛を伴う処刑ですよね、根拠や人権なんて言う人は何故それを普通に受け入れられないのでしょうか?疑問です偏見と言われればそうですがそれも文化の一部ではないでしょうか?そもそも中華料理などもゲテモノ喰いが多々ありますもんね、未だに犬なと裏市場で売買さらている国家ですよ。
ここからは私の偏見ですが人喰いはDNAに刻まれると思っています
人喰い熊も子孫が人喰い熊に変異すると言う仮説がでてますもんね、だから中国人は平気に残忍な殺人と残忍な死体処理を行うんだと思おます。
生物学的には、人肉食にはむしろ『クールー病*』という形で、強力な歯止めがかけられる。
*クールー病:(たんぱく質の一種である)プリオンにより引き起こされる脳の病気。プリオンにおかされた脳はスポンジ状に変質・破壊され、痴呆状態や運動障害を経て、最終的には死滅する。
この事実を考えると、「人肉食はDNAに刻まれている」という見解は、勇み足かも、
記事で紹介された古代中国の人々も、その多くがクールー病のような症状を呈した最期を迎えたのでは?
水滸伝にも峠の追い剥ぎが被害者の肉をまんじゅうにして食べていた。と言う記述がありました。
日清戦争後日本が台湾を併合した際、先住民族の高砂族は戦った敵の英雄の肉を喰らいその胆力を自分の実にしていたと聞いている。
この考え方は世界中にあったらしい。
諸葛亮の好物は赤ん坊のピクルスだろ?
今人気のキングダムの登場人物達も祝いの席で人肉をご馳走として食べていた可能性も大いにあるんだよな
まあ、日本でも人肉食いはあったよな。土佐だっけ内臓が薬になるとかなんとかで。
鼻くそ食べるのは人肉食の一種なのだろうか。。
鼻くそ食べると免疫力アップらしいよ、どんどん食べて!人肉食ではないと思うよ!唾液とか鼻水飲み込んでるのと同じ一連の動作だと思うの
火葬後の死者の骨をかじる慣習は日本の各所にのこっているそうな
コメントが、今の中国人が食べている様な話にすり替わっています。
そもそも大日本帝國陸海軍にも戦時下では同じ様な話がある。
戦後の引き上げ時には、一族や村が逃げる為、川を渡る為、見逃してもらう為、10代の女性を戦勝国の兵士に献上した話まである。
史実として、被害者の女性が語っている。
他人を食い物にすると言われれば、風俗や、ホスト、キャバクラ等、沢山ある。
恋人の胸に顔を付けるのも、同じだろう。
猿の脳髄は今だに、食べている人種がある。
犬は、韓国でも売ってるし。
虫は日本各地に自販機や、佃煮も売ってる。
、
話が全然違ってきてるよ
文化として食人が根付いてるってこと
文字通り人の肉を食べるってことで
比喩の話じゃないんだよね
犬とか虫とか関係ないよ
中国は、人口が大きいので人肉食の実現も多くなるのではないか。そうすると飢餓対策のようなやむを得ないもの以外の猟奇的なものも現れ、目立つから記録にも残りやすいのでは。
どれも騎馬民族に
政権取られていた頃の話じゃないか。
近年、美容で耳にするプラセンタ。これは日本語で「胎盤」という意味。
つまり、ヒトプラセンタとは…
げに恐ろしき美の探求。
文章として残っていたならば、中国の食人が文化として残っているように、バイキングの残酷なやり口も文化に残っていて、遺伝子にも残っているのかも?
二足羊の名前でヒトを捌いて売ってたり、清朝末期まで凌遅刑(生きながら罪人の肉を削ぐ)やってたり
前の皇帝や王朝を倒して新しく権力を握った側が自己の行為を正当化するために野蛮性や残酷性、退廃性を捏造・誇張するのはよく聞くが美談とするのはあまり例を見ないな
笑止
欧州人のプリオン抗体比率をチェックしたら?
ちなみに食人族は55%
あら不思議~中国人の僅か3%に対し日本人のプリオン抗体比率はなんと!6.4%でした!残念!
チャンケの記事になると途端にキメェサヨクがワラワラ沸くこと…
あなたもかなり気持ち悪いですよ
漢方薬で、ヒトの体の一部を原料とする生薬がいろいろあるそうです。日本薬局方が整備される前は日本でも輸入されていたそうですが、中国では、今も流通や生産がお紺われているのかしら?
かつて、新型コロナウイルスの起源を探るドキュメンタリー番組で、武漢市の青空市場で、死んだ野犬、サル、センザンコウが売られているのが放映されました。家庭レベルでの野生動物の解体や肉食の敷居が低いのかもしれませんね。
忌避されるべきは殺人そのものであって食人がなぜ特別にタブー視されるんだろうか
ムリムリムリムリムリムリムリムリ