不和が発生し「2つの派閥」に分断、8名が迎えた最期とは?
食糧も満足に得られず、酸素が薄くなるにつれ、クルーたちの士気が低下し、精神的な疲労が目立ち始めました。
ネルソンは「無駄なエネルギーを使う余裕がないので、私たちはまるでスローモーションのダンスをしているように緩慢に動いていた」と話します。
さらに地獄だったのは、このプロジェクトが当時からメディアの注目を受けていたため、実験を一目見ようと、多くの人々が毎日のように押し寄せていたことです。
施設は太陽光を入れるために全面ガラス張りでしたから、クルーたちは常に人目にさらされていました。
クルーの一人であるリンダ・リーはこう話しています。
「毎日、観光客や学校の子供たちを乗せたバスがやって来てはガラスを叩いたり、やせ細った私たちの写真を撮っていました。
一度、動物行動学者のジェーン・グドール(チンパンジー研究で有名)が訪れて、まるで私たちを囚われた霊長類のように観察していました。
ガラスにコップを投げられたり、唾を吐かれることもありましたが、幸いなことに暴力は起こりませんでした。
次第に私たちの間でも冷たい空気が張り詰めて、お互いに近くにいたくない、そんな雰囲気に飲み込まれていきました」

ついにはクルーの間に集団的な対立が勃発し、2つの派閥に分かれます。
「酸素や食糧を外部から送ってもらうべきだ」とする派閥と、「いや、実験を完遂するために自分たちで乗り切るべきだ」とする派閥です。
双方互いに譲ることなく、当初は親しい友人同士だったはずのクルーたちが、今や仕事に必要な最低限の会話を交わすだけの仲になってしまいました。
しかし酸素濃度の低下は収まらなかったため、結局は外部と連絡を取り、酸素と食糧を供給してもらっています。
この時点で実験開始から16カ月が経過していました。
ただ酸素と食糧が得られたクルーたちは目に見えて元気になり、「みんな突然大笑いしながら走り回っていた」とネルソンは話します。
また彼はこう続けました。
「まるで90歳の老人から10代の若者に戻ったような気分でしたよ。それで、ふと気づいたんです。『そういえば、何カ月も誰かが走る姿を見ていなかったな』ってね」
それほどにバイオスフィアの住人たちは弱りきっていたわけです。

最終的にクルーたちの仲も元通りに戻りましたが、「閉鎖空間の中で自力で生きられるか」という実験目標は失敗に終わりました。
これ以上続けても危険であるため、バイオスフィア2は実験開始から2年後の1993年9月26日に終了。
また1994年に第2回が実施されたものの、わずか半年で終了しています。
当初の構想ではクルーの交代制で100年継続する計画でしたが、望んだ成果は得られず、プロジェクト自体も幕を閉じました。
では、バイオスフィア2の施設はその後どうなったのか?
1994年6月、2回目の実験の途中で運営会社が解散し、施設は宙に浮いた状態となりました。
一度は住宅や店舗建設のため取り壊される予定も持ち上がりましたが、2011年にアリゾナ大学が研究用施設として所有権を取得。
現在では、月や火星で野菜を栽培する方法を調べたり、生命のない土壌が数年かけて肥沃な土壌に変わるプロセスを解明する研究が続けられています。
今の段階では、他惑星にドーム型の居住室を作ったとしても、そこで人類が何十年、何百年と暮らしていくのは難しいのかもしれませんね。































![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)





















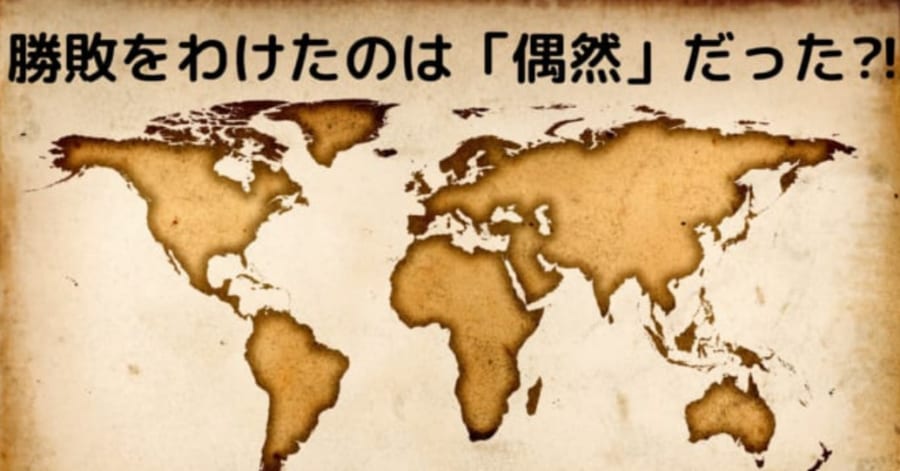






普通に前提条件用意するのに失敗しただけじゃん
それにこういう手の実験はセックスの話以外は聴きたくないね
叩くだけの人生。悲しくならんのかね
失敗から得るものも大きいでしょうに。そもそもあんたは失敗せずに生きて来られたのか?
おそらくだけど自慢できる人生ではないよね
極限状態で繁殖に意識向くわけないじゃん
全裸サバイバルとか知らないの?
こういうのがガラスにコップ投げたり唾吐きかける惨めな人間なんだろうなと
酸素14%みたいな低酸素状態でそんな体力使う行為できるわけないし、聞いたとこでどうすんの?
どうせ慰めるしかできないのに
コンクリートの地面が諸悪の根源
ここさえクリアすれば、酸素濃度も減らず、もう少し何とかなったんじゃないだろうか
とりあえず酸素だけは外から供給することにしてもう一回やってみれば良かったのに…
同じような施設を複数同時に運用しないと優位な結果は得られません。
コンクリートの閉鎖系では生きていけないというのが分かったのだから大収穫じゃない?
それにコンクリートなんて宇宙に持っていけないでしょ?
目的を達成させられなかった、という点では完全な失敗だけど、そこから知見を得られるか、どう活かせるか、が大事だと思う。AIなんかも理論が出たころは荒唐無稽なほとんどsfな話だったのがいろんな要素が進歩して実用になっている。
このコンセプトも今、あるいは未来の技術でやれば違う結果、知見に。
でも今の世相だと確実に結果が見えるようなプロジェクトだけ通って不確実性の高いのは実現できないんだろうな。
失敗から学んで、コンクリートの件をクリアした施設で実験しないとね。
問題がクリアされたであろう二回目の実験の顛末こそ、興味ある。
コンクリート材料は火星にもあるから、現地で手に入るのに、それがダメだとなると何を材料に文明作るか手詰まりだな。
見学者が見に来るのはメンタルによくない。
せめてカメラ越しでないと。
この記事には書いていないけど、施設の中に風が吹かないので樹木がしっかり育たなかったんだよな。風が吹いてこそ根とか幹が逞しくなる。
コンクリートな、強度上げるために
『石炭灰・フライアッシュ』を混ぜている。
コレには、トリウム、ラジウム、天然ウランが濃縮されてるんよ。
閉鎖してしまうと、核壊変して放射性ラドンガスが発生する。コレは3日でアルファ線を放出して鉛になる!!!
除去するシステム組まないと、鉛中毒が容認出来ないレベルになる。
確かに
コンクリートの石炭灰の含有量は最大でも30%。そして石炭灰から放射性物質の回収は含有量が少ない為行われていない。
水銀の方がより高濃度で含まれているが無機水銀の為有機水銀より危険性は低く、水俣条約の規制も受けていない。
門外漢が的外れな事を抜かすな。
そろそろこの時の失敗経験を活かしてよりサスティナブルな実験をやってもいいのでは?
閉鎖空間でさえ最初は上手くいってたのに
お前らときたら…
コンクリにシートでも被せるなりして内部の酸素を消費しないように改善して再実験をするべきだったのでは?
色々と惜しい実験だなと思いますね。
実験の設備、人数の規模が小さすぎました。生態系を創ってそれを自活できるようにするには数桁分巨大な施設と資源が必要でしょう。8人という小規模世界ならISSやソユーズのようにすべてのリソースを外部から持ち込むはずです。それは前哨基地であって生活圏=村落~都市ではありません。ただこうした長期的視野に立った実験&訓練を計画・出資する人がいなくなることはないでしょう。ムーンベースアルファの実現を楽しみにしています。
いかにもアメリカらしい発想の大規模な実験で、始まった当初から注目していました。一部始終が本にまとめられ、日本でも翻訳の文庫本が昔売られていました。面白かったです。
あれだけの巨大施設でも、例えば光合成で酸素を一定に保つのは困難と分かり、実は実験中にかなり大気を入れ替えています。すると例えば将来、宇宙船で火星に往復する場合はどうするのでしょうか。
バイオスフィア2に比べれば、宇宙船は極端に小規模な空間で、往復2年半に及ぶ飛行時間に消費する酸素をすべて持っていくのは困難です。かといってこの実験によると、光合成を使って安定供給するのも想像以上に難しそうです。トランプとマスクは「月なんか飛ばして火星に一番乗りする」とか言ってますが、もっと基礎技術を見直す必要があるのでは。
拙くお粗末な前時代の実験に過ぎない。
環境管理という概念はなく、モニタリングすら不十分。
そもそも、閉鎖環境という命題を掲げるなら、なにも人工的な調整を放棄する必要性はない。
にもかかわらず、そこを履き違えて何故か「自然に任せる」ことを選択したため失敗した。